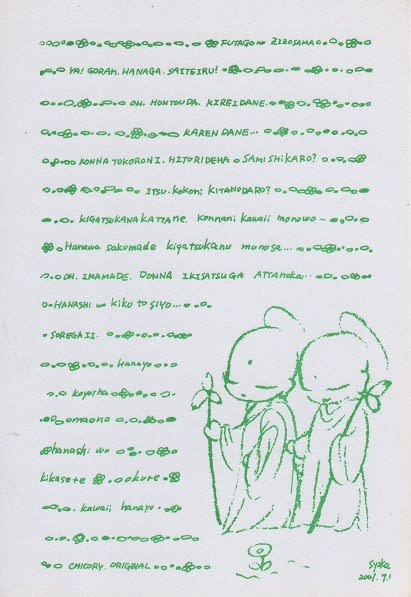先日のことです。
遠い昔の、辛い思い出のある場所を、ふとした偶然から再び訪れるという出来事がありました。
子供の頃、何も知らぬまま、見捨てられた心を自ら傷つけ続けていた、そんな日々があった場所でした。
住む人のみが変わって、建物は変わらぬまま。でも周囲の風景は、すっかり変わっていました。
じめじめした陰気な場所だと思っていた竹藪はなくなって、小ぎれいな家々の並ぶ小道に変わっていました。広々としていた畑には、いくつもの家が点々と並んでいました。お化けの出てきそうな古い神社は、建て直され、参道もきれいに整備されて、清々しい広場に変わっていました。
そして、見上げると、いつも黄昏のように暗かった記憶の数々を、ぬぐいさるようにきれいな、あきれるほど澄んだ青空。
なんてことだろう。
思い出は、何も浮かんで来ないのです。涙さえも出ないのです。ビニールのきれっぱしのような薄っぺらな記憶が、一つ流れて消えただけ。あれほど辛かった日々の痕跡は、嘘のように消えていました。
変わったのは、私なのか、風景なのか。
それとも社の木々をなであげる風が、記憶をみんなさらっていってしまったのか……。
瑠璃色の秋空は、想いを吸い上げるばかり。ただどこかから、甘くしょっぱい高まりが、静かに胸に押し寄せてくるのです。
ああもう、引きずっていなくていいのだ。あれは終わったことなのだ。夢の向こうに消えたことなのだ……。
どんな恨みつらみもいつかはみんな、こんなふうに風が食べてくれるのでしょうか。どんなことがあっても、人はいつか、みんなわかりあえるのでしょうか。
まるで、何度も水にさらされて得た金の一粒のように、小さな昔の自分は、私の胸の中で微かな痛みとなって、今も生きています。
(1997年11月ちこり11号、編集後記)
ゆくへなき
ゆくへなき この身いづこに あづけむと さすらひびとの 影を描く月
とほき日の 雪に凍える 炭の目の わらはの魂よ 古家に憩へ
ひとひらの てふを小箱に とぢこめて 君に寄すこの 謎解きたまへ
すでになき ものをたよりと 背もたれて くづれゆく身の ゆくへを知るか
梅が枝に とをとひとつの 小鳥ゐて ささやきこめる 星のことのは
乾ききる 砂をグラスに ついで飲む 鉛の肺に 降り積もる虚無
蒼穹に 星組みて野に 愛の散る 白百合は待つ 受胎のここち
背を向けて 風の岩戸に 去りゆかむ 追ふものもなし たそがれの星
きぐるみの おのれを踊る うつせみの 世は一幕の かげろふの歌
ゆふやみの しづかにおりて 石のごと 重き荷となる 立てずとも立て
高光る 日のしたたりの 胸に映え さいはひに似し 孤独の痛み
(2012年、歌集「玻璃の卵(はりのかひ)」より抜粋)
あなた
わたしのことばのなかに
あなたの愛が流れてきて
不思議な詩が
小鳥のように歌う
小さな宝石を並べて
海辺で拾った貝や
川辺で拾った石を並べて
石畳で拾った赤い落ち葉や
野の隅で咲いていた花などを
貼りつけて
かわいい詩を書いた
わたしは わたしのなかの
小さな心の鈴が
喜ぶ詩を書いて
死にそうなわたしの心を守っていた
その詩の中に
いつかしら あなたの言葉が
流れてきて
いつの間にか あなたが
わたしの詩を書いていた
ああ わたしを
生かしてくれていたのは
あなただったのですね
さびしいと思うときはあるよ
わたしの歌う風の声は聞こえない
けれどあなたの声は暖かい
いつの間にか
傷だらけだったわたしを
ささえてくれていたのは
あなただったのだ
生きているわたしを
繭の中で眠る赤ん坊のように
あやしながら
わたしは静かに歌う
あなたの愛の中で
しばし
物語の 本当の
終わりが来るまで
(2012年頃、詩集「カシオペア」より)
生まれる前の話
そこは、見渡すかぎり、花の野原でした。
のばらや、ツユクサ、クリンソウ、ヒオウギ、タンポポ、ヒメスミレ……。じゅうたんのように、一面に、一面に、咲いています。ところどころ、木々が、緑のこずえをさやさやとなびかせ、細腰を優雅に曲げて立っています。ちょろちょろ流れる小川のほとりでは、かわいらしい野苺の実も、まるで小人のともしびのように、ぽちぽち赤く光っています。
こどもたちも、たくさん、遊んでいました。花をつんで首かざりを作ったり、小川でカニをつかまえたり、チョウチョウとおいかけっこをしている子もいます。れつを作って、木にしつらえたブランコの順番を待っているこどもや、爪に花の汁をすりつけて、お化粧ごっこをしている子、高い木の上にのぼって、ただ遠くを見ている子、ねころんで、アリの行列を一心に見つめている子……。たくさん、たくさん、います。それに、先生のような大人の人も、何人か見えます。
さて、ここはどこでしょうか? ここは、幼稚園なのです。でも、普通の幼稚園とは、ちょっとちがいます。この幼稚園のこどもたちは、みんな、生まれる前の、こどもたちなのです。そう。おぎゃあと、赤ちゃんになって、おかあさんから生まれてくる前、こどもたちはみんな、ここにいたのです。いつか生まれてゆく日の、準備をするために、こどもたちはここで、いっしょに遊んだり、勉強をしたりします。花をつんだり、小川で水遊びをしたりしながら、いよいよ生まれてゆくときは、どんな感じだろうとか、生まれたら、どんなことをして遊ぼうかなあって、どきどき、わくわく、しながら、考えているのです。
え? そんなところ、見たことも聞いたこともないって? それはしかたありません。この世に生まれてきたら、ほとんどの人は、この幼稚園のことを、すっかり忘れてしまうのですから。
空は、青いというより、あわい虹色に見えました。それは、霧のようなふわふわ雲が、子供たちの歌う不思議な歌にそめられて、ぽわぽわと色で歌っているからです。小鳥も、たくさん飛んでいます。耳をすますと、ヒバリの声が、ちりちりちりちり、まるで心の中に、じんじん溶けてくるようです。あの雲の向こうから、時々ちらりと見えるやさしいお顔は、お月さま? それとも、お日さまかな? こんなにあたりは明るくて、あたたかいから、お日さまにちがいない。でも、あんまりやさしくて、静かな光だから、なんだか、まちがえてしまいそう……。
空を見あげて、きょとんと首をかたむけたのは、フゥちゃんです。フゥちゃんは、ついさっきまで、夢中で花をつんでいました。フゥちゃんの好きな、のばらの花のかんむりを、三つも作ったのです。一つは自分でかぶって、さて、あとの二つは、誰にあげましょう?
そのとき、野原に風がそよそよ吹いて、先生の声をはこんできました。
「みなさん、あつまりなさい。もう遊びの時間は、おわりましたよ」
ふりむくと、ゆるやかな丘のてっぺんで、先生が手をふっています。フゥちゃんは、かんむりの一つは、先生にあげようと思いました。そして、一生けんめい、走って、丘をのぼりました。みんなも、遊んでいたのをやめて、いっせいにのぼってきます。
フゥちゃんは、一番最初にせんせいのそばに走っていきました。先生は、白いドレスのような服を着た、ほっそりとした女の人です。にこにこわらっていて、きれいな苺の耳かざりと、白い花の胸かざりをつけています。フゥちゃんは、先生に、のばらのかんむりをあげました。先生は、ありがとう、とにっこりわらって、かんむりをかぶってくれました。
みんなが、先生の前に集まりました。
「みなさん、あつまりましたね。さあ、ここにいるのは、来年の一月生まれの、こどもたちです。みんな同じ、一月に生まれるのですよ。そして今日は、十二月三十一日。神さまがみなさんに、いのちをくれる日です」
みんなは、わあっと声をあげました。うれしくって、とびあがる子もいます。ちょっと不安そうに、もじもじする子もいます。
「ほら、後ろをごらんなさい。小川のほとりに、どなたかいますよ?」
先生が指さすほうをふりむくと、そこには、茶色の、すその長いコートを着た、白いひげのおじいさんが、小川のほとりで、ゆったりとすわって、手をふっていました。
「あれ、神さま?」
こどもたちのだれかが言いました。先生は笑ってうなずきました。こどもたちは、さざ波のように、うきあしだちました。神さま? あれが神さまだって! ウワァ……。
「みなさん、静かに、さあ、行儀よくならびましょう。急がなくても、神様はちゃんと待っていてくださいます」
先生にしたがって、こどもたちは一列に並びました。そして、神さまのところまで、そわそわ、そわそわ、歩きました。それぞれに、つんだ花や、木の実や、チョウチョウなどを、いっぱいもっています。それらはみんなこどもたちが、この世にもっていく、おみやげになるのです。ほら、生きていると、つらいこともあるけれど、一生に何度か、とてもうれしい、きらきらしたできごとがあるでしょう? それはこのときに幼稚園でもらった、神さまのおみやげなのです。
こどもたちの行列が、神様の前にたどりつきました。近くで見ると、神さまは、まるで小山のように大きくて、みんなちょっとびくびくしました。高いところにある。神さまのお顔は、なんだかよく見えないけれど、笑っているような気がします。
「みんな、楽しかったかい?」
神さまの声は、深い山の上から降りてくるこだまのようなとてのやさしい声でした。いたずらなこどもがひとり、「神さま、どこにいるの? お顔が見えないよ!」と叫びました。すると神様は、「おやおや、そうかい」と言って、わさわさと音をたてながら、野原の樫の木くらいい、小さくなってくれました。こどもたちは、よろこんで、ぴょんぴょんはねました。
かみさまは、右の肩に白いうさぎを、左の肩に灰色の子犬をのせています。ほほ笑んでいるお顔から、音のない水のように、白いヒゲが流れています。目も遠いお山の青い峰のように、清らかです。手は大きくて、強そうで、白いつえをにぎっています。よく見ると、茶色のコートは、地面にさわるところで、溶けるように消えていて、神さまはまるで、ほんとうに、お花の野原から生えてきている、木のようでした。
「さあ、みなさん。これから神さまが、命をくださいます。順番に、神さまの前に出たら、右手か左手の、どちらかの手で頭をなでてくださいと、いうのですよ。ほらごらんなさい。神さまの右の肩にはうさぎが、左には子犬がいますね。うさぎの名は『幸福』といい、子犬の名は『試練』といいます。幸福とはしあわせのこと、試練とは苦しみのことです。もし、神さまが、右手で頭をなでてくれたら、きっと幸せの多い人生を授かるでしょう。けれどももし、左手で頭をなでてくれたら、苦しみの多い人生となるでしょう」
先生が、言いました。みんなはざわざわとざわめきました。
れつの真ん中あたりで、フゥちゃんはどきどきしていました。神さまは、のばらのかんむりを、かぶってくれるでしょうか? フゥちゃんのささやかなおくりものを、よろこんでくれるでしょうか?
こどもたちは、つぎつぎと、頭をなでてもらいました。みんな、右手でばかり、なでてもらっています。それはそうです。しあわせになりたいと思うのは当然のこと。頭をなでてもらった子は、一瞬、白い光にふわりとつつまれ、たんぽぽのたねのように体が浮いて、つぎつぎに小川のむこうに飛んで行きます。小川の向こうは、いつしか綿のような白い霧におおわれていて、目をこらしても、みんなどこにいってしまったのか、わかりません。でもきっと、どの子も、やさしいおかあさんやおとうさんのところに、生まれているでしょう。そして、宝物のようにだいじにされて、しあわせに笑っているのでしょう。ああ、はやく、順番がこないかなあ。こどもたちは、ためいきばかりついて、じりじり待っています。
けれど、フゥちゃんは、ふと、気づきました。順番が近づくにつれ、神さまのお顔が、何だか少し、さみしそうに見えるのです。
「神さま、右手でなでてね」
「ぼくも、右手で。いいことがいっぱいあるように!」
「わたしも右手! くるしいのは、いやだもん!」
こどもたちは、つぎつぎに言います。そのたびに、神さまは、
「ああ、いいとも、みんな楽しくやっておいで」
と言って、やさしく、右手で、頭をなでてあげるのでした。左手は、ずっと、つえをにぎったままです。白いうさぎは、せわしなく口をもぐもぐさせたり、目をぱちぱちさせたりさせたりしていますが、子犬はずっと眠っています。
フゥちゃん、神さまの顔ばかり、見ていました。自分の前の人数が、すくなくなっていくにつれ、神さまがフゥちゃんに近づいてきます。最初は、気のせいかなぁとも思ったけれど、だんだん、順番が近くなるにつれ、胸に水がしみこんでくるように、フゥちゃんにはわかってきました。神さまは、さみしいのです。なんだかわからないけれど、さみしいようなのです。
(どうしてかなあ。神さまは、しあわせじゃないのかなあ。かんむりをあげたら、よろこんでくれるかな)
そうこうしているうちに、フゥちゃんの番がやってきました。先生に言われて、はっとしたフゥちゃんは、あわててのばらのかんむりをさがしました。でもかんむりは、どこにもありません。ぼんやりしているうちに、落としてしまったのでしょうか?
「さあ、どちらの手で、なでようかね?」
神さまが、やさしく、いいました。フゥちゃんは、神さまを見上げました。右肩の、うさぎも、ちらりと見ました。次に、左の子犬も見ました。最後にもう一度、神さまの顔をみました。神さまは、やさしくわらっています。でも、やっぱり、まるで氷のつぶのような、さみしいきもちが、神さまのひとみの奥から、フゥちゃんの胸に、ぽつぽつと落ちてくるのです。フゥちゃんは、なんだかたまらなくなって、思い切ってたずねました。
「神さま、どうしてさみしそうなの?」
「おや、おまえには、さみしそうに見えるのかね」
「うん」
フゥちゃんがいうと、神さまは、とてもあたたかい笑顔で、フゥちゃんを見下ろしました。でも、フゥちゃんの問いには、答えてくれず、ただだまって笑っています。
「……のばらのかんむりを、あげようと思ったの。でお、落としちゃったみたいで、どこにもないの。あっそうだ、まだひとつあった。ほら、これ!」
フゥちゃんは、自分のかぶっているかんむりを外して、神さまにさしだしました。でも、神さまはゆっくりと首を横に振りました。
「それはおまえのものだから、おまえがもっていなさい」
フゥちゃんは、こまった顔をしました。もう、あげるものがありません。どうしたら、神さまの、うれしい顔を、みることができるでしょう。フゥちゃんは考えこみました
「さあ、どちらの手でなでようかね?」
神さまが、もういちど、いいました。フゥちゃんは、ふたたび、神さまを見上げました。もしかしたら、神さまは、右手でばかりなでるのが、いやなのかな? そしてフゥちゃんは、神さまの手をみて、はっとしました。どうしたのでしょうか? 神様の右手はふっくらとした左手にくらべると、とてもやせこけて、まるでイバラでひっかいたように傷だらけになっていたのです。
その痛みが、ひりひり心にしみてくるようで、フゥちゃんは、泣きたくなりました。そしてまた、考えこみました。
(どうしよう。しあわせのほうがいいなあ。でも、神さま、痛そう。ずっとがまんしてたんだね……)
考えに考えたすえ、フゥちゃんはとうとう、いいました。
「……神さまが、きめて」
すると神さまは、はっとしたように、目をみひらきました。
「わたしがきめていいのかね?」
「うん、いい」
フゥちゃんは、神さまをまっすぐにみあげて、きっぱりといいました。すると、急に、フゥちゃんのまわりは、深く、深く、海のように、ゆたかな、神さまの吐息に、満たされました。神さまは、かなしげな、それでいて、うれしげな、とてもふしぎな、ひとみで、フゥちゃんをみつめかえしました。涙が、ひとつぶ、ふたつぶ、ふってきたような気がします。フゥちゃんは、ぼんやりと、みとれました。なんときれいな、なんとやさしい、目なのでしょう。
「かわいい子よ」
それは、海の底からひびいてくるような、深い声でした。そして、神さまは、ぐらりと、山のように体ぜんたいをゆらしました。
「……おまえの、とおい、とおい、真実の、しあわせのために」
声は、まるでやわらかい風の布のように、フゥちゃんのたましいを、やさしくつかまえました。なんだか気持ちがよくって、頭の中がぼんやりします。かすかに、子犬が、動いたような気がしましたが、フゥちゃんはもう、目を閉じてしまったので、神さまがほんとうはどちらの手でなでてくれたのか、わかりませんでした。ただ、神さまの手はとても大きくて、暖かくて、まるでフゥちゃんのすべてを、つつみこんでくれるかのようでした。
これは、フゥちゃんの、生まれる前の話です。わたしは、フゥちゃんが十才のときに、この話を、フゥちゃんから、聞きました。おぼえていないはずなのに、なぜかおぼえてるのって、フゥちゃんは笑っていました。神さまも、ときには手ちがいをするのかもしれませんね。
フゥちゃんの左手は、生まれつき、動きません。目も、あまり、見えません。今、フゥちゃんは二十才。昼は会社で働いて、夜は学校で勉強しています。
わたしは、天気のいい日には、よくフゥちゃんといっしょに、青空の下でおべんとうを食べます。こどものときから、とてもいいともだちなのです。
「きっとわたしは、右手でなでてっていった口だね」
わたしはいつも、いいます。フゥちゃんは、だまって笑っています。
「フゥちゃんは、どっちの手で、なでてもらったと思う?」
そうわたしがきくと、フゥちゃんは、少し首をかしげて、いいます。
「さあ、わからない。たしかに、つらいことやくるしいこと、たくさんあったけど……。でもわたし、今は、ほんとうに、あれでよかったと思ってるの」
「神さまが、よろこんでくれたから?」
「ううん。……神さまのきもちが、わかったから」
そういうと、フゥちゃんは、青空を見上げて、きらきらと、笑ったのです。わたしは、あのときほど、にんげんの、ほんとうに、しあわせそうな笑い顔を、見たことはありませんでした。
(2000年ごろ、旧ブログより)
レモン
心を静かに整えて
欲を少なくしていましょう
美しい人よ
すえた我臭の泥沼に
身を浸してまで
その底で揺れる
琥珀の檸檬に
手を出してはいけません
あれは琥珀などではなく
沼にうつる金の木漏れ日
哀しみに全てを失ってしまう前に
瞳をあげ
あの空一面の
花の野をごらんなさい
沈黙の奥に折りたたんだ
あなたの水晶の心臓を
今 布のようにいっぱいに広げ
風の中に溶け込む
美しいこの星の香りに
さらしましょう
魂に風がとおり
心が澄みわたる
閉じ込められていた小鳥が
あなたの中で金の歌を歌いだす
あなたが求めていたものの
全てがそこにある
ひとつの星
こよい すべての星が
ひとつの星を見ている
花をもつ鳥を生み
地上に祝福をなげかける
透明な鐘を鳴らし
ひそやかに生まれてくる赤子に
ささやきかける
こよい すべての星が
ひとつの星の
めざめるのを見る
(2006年、南野珠子詩集「ひとつの星」より)
ばら
楼閣のように
巨大な ばらが
大空に 描かれるように
それは
何度消しても 消しても
くりかえし
描かれるように
わたしの中で
それは
叫ぶのです
ちきゅうが
かわいらしくて ならない
ひとびとが
いとおしくて ならない
ああ
どうすれば いいのか
わたしの 奥の 奥深く
光る きわみから
つるされる 無数の
存在の
すべてをかけて
それは 叫ぶのです
のうみつな 光の汁を
まるめて つくった
山ほども 大きな
赤ん坊が
わたしの中に
打ち捨てられて いるように
それは いつまでも
叫びつづけるのです
(2002年、種野思束詩集「種まく人」より)
死の河の森
これは、世界がまだ赤ん坊のように無垢だったころの話だ。あるところに、若い王と王妃がいた。王は聡明で、王妃は美しく、国は豊かで、人々は温和だった。これは、信じられないほど、世界が明るかった頃の話だ。
死の河を超えて
来れ我が元に
絶望のなせる業ではなく
自らの王として
ある日、王が書斎で書き物をしていたとき、ふと、きれいな若い女の歌声が、耳に入ってきた。彼は、ペンを持った手をとめて、窓の外を見た。よく晴れた水色の空に、羊色の雲が優雅に浮かんでいる。
(やれやれ、しょうがない人だ。よほどあの旋律が気に行ったのだな)
歌声の主は、彼の若い妻であり、この国の王妃だった。ひと月前に結婚したばかりのなりたての王妃は、儀式の時だけに歌う習わしの代々王家に伝わって来た歌を、こんな風に軽々と口ずさんでしまう。
彼は机の上に広げていた書物を閉じると、明るい日差しのさしこんでいる螺旋階段を降りて、城の中庭に出た。
王妃は、中庭の芝生に座って、歌を口ずさみながら刺しゅうをしていた。彼女の傍らには、白樺に似た一本の細い灌木が植えられてあり、それは柔らかな木陰を作って彼女を包んでいた。
王妃は、夫の姿を認めると、はっと口をつぐみ、刺しゅう枠をおいて立ち上がった。そしていたずらを見つけられた子供のように目を伏せた。
「ごめんなさい、つい、口から出てしまったのですわ。だって、とてもきれいな歌なんですもの」
王は何も言わず、彼女に歩み寄った王妃は叱られてしまうと思って、思わず首をすくめた。王は、王妃の肩に手をかけると、傍らの気を指さして、やさしく言った。
「この木のいわれを、まだあなたに話していませんでしたね」
「え?」
王妃はきょとんとして、王の顔を見上げた。
「この木は、我が王家に伝わる大切な宝なのです」
王は木の幹をいとおしげになでながら、こずえを見上げた。
「昔、まだこの国がそれほど豊かではなかったとき、一度、大変な飢きんが国を襲ったことがありました。たくさんの人々が飢え死にしてしまい、それを悲しんだ我が王家の祖先が、神に会うために、死の河のほとりまで旅をしたのですよ」
「死の河?」
「ここから、南に向かって五百日、次に東に七百日歩いた所にあると言われる、神が住んでおられる国と、人間の住んでいる国を隔てている恐ろしい河のことです。人はみな死ぬとき、一度だけその河を超えるといわれるのですが、生きている人間がそこにたどりつくのはひどい難行なのです。ですが、祖先の王は幾多の苦難を超えてそれをなしとげました。そして神は、王の献身に報いるために、この神聖なる木を、この国の永遠の豊かさと幸せのしるしとして王に与えたのです」
「まあ」
「ですから、この木がここにあるかぎり、国は永遠に豊かで、平和なのですよ」
日が陰ってきたので、やがてふたりは城に戻り、いつものように塔に登った。当のてっぺんのバルコニーに出ると、国中が、一望に見渡せるのだ。西に、静かで美しい湖、東に美しい緑に覆われたなだらかな一群の丘、北には険しい山があり、そこから流れる河が、いろとりどりのモザイクのような街並みを縫って走りながら、湖に注いでいる。南には果てしない平原が広がっている。
この風景を見るたびに、王は思う。この豊かさ、この美しさ、この幸せ、これこそが、正しいのだ。いったい、この世界のどこに不幸せというものがあるのだろう? どおに醜く汚いものがあるだろう。いや、ありはしない。神との約束を守っている限り、この幸せは永遠に続くだろう。それこそが、我々人間が真実をつかんでいる証拠なのだ。
王は、王妃の美しさと、国の豊かさと同じように、己の正しさを信じていた。
さて、ある夜のことだった。窓からさす月の光があまりに明るいので、王はなかなか寝つかれず、何度も寝返りを打った。
このままではとても眠れそうにないので、王は仕方なく、眠くなるまで中庭の散歩でもしようと、起き上がった。
庭に出ると、白く丸い月が、しんと空の真ん中に座していた。夜の闇にミルクを混ぜたような静かな光が、中庭を照らしていた。夜気の中を、王は芝生を踏みしめながら、ゆっくりと歩いた。ふと、王は、どこあらか、しゃり、しゃり、という、妙な音がするのを聞いた。
(おや? なんだろう)
彼はその音がするほうに耳をすました。風の音ではなさそうだ。虫の声とも違う。何やら、まるで、何かがものを食べているような……。はっと、王は、その音があの聖なる神の木の根元の方から聞こえることに気がついた。
(何てことだ! さてはどこかの無作法な畜生が、神の木に悪さをしているに違いない!)
王はとさに、腰につけている宝剣に手をかけた。それは護身というよりも、お守りがわりに王がいつも身につけているものだった。彼は芝生に身を伏せると、できるだけ音をたてないように神の木に近づいた。近づくに従って、音ははっきりと聞こえてきた。
不意に、風が木の枝をゆらし、その音の主の姿を月光の下にさらし出した。それを見た時、王は息を飲んだ。
それは、黒く干からびた肌をした、見るに堪えぬ醜い老婆だった。背は五つの子供より高くなく、異様に長い骨と皮だけの腕が、神の木の根元あたりの土を掻きむしっている。王は背筋を冷たいものが走るのを感じた。あんな汚らしいものが、神聖なる神の木を汚すことはど、許せるはずがなかった。
「この化け物め!」
王はそう叫んで立ち上がるや否や、宝剣を抜いて老婆に切りかかった。老婆には声をあげる暇さえなかった。あっという間に、王の剣は老婆の首を切り裂き、月光の下に、干からびたリンゴのような小さな老婆の首が転がった。そして、不思議なことに、王が冷や汗を拭っている間に、老婆の遺骸はゆっくりと月光に溶けるように消えていった。王は、しばらく夢でも見ていたのかと、その場に立ち尽くした。
翌朝は、朝から雨でも降りそうな、灰色の陰気な天気だった。昨夜眠れなかったせいか、つきつきと頭が痛む。王は寝台から起き上がると、いつものように窓辺によって、中庭の聖なる木に目をやった。
とたんに、王は声にならぬ声をあげた。昨日まで、あんなに生き生きと美しかった木が、葉をみんな落とし、骨のように痩せた幹が、からからに乾いて、朽ちていた。
王はあわてて中庭に降りた。そしてそのあまりの無残な姿を間近にして、よろよろとその場にくずおれた。
「あああ、これはどうしたことだ、一体、何で、こんなことが起こったのだ?」
はっと、彼は昨夜の出来事を思い出した。
「そうだ、きっとあの老婆のやらかしたことに違いない。ああ、でもどうすればいいんだ。このままでは、神のご加護が失われてしまう」
王の予感は、その日の昼ごろには、現実になった。東の丘の木々が、一夜のうちにすべて枯れてしまったというのだ。次の日の朝には、北の山から流れる河が干上がってしまったという知らせが入り、その次の日には、湖が次第に小さくなっていているとの知らせが届いた。
不安のあまり、城の門の前に波のように国民が押し寄せた。だが、王にはどうすることもできなかった。まるで、手のひらを返したように、神の恵みが拭い去られ、国はひと月の間に見るも無残な姿になった。飢きんが国じゅうを襲った。たくさんの国民が飢えて死に、あるいは生きることに絶望して自ら命を絶った。
だが、王にできることはと言えば、城の中でただ右往左往することだけだった。見るに見かねた王妃が、ある日、こう言った。
「王様、わたしの故郷に、有名な占い師がいます。とても有能な予言者という噂です。どうでしょう。その占い師に相談してみては」
「占いなどあてになるものだろうか……。だが何もしないよりはいいかもしれない」
王は、藁にもすがる思いで、占い師を城に呼び寄せた。
占い師は、古いつぎはぎだらけの黒い服を着た老婆だった。王はひれ伏さんばかりに深く頭をたれて、老婆に救いを求めた。
「王よ、あなたはたいへんな過ちをおかしましたね」
老婆が、口を開くなり言った。静かな優しい声だった。
「なんと、わたしがですと?」
王は信じられないという顔で、まじまじと占い師の顔を見返した。
「そうです。あなたは、根の老婆を殺したのです」
「根の老婆?」
占い師は、哀れみをこめた長いため息とともに、ゆっくりと首をふって言った。
「王よ、あなたは、なぜ花が美しいのか、なぜ木々の緑がすがすがしいのか、知っておいでか。それは、誰も知らない地中深くに、根の老婆という、醜い女がいるからなのです。彼女らは、っ暗い土の下で、一生誰にも知られないで、木や花のために苦い土を食み続けるのです。彼女がいなければ、木や花は命を奪われたも同じです」
「ああ、それでは、あの夜、わたしが殺したのは……」
王は、絶望のあまり、よろよろとその場に手をついた。
「知らなかったとは言え、あなたは大変なことをしてしまいました。神は怒って、国中の根の老婆を去らせてしまったのです。もう、この国に緑は蘇りますまい」
「もう、だめなのですか? わたし一人の罪で、民がみんな死んでしまうのですか? ああ、もう、神は許して下さらないのですか?」
王は土に顔を伏せて、唇を噛んで泣いた。
「一つだけ、方法があります」
占い師の言葉に、王ははっと顔を上げた。占い師の老婆は、暗い顔で王の顔を見返した。
「でも、これには、たいへんな覚悟がいります。あなたにできますか?」
「教えてください、その方法を! 罪を償えるのなら、何だってする!」
「王よ、その方法とは……、死の河を超えることです。あなたは、死の河を超えて、神に会い、許しをこわねばなりません。そして、もう一度、新しい木をいただいてくるのです」
「しかし、死の河とは、人間には一度しか超えられない河です。川を越えて神に会えたとしても、どうやってこちら側に帰ってきたらいいのです? それではせっかくの木をこっちに持って帰ってくることはできない」
「王よ、あなたは死に、そして生きなければならない。それはあなたが王だからです。考えなさい。そうして答えを出しなさい。わたしにできるのはここまでです」
そう言って、占い師は城を去っていった。
次の日から、王は塔のてっぺんに閉じこもった。自分の浅はかな行いのせいで、この不幸が起こった。自分の正しさを一時も疑ったことのない王にとって、それはたえがたい苦しみだった。しかも、その罪をつぐない、もとの豊かな国に戻すことは、どう考えても不可能だった。人間に、死の河を二度渡ることは、できないのだ。
王妃は、閉じこもったまま出て来ない王の身を心配して、ずっと中庭から塔を見上げていた。王の罪は王がつぐなわなければならない。それはわかっていてっも、何おできない自分が彼女にははがゆくてしようがなかった。
(せめて、あの方の心を慰めることができれば……、そうだわ、あの歌を歌ってみよう。お耳に届けばいいのだけれど)
王妃は、心を込めて、優しいあの旋律を歌った。
死の河を超えて
来れ我が元に
絶望のなせる業ではなく
自らの王として
その歌を聞いたとき、まるで、今までの自分を取り囲んでいた黒幕がいっせいに取り払われたように、王の目の前にある真実がありありと浮かび上がった。
「わたしには、わたしがある。わたしの命が、わたしに託されている。ああ、なぜこのことに気づかなかったのだ。わたしはこの国の殴打。そして、わたし自身の王なのだ!」
塔より降りてきたとき、王妃の前に現れた王の顔には、一つの決意が現れていた。その瞳の中に、微動だにしない意志の輝きを見て、王妃は恐れおののいた。そして、深い悲しみにおおわれた。
「わたしの王妃よ。わたしは、これから南への旅に出る」
「ああ、それでは、死の河に赴かれるのですね」
王妃のほおにはらはらと涙が流れた。王は彼女の肩に手を置くと、やさしくささやいた。
「王妃よ、死とは、滅びることではないのだ。あなたが歌ってくれたあの歌のおかげで、わたしにはそれがわかったのだよ。わたしは、わたし自身のすべてをかけて、神にお会いしてくる。そうしてきっと、帰ってくる」
そういうと王は、腰の宝剣をとり、それを中庭の土に深く突き刺した。
「わたしが度に出ている間、決してこの剣を動かしてはいけない。そうしてもし、この剣が錆びて朽ちるまでわたしが帰らなければ……」
「ああ、そんなことをおっしゃらないでください!」
王は、さめざめと泣いている王妃を胸に抱き寄せた。
そうして一時別れを惜しむと、王はすいと王妃の体から離れて、にっこりと笑い、くるりと振り返ってまた城の中に姿を消した。
次の朝早く、王は発った。誰ひとりとして共をつれず、わずかな食料を入れた粗末な皮袋だけを持って。王妃は塔のてっぺんから、小さなその姿が南の平原に向かって、だんだんと小さくなり、消えていくのを眺めていた。
それから、毎日、王妃は、中庭の芝生に座って、宝剣ばかりを見つめて暮らした。大臣や召し使いたちがどんなに言っても、けっしてそこから動こうとしなかった。
死の河は、南に五百日、東に七百日歩いた所にある。王妃は五百日待ち、そして七百日待った。また七百日待ち、五百日待った。だが、王は帰って来なかった。宝剣はだいぶ錆びつき、つかの飾りが腐って落ちた。
国は、次第に衰え、日と義とはだんだんと少なくなっていった。国民も、城の召し使いも、大臣たちでさえ、もっとほかの豊かな国を探してこの国を去り、やがて王妃のもとに残ったのは、昔から王妃に仕えている侍従一人だけになった。それでも、王妃は帰らぬ王を待っていた。
十年がたった。宝剣は、もうほとんど朽ちて、土の上にそれと探すのも苦労するようになった。だた王妃は待っていた。
「王妃様、もう剣はほとんど朽ちてしまいました。もう待っても無駄かと思います」
侍従は言った。
「まだよ、まだ、刃の先が少しのこっているわ」
王妃はそう言って、宝剣のそばをはなれようとはしなかった。
「王妃様、なぜそのようにしてまで、あのお方をお待ちになるのですか。しょせん、人間には死の河を二度渡ることはできないのです。人々ももう、ほとんどいなくなりました。国は滅びてしまったのですよ」
「あなたにはわからないのだわ。死は滅びることではないのよ。あのかたはそう言ったわ」
「王妃様」
「暗い闇の底で、何もできず、絶望にあえいでいた人の魂の中にも、どこからか語りかけるものがあるわ。今のわたしたちは、死なねばならないの。なぜなら、死の向こうにこそ、もうひとつの生きる道があるからよ」
侍従はもう何も言わなかった。悲しみのあまり、王位は狂ってしまったのだと、そう思った。
それから二、三日たった朝のことだった。侍従がいつものように、粗末な食事を王妃に届けようとしていたとき、庭から狂ったような王妃の笑い声と叫び声を聞いた。
「ああ、ああ、帰っていらっしゃった! 帰っていらっしゃったわ!」
驚いた侍従は、あわてて中庭に降りた。すると、どうだろう。王の遺した宝剣のあったあたりの地面から、若葉色のまばらな樹冠をのせた細い若木が、まるで大地から天が白い綱を引っ張り出しているように、するすると見る間に伸びていくではないか。
王妃は泣きじゃくりながら、伸びていく木の幹にすがりついた。するとそのとき、ゆらゆらと彼女の姿がぼやけ、瞬きをするあいだに、彼女の姿はとめどなくあふれる泉になった。木は枝を伸ばし、こずえをはり、刃を茂らせ、瞬く間に大木になり、泉は次々とわきいでて、水を集め一本の小さな流れになった。まるで、長く会わなかった恋人たちのように、木と水はからみあい、もつれあいながら、成長し、広がっていった。
そして一夜のうちに、国に大きな森と、河が出現した。
わずかに残っていた人々が、それを見て、喜びのあまり、口々に王と王妃の名を呼びながら、城に集まってきた。だが、城はもうどこにもなく、ただ、新しい河のほとりに、老いた侍従が呆然と立ち尽くしているのを見つけただけだった。
それから、王と王妃の姿を見た者はだれもいない。城は森の中に消え、王家の血は絶えた。人々は新しい城を建て、新しい王を立てて、新しい国を作った。だが、その国には、二度と、昔のように豊かな幸せが訪れることはなかった。森と河は確かに美しく豊かであったが、それらはもう決して、彼らを快くうけいれることはなかった。
人々は、昔、自分たちが夢の中に住んでいたことを知った。そして、自分達が愚かで、醜かったことを知った。
長い長い年月がたった。人々は、その悲しい伝説と共に、その森のことを「死の河の森」と呼んで、長い間忘れなかった。だが、それもしょせん一時のことだった。今では誰も、その森がどこにあったのか知らない。
だけど、この世界のどこかに、その森は、ひっそりとたしかに生きている。人々の忘れてしまった思い出をその奥に隠して、そうして、じっと、待っている。一つの決意を持って、いつか誰かが、訪れてくるのを。
(おわり)
(1989年、個人誌「ここり」掲載)
ご存じのとおり、かのじょにはたくさんのペンネームがある。それで、ペンネームごとに分類して作品を競演させてみることにした。青城澄、詩島瑠璃、種野思束、南野珠子、けやき、てんこ、棚木那野の7人である。ご存じとは思うが、これらの名前は全部の名前の半分にもならない。探し出すとまた出てくるのだよ。かのじょは自分に名前をつけるのがよほど好きだったようだ。というより、どういう名前が自分に似合うのか、全然わからなかったのだろう。本名は彼女をそのまま言い表しているような名だが、全く似合わない。
ちなみに棚木那野はかのじょが20代の頃に個人誌で使用していた名前であり、種野思束は30代から40代に同人誌その他で使用していた。青城澄と詩島瑠璃は40代から50代だ。「てんこ」「けやき」はHNである。まあそんなことを考えながら、楽しんでくれたまえ。一応、年齢順に発表してゆく。
明日は棚木那野である。もっとも古い筆名だ。棚木にはある意味があるのだが、残念ながら失念してしまった。那野はかのじょも言っていた通り、1ナノメートルのナノである。
まだ表現力も未熟で人生や社会の構造も見えていなかった頃の作品だ。なお、てんこの作品は、おもにブログ上での表現で使われたので、旧ブログから引っ張ってくる。
お遊びみたいなものだが、楽しんでくれたまえ。