(16.7.8.たんぽぽ・うたごえ喫茶スクラム)。
ずいぶん昔(20歳ころ)、当時流行っていた「歌ごえ喫茶」というものに一人で行ってみた。
きわめて健康的なのだ。ビールくらいは出されたかもしれないが、みな歌うことに夢中で、連帯感があって、私のような者が一人で行く場所ではなかった。
歌はうまくないが、中にヨーデルなんかが上手な人がいて、拍手喝さいを浴びていた。伴奏はアコーデオンが主。伴奏も上手いとは言えない。
ほうほうの体で私は店を出た。私とは人種が違うと思った。私にはもっと薄暗くて隠微な雰囲気さえある、ジャズのライブハウスが合っていると痛感した。
※私の俳句(夏)
両翼を浜にひろげし夏ホテル



















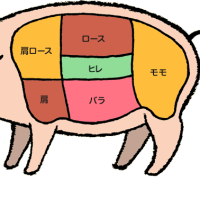
(1)
「うたごえ喫茶」は懐かしい。戦後のいわゆる「うたごえ運動」の流れの中で、全国規模で広がった「うたごえ喫茶」。現代で言えばさしずめ「カラオケ」であろうか。歌いたいという本能的欲求を日常的に満たす場でもあった。
最盛期には、うたごえ喫茶のもようが、ラジオで実況中継されることもあった。記憶しておられる方々もおられると思うが、新宿のラ・セーヌからの中継は「ラ・セーヌ・ヒットソングアワー」として定時のラジオ放送として評判になった。司会は山本歌子。
運動も喫茶も、まるでインフルエンザのごとく全国に広がり、「蔓延」という言い方が相応しいほどだったが、自然発生的というには不自然なところもあった。
(2)
実は、うたごえ運動は、昭和23年(1948)声楽家関鑑子を中心に設立された中央合唱団が旗振り役になって全国展開した、計画的な合唱運動で、労働組合、企業、大学、一般社会人などを核とした合唱団の結成を目指した。
中央合唱団は共産党の下部組織で、戦後の平和運動や、左翼運動、共産主義運動を、大衆化し、市井の人々の共感を得るべく、「みんなで一緒に声を合わせて」団結を図るというものだった。政治的に一定の方向に誘導するという意味では、不純な(笑)要素を含むものでもあった。
(3)
「不純」と言ったが、高度に政治的意図があったということよりも、大衆運動故の非芸術性が堪え難いほどのものだったからである。コンサートホールで聴衆、観客を魅了する音楽性を備えた合唱団が結成されることはなかった。その特徴は、四声体の美しいハーモニーをめざさず、その場に居合わせた人々がひとつになって同じメロディを歌う。まるでAKBのアダルト版であり、ジジババ版なのだ。そこに「団結」の観念を混ぜていた。歌はロシア民謡、日本の童謡、小学唱歌、「原爆許すまじ」といった反戦志向、平和志向でかつ反保守的な歌。芸術的な詩情性は皆無。中里さんの心が満たされるようなものでは断じてない。(笑)
しろうとが集まるので、アコーデオンの伴奏がつき、奏者は人々の歌うメロディも引いて、音楽の苦手な人たちをサポートした。なぜピアノでなくアコーデオンだったかというと、簡単に持ち運べて、海でも山でも国会前でも、メーデー行進の最中でも、ユノゾンの歌をサポートできたからである。
(4)
社会学的には、カラオケの機能も持ち合わせていたから、中里さんがいみじくもお書きになっているように、「みな歌うことに夢中」で、ユニゾンなので「連帯感」もバッチリ。「みんなで一緒に」が合い言葉のようになっていた。共産党の標榜する「大衆的連帯」がバーチュアルに形成されていった。
合唱団に参加する人、うたごえ喫茶に通う人たちは、必ずしも政治的ではなかったし、共産党や社会党シンパというわけでもなかったのはある意味幸いしたと言える。私も大学時代に、それと知らず、学友たちと通って、焼き鳥、チューハイと共に、見ず知らずの人たちとにわか団結をして楽しんだ。(笑)
「さあ皆さん声を合わせて5番の歌を歌いましょう」という形で、心理的に「強いられる」雰囲気もあったので、ジャズ愛好家の中里さんが「ほうほうの体で店を出た」という気持ちは痛いほどよくわかる。お呼びでない、というか「場違い」なのである。新興宗教に勧誘されて、社会見物のつもりで、とりあえず様子を見にいったら、あまりにも「お呼びでない」ので、ほうほうの体で逃げ出すのと酷似している。(笑)
「歌ごえ喫茶」のなにがイヤかと言って。「明るさ」と「連帯感」なんですよね。
なんとまぁ、お軽い「連帯感」。シンからの「連帯」は本当は超難しいのだと、私は思っています。
(1)
東京の高校時代の後半ぐらいから、下校時によく友達と連れ立って渋谷のジャズ喫茶に通った。屋上に五島プラネタリウムのドームが目立った「東急文化会館」や、お洒落なケーキ店フランセや紀伊国屋書店がテナントとなっていた「東急プラザ」がランドマークだった時代。この二つの施設は今はない。
パルコも109もまだなく、Bunkamura オーチャードホールもなかった。時は1960年代後半。今から五十年も前のことである。我々が制服のまま通ったのは道玄坂を中ほどまで上って右に折れた百軒店(ひゃっけんだな)。今でもあるが、当時とは様相を異にして健全な雰囲気を漂わせている。
元々は江戸時代につながると言われる色街で、戦災で焼け跡闇市化したことをきっかけに、Business Girlと揶揄された街娼がたむろし、ちょいの間、飲み屋、隠微なトリスバーなど大人の裏世界のお膳立てが見事に出そろっていた。当時はストリップ小屋まであった。
(2)
犯罪の香りもただようそんなヤバイ路地に、詰め襟の制服を着た高校生が、夕方から九時ごろまで…。世間知らずだったのである。もっとも、市ヶ谷の女子学院の放課後に、制服を着たまま、同じくジャズ喫茶通いをしていたという同じ年の強者(つわもの)女史がいる。大学同期の友人だが、先年、そのことが話題になってさすがに驚いた。
クラシック純喫茶として知られた「ライオン」と並んで、「オスカー」「ブラックホーク」「デュエット」「サブ」など。音がだだ漏れのバラックの見すぼらしい店がめじろおし。中は薄暗く隠微の権化なのだが、言葉を変えれば、ディケンズの時代のロンドンの芝居小屋の貧しさとも言えた。
(3)
そこでコーラかコーヒーを一杯頼んで、高級オーディオから流れてくる大音声(おんじょう)のジャズを聴きつつ二時間、三時間と粘るのである。
自然発生的に生じた店内雑談禁止のルールは徹底していた。普通では入手できないような、リリースされたばかりの話題の輸入盤を聞くことが出来た。1ドル360円の時代だったから音の良い輸入盤は高嶺の花で、高校生のお小遣いでは収集は無理だった。
その変わり、ジャズ喫茶ではリクエストが出来た。話が出来ないから、目をつぶって音楽に集中する。さまざまな思いが去来する濃厚な精神空間だったのである。客の全員が押し黙って、本も読めない薄暗いバラック小屋で、再生音楽に聞き入っている。門外漢からすれば、さしづめ「なんとか真理教」の如き異様な空間だったに違いない。可能ならば中里先生をタイムマシンでお連れしたいくらいの濃密な精神空間である。(笑)
ただ、ストリップ小屋が渋谷にあって街娼がいたとは覚えがないなあ。
とにかく今の渋谷と違って、渋谷はもっと淫靡だったし、小汚い中華屋なんかもありましたよね。
私の父親は、玉川電車のガード下にある「珉珉」という中華屋が好きでした。その店先には確かトンコツがぶらさがっていたなぁ。