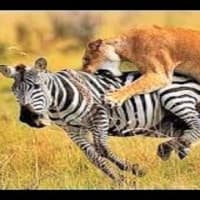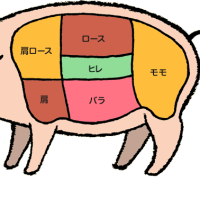船医を経験したことのある大先輩の話だから、昭和30年代のことである。
その先輩は1000人規模の大漁船団の船医として、遠洋漁業に出かけた。当時、船医の実入りはよかった。なぜかというと、船医は半年、1年と船に乗りっぱなしで、後任が来ない限り船から降りてはいけないと法律で決まっていたからである。
いくら実入りが良くても、自由がないので陸の医者からの応募が少なく、遠洋漁業が活発だった時代ということもあって、船医は不足していた。
船の世界というのは、軍隊式の階級社会であるらしく、一番上が船長と船医だった。船長と船医は母船に特別室を与えられた。
その下に、漁撈長とか機関長とかの階級があって、一番底辺の船員はなんと「雑夫」と呼ばれていた。「雑夫」は港でその都度募集され、経歴を問われることはなかった。だから、船に乗ってしまえば、前科者であろうと、なんであろうと、おかまいなしだった。犯罪を犯してから船に乗って「雑夫」として逃亡した者もあったという。
大先輩が船医だった時代、医者として腕を振るう機会はめったになく、閑職だったらしい。マトモな病気や怪我よりも、喧嘩での怪我が多かったそうだ。「雑夫」どうしの喧嘩である。
船の上で喧嘩をして相手を刺しても、警察が飛んで来るわけではない。だから、喧嘩による傷害はよくあった。でも、漁船を陸へ引き返してまで、怪我の手当てをするほど船団は悠長なものではない。船団は魚を獲ってなんぼである。刺されて死んでしまえばそれまで。そこで船医の出番である。
船団はある意味で治外法権である。だから、直接いのちを扱う船医は、最上階級に置かれていたのである。
私がまだ若いころ、医者の雑誌によく「船医募集」という記事があった。待遇は破格だった。ところが最近は「船医募集」という記事を見ない。
医者が足りるようになったのだろうか?いや、そうではなかろう。人権意識の高まりで、船団に病人や怪我人が出れば、船が最寄りの港へ行くようになったのではないかと、私は考えている。それとも、船医を必須とする法律が変わったのだろうか?
その先輩は1000人規模の大漁船団の船医として、遠洋漁業に出かけた。当時、船医の実入りはよかった。なぜかというと、船医は半年、1年と船に乗りっぱなしで、後任が来ない限り船から降りてはいけないと法律で決まっていたからである。
いくら実入りが良くても、自由がないので陸の医者からの応募が少なく、遠洋漁業が活発だった時代ということもあって、船医は不足していた。
船の世界というのは、軍隊式の階級社会であるらしく、一番上が船長と船医だった。船長と船医は母船に特別室を与えられた。
その下に、漁撈長とか機関長とかの階級があって、一番底辺の船員はなんと「雑夫」と呼ばれていた。「雑夫」は港でその都度募集され、経歴を問われることはなかった。だから、船に乗ってしまえば、前科者であろうと、なんであろうと、おかまいなしだった。犯罪を犯してから船に乗って「雑夫」として逃亡した者もあったという。
大先輩が船医だった時代、医者として腕を振るう機会はめったになく、閑職だったらしい。マトモな病気や怪我よりも、喧嘩での怪我が多かったそうだ。「雑夫」どうしの喧嘩である。
船の上で喧嘩をして相手を刺しても、警察が飛んで来るわけではない。だから、喧嘩による傷害はよくあった。でも、漁船を陸へ引き返してまで、怪我の手当てをするほど船団は悠長なものではない。船団は魚を獲ってなんぼである。刺されて死んでしまえばそれまで。そこで船医の出番である。
船団はある意味で治外法権である。だから、直接いのちを扱う船医は、最上階級に置かれていたのである。
私がまだ若いころ、医者の雑誌によく「船医募集」という記事があった。待遇は破格だった。ところが最近は「船医募集」という記事を見ない。
医者が足りるようになったのだろうか?いや、そうではなかろう。人権意識の高まりで、船団に病人や怪我人が出れば、船が最寄りの港へ行くようになったのではないかと、私は考えている。それとも、船医を必須とする法律が変わったのだろうか?