平成27年9月9日
津山市議会一般質問2日目に奨学金の件で質問が出され、奨学金返納免状の導入が進められるようです!
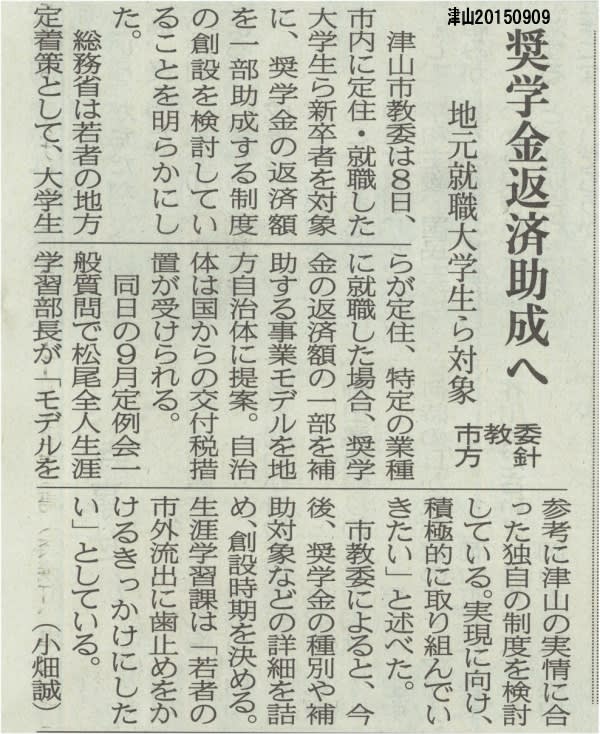
少し長くなりますが、昨年(26年)の6月議会での私の質疑の議事録を貼り付けます。
定住化推進と晩婚化について質問しています。
改めて議事録を見ると、若者からの意見徴収をしたうえでの今回の答弁なのかな?
平成26年9月議会(奨学金制度について)
安東
平成24年4月1日に津山市奨学金制度条例の改定を行いました。改正の内容の一つが免除規定です。津山市奨学金条例第8条免除規定1項で、本市に居住し、かつ規則で定める区域内に存する事業所に就職したときは、奨学金の免除申請ができると定めたものです。奨学金と定住化を結びつける施策であります。
津山市奨学金の免除規定を定めるという改定に当たり、当時執行部としてどのような議論がなされたか、議論の経過についてお尋ねいたします。
また、条例改定により応募者数に変化があらわれたかどうか、また23年から26年の4年間でそれぞれの年度の奨学金の貸付実績をお尋ねいたします。
生涯学習部長(松尾全人)
私からは、津山市奨学金制度についてのお尋ねにお答えいたします。
津山市奨学金制度は、従来の全本明正奨学基金に、故富田泰司様の寄附金を増資し、新たに平成24年4月1日に施行いたしました。新津山市奨学金制度では、多くの生徒、学生に利用しやすく、毎年安定した募集、貸与が行われるようにとの思いで、当初は募集人員の増員、大学院生や専門学校生への対象拡大など、応募要件の緩和のみを考えておりました。
その後、政策決定議論の中で、津山市の喫緊の課題である定住促進に資する制度となるよう、Uターン就職の動機づけに一定の効果が見込まれるものとして、奨学金の返還期間内に津山に居住し、かつ津山圏域の事業所等に就職している場合、年間返還予定額の3分の1を免除できることといたしました。
次に、条例改正による応募者数の変化についてでございますが、改正前の全本明正奨学金であった平成23年度は、募集人員枠いっぱいの3人、改正後の平成24年度は10人、その後平成25年度10人、平成26年度6人と推移しております。
それから、平成23年度からの奨学金貸与実績値でございますが、決算額で申し上げますと、平成23年度、高校生1名、16万8,000円、大学生3名、108万円、平成24年度、高校生1名、16万8,000円、大学生11名、396万円、平成25年度、高校生はありませんで、大学生17名、594万円、平成26年度はこれは見込みでございますが、高校生1名、16万8,000円、大学生19名、684万円でございます。
安東
津山市奨学金制度条例改定に関しての質問ですが、この当時の議論の中身を知りたかったということで質問しました。奨学金の免除が定住化につながるかなど、激論が交わされたのではと予想しています。そこで、議論の中身はどんな内容だったのか、再質問をします。
生涯学習部長(松尾全人君)
奨学金の返済免除制度の導入については、限られた対象者への優遇措置であることから、定住促進策としての費用対効果の面や、基金が減少することに対する対応策等が議論となりました。その結果、やはり定住促進が喫緊の課題となっている中で、今後も市全体として取り組むべき定住促進策の一つとして、Uターン就職等の動機づけとして返還免除制度を導入すべきとの結論となったものでございます。
なお、基金の減少に関して、返還免除相当額について、一般会計からの繰り入れも含めて対応する予定となっております。
安東
私は、この奨学金制度改革、これは都市への集中や晩婚化に対する施策の一つになると考えております。
津山市の平成25年3月の卒業で、中学校から高校への進学はほぼ100%に近く、高校から大学等への進学率は46%となっています。
その進学資金として、多くの学生さんがさまざまな奨学金制度を活用されていると予測します。
つまり、大学等卒業時にこれから就職しようとするとき、自分自身には大きな借金を抱えることになります。親がかりの返済もあるかもしれませんが、大半は自分で返済することになります。このことが給与水準の高い大都市への就職や、借金があるという意識により晩婚化につながる要因の一つであると考えます。定住化への効果が出るのはこれから2年後以降になりますが、注視をしてください。
そこで、提案なんですが、この総合計画策定に当たり、津山市在住者を対象に現状の奨学金借入状況の調査を調査項目の一つとして考えていただきたいんですが、いかがでしょうか。
特別理事(常藤勘治)
総合計画策定に当たって実施しますアンケートは、市の向かうべき方向性、柱とすべき考え方などを調査するものでありまして、今年度実施予定の地区別懇談会等で市民の皆様からいただく意見などをもとに、目的やコンセプトを明確にし、実施いたします。
奨学金の借り入れに関する調査については、現在の若者の抱える課題、問題の発掘、将来志向、経済状況の把握を行う趣旨であるというふうに考えますので、アンケート内容を決定する際に、どのような聞き方ができるのか検討させていただきます。
津山市議会一般質問2日目に奨学金の件で質問が出され、奨学金返納免状の導入が進められるようです!
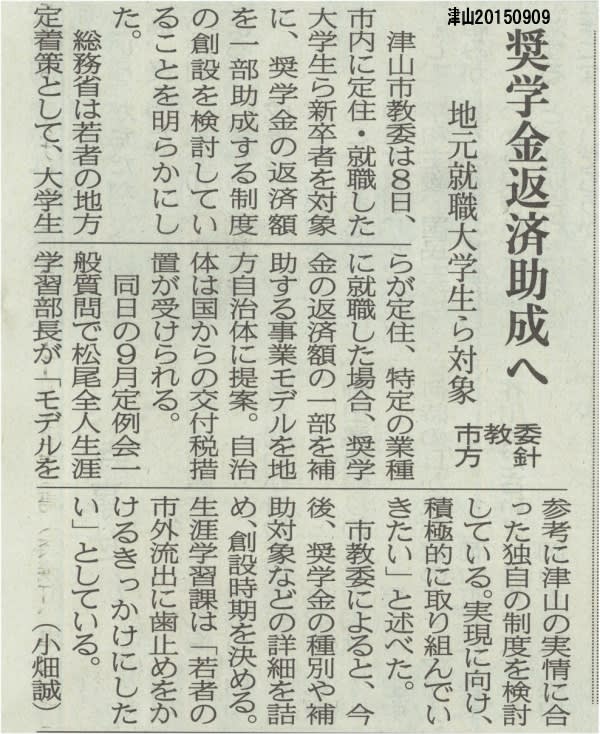
少し長くなりますが、昨年(26年)の6月議会での私の質疑の議事録を貼り付けます。
定住化推進と晩婚化について質問しています。
改めて議事録を見ると、若者からの意見徴収をしたうえでの今回の答弁なのかな?
平成26年9月議会(奨学金制度について)
安東
平成24年4月1日に津山市奨学金制度条例の改定を行いました。改正の内容の一つが免除規定です。津山市奨学金条例第8条免除規定1項で、本市に居住し、かつ規則で定める区域内に存する事業所に就職したときは、奨学金の免除申請ができると定めたものです。奨学金と定住化を結びつける施策であります。
津山市奨学金の免除規定を定めるという改定に当たり、当時執行部としてどのような議論がなされたか、議論の経過についてお尋ねいたします。
また、条例改定により応募者数に変化があらわれたかどうか、また23年から26年の4年間でそれぞれの年度の奨学金の貸付実績をお尋ねいたします。
生涯学習部長(松尾全人)
私からは、津山市奨学金制度についてのお尋ねにお答えいたします。
津山市奨学金制度は、従来の全本明正奨学基金に、故富田泰司様の寄附金を増資し、新たに平成24年4月1日に施行いたしました。新津山市奨学金制度では、多くの生徒、学生に利用しやすく、毎年安定した募集、貸与が行われるようにとの思いで、当初は募集人員の増員、大学院生や専門学校生への対象拡大など、応募要件の緩和のみを考えておりました。
その後、政策決定議論の中で、津山市の喫緊の課題である定住促進に資する制度となるよう、Uターン就職の動機づけに一定の効果が見込まれるものとして、奨学金の返還期間内に津山に居住し、かつ津山圏域の事業所等に就職している場合、年間返還予定額の3分の1を免除できることといたしました。
次に、条例改正による応募者数の変化についてでございますが、改正前の全本明正奨学金であった平成23年度は、募集人員枠いっぱいの3人、改正後の平成24年度は10人、その後平成25年度10人、平成26年度6人と推移しております。
それから、平成23年度からの奨学金貸与実績値でございますが、決算額で申し上げますと、平成23年度、高校生1名、16万8,000円、大学生3名、108万円、平成24年度、高校生1名、16万8,000円、大学生11名、396万円、平成25年度、高校生はありませんで、大学生17名、594万円、平成26年度はこれは見込みでございますが、高校生1名、16万8,000円、大学生19名、684万円でございます。
安東
津山市奨学金制度条例改定に関しての質問ですが、この当時の議論の中身を知りたかったということで質問しました。奨学金の免除が定住化につながるかなど、激論が交わされたのではと予想しています。そこで、議論の中身はどんな内容だったのか、再質問をします。
生涯学習部長(松尾全人君)
奨学金の返済免除制度の導入については、限られた対象者への優遇措置であることから、定住促進策としての費用対効果の面や、基金が減少することに対する対応策等が議論となりました。その結果、やはり定住促進が喫緊の課題となっている中で、今後も市全体として取り組むべき定住促進策の一つとして、Uターン就職等の動機づけとして返還免除制度を導入すべきとの結論となったものでございます。
なお、基金の減少に関して、返還免除相当額について、一般会計からの繰り入れも含めて対応する予定となっております。
安東
私は、この奨学金制度改革、これは都市への集中や晩婚化に対する施策の一つになると考えております。
津山市の平成25年3月の卒業で、中学校から高校への進学はほぼ100%に近く、高校から大学等への進学率は46%となっています。
その進学資金として、多くの学生さんがさまざまな奨学金制度を活用されていると予測します。
つまり、大学等卒業時にこれから就職しようとするとき、自分自身には大きな借金を抱えることになります。親がかりの返済もあるかもしれませんが、大半は自分で返済することになります。このことが給与水準の高い大都市への就職や、借金があるという意識により晩婚化につながる要因の一つであると考えます。定住化への効果が出るのはこれから2年後以降になりますが、注視をしてください。
そこで、提案なんですが、この総合計画策定に当たり、津山市在住者を対象に現状の奨学金借入状況の調査を調査項目の一つとして考えていただきたいんですが、いかがでしょうか。
特別理事(常藤勘治)
総合計画策定に当たって実施しますアンケートは、市の向かうべき方向性、柱とすべき考え方などを調査するものでありまして、今年度実施予定の地区別懇談会等で市民の皆様からいただく意見などをもとに、目的やコンセプトを明確にし、実施いたします。
奨学金の借り入れに関する調査については、現在の若者の抱える課題、問題の発掘、将来志向、経済状況の把握を行う趣旨であるというふうに考えますので、アンケート内容を決定する際に、どのような聞き方ができるのか検討させていただきます。















