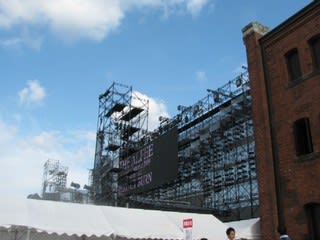ここ3日ばかり朧月がきれいだった。

十三夜。旧暦6月14日

十五夜。旧暦6月16日
今夜は十六夜だ。
先日、えんの会で話題になった阿仏尼『十六夜日記』。
古典文学は高校で習ったきりなので、はなはだ心もとないのだが、
十六夜にちなんで、さわりを読んでみようと思った。
相続問題の解決のため、神無月16日に阿仏尼は京を発ち
鎌倉に向かった。
まずは旅立ちの由来が述べられ、東下りの旅日記、
鎌倉滞在記、戦勝祈願の長歌と続く。
東下り、道中の最初の部分。
<東下り>
「さのみ心よはくてもいかゞ。」とて、つれなくふりすてつ。
あはだぐち(*ママ)といふ所より車はかへしつ。
ほどなくあふさかのせきこゆるほどに、
さだめなき命はしらぬ旅なれど又あふ坂とたのめてぞ行
のぢといふ所は、こしかた行さき人もみえず。
日は暮かゝりていと物がなしとおもふに、時雨さへうちそゝぐ。
うちしぐれ古郷思ふ袖ぬれて行先遠き野路の篠原
「こよひはかゞみといふ所につくべし。」とさだめつれど、
くれはてゝゆきつかず。もり山といふ所にとゞまりぬ。
こゝにも時雨なほしたひきにけり。
いとゞ猶袖ぬらせとや宿りけんまなく時雨のもる山にしも
けふは十六日の夜なりけり。いとくるしくてふしぬ。
いまだ月のひかりかすかにのこりたるあけぼのに、
もり山をいでてゆく。
やす川わたるほど、さきだちて行たび人のこまの
あしおとばかりさやかにて、きりいとふかし。
旅人はみなもろともにあさたちて駒打わたすやすの川霧
――まず「あふ坂」の関で1首、夕暮れの時雨降る野路で1首、
「かがみ」まで行こうとしたがたどりつかず、
「もり山」で一泊することになり1首、
まだ月の残る明け方に「もり山」を発ち、「やす川」を渡り1首、
でよいのかしら?
20日、尾張の国、鳴海の潟で都鳥や八橋を詠んだ歌は有名らしい。――
「すみだ川のわたりにこそあり。」と聞しかど、
みやこどりといふ鳥のはしとあしとあかきは、此うらにもありけり。
こととはむ觜と足とはあかざりし我住かたの都鳥かも
二むら山をこえて行に、山も野もいととほくて、日もくれはてぬ。
はる\〃/と二村山を行過て猶すゑたどる野べの夕やみ
「八橋にとゞまらん。」といふ。くらさにはしもみえずなりぬ。
さゝかにのくもであやうき八橋を夕ぐれかけて渡りぬる哉
――29日に鎌倉に着き、この東下りの旅は終わる。
60歳で13日かけて京から鎌倉まで・・すごいです。(・ω・;A
このあと鎌倉滞在。――
<鎌倉滞在記>
あづまにてすむ所は、月かげのやつ(*月影の谷)とぞいふなる。
浦近き山もとにて、風いとあらし。山寺〔極樂寺〕のかたはらなれば、
のどかにすごくて、浪の音松のかぜたえず。
都のおとづれは、いつしかおぼつかなきほどにしも、
うつの山にてゆきあひたりし山ぶしのたよりに
ことづけ申たりし人の御許より、たしかなるたよりにつけて、
ありし御返しと覺しくて、
旅衣涙をそへてうつの山しぐれぬひまもさぞしぐるらん
ゆくりなくあくがれ出し十六夜の月やおくれぬ形見成べき
「都をいでしことは、神無月十六日なりしかば、
いざよふ月をおぼしめしわすれざりけるにや。」と、
いとやさしくあはれにて、たゞ此返事ばかりをぞ又きこゆ。
めぐりあふ末をぞ頼むゆくりなく空にうかれし十六夜の月
――ふむふむ、鎌倉は極楽寺近くの月影の谷にお住まいだったと。
え~と古典は苦手だったからなあ。(・ω・;A
先の東下りの旅の途中25日、宇津の山で山伏に
ことづけた手紙のお返事と歌2首がきたので、
そのお返しの歌1首を作られたということでいいのかな。
16日の出立だったので、「あくがれ出でし」十六夜の月を詠っているのか!
十六夜の月は阿仏尼のことかな。
25日の宇津の山のくだりを確かめてみると、
上記の返歌もさすが・・と思えるのだ。
25日の宇津の山のところ。――
うつの山こゆるほどにしも、あざりのみしりたる山ぶしゆきあひたり。
「夢にも人を」(*「夢にも人にあはぬなりけり」)など、
むかしをわざとまねびたらん心地して、いとめづらかに、
をかしくもあはれにもやさしくもおぼゆ。
「いそぐ道なり。」といへば、文もあまたはえかゝず。
たゞやむごとなきところひとつにぞ、おとづれきこゆ。
我心うつゝともなしうつの山夢にも遠き昔こふとて
つたかえでしぐれぬひまもうつの山涙に袖の色ぞこがるゝ
――「しぐれ、うつの山、涙、袖」にこたえて
「旅衣、涙、うつの山、しぐれ」。
心情的にも「大変だね・・」と答えているし。
さらにあくがれ出た十六夜の月の1首を足して発展させ、
それにまた阿仏尼がめぐりあいたいですと十六夜の月の歌で返す。
「末」とは山の頂のことで阿仏尼の歌の相手なのだろうか。
またあなたに会う日を頼みとしています・・でいいのかしら。
滞在中、ひんぱんに都人とも文の交換をしていたらしい。――
卯月のはじめつかた、たよりあれば、又おなじ人の御もとへ、
こぞのはるなつのこひしさなどかきて、
見し世こそかはらざるらめ暮はてし春より夏にうつる梢も
夏衣はやたちかへて都人今やまつらん山ほとゝぎす
そのかへし、又あり。
草も木もこぞみしまゝにかはらねど有しにもにぬ心ちのみして
さてほとゝぎすの御たづねこそ。
人よりも心つくして郭公たゞ一聲をけふぞ聞つる
さねかたの中將の五月まで時鳥きかで、みちのくにより、
〔續後撰〕「都にはきゝふるすらん郭公せきのこなたの身こそつらけれ」
とかや申されたる事の候なる。そのためしとおもひいでられて。
此文こそことにやさしく。
など、かきておこせ給へり。さるほどに、う月のすゑになりければ、
ほとゝぎすのはつねほのかにもおもひたえたり。
人づてに聞ば、「ひきのやつ(*比企谷)といふ所にあまた聲なきけるを、
人きゝたり。」などいふをきゝて、
忍びねはひきのやつなる郭公雲ゐにたかくいつかなのらん
――ホトトギスの声についての歌の応酬は、万葉集巻18、
家持らの宴席での歌を思い起こさせる。
卯月の初め、都と東の地でのホトトギスの初音の時間差。
「もう山ホトトギスは鳴きましたか?」
「耳を澄ませたら今日一声が聞こえましたよ。」
卯月の終りには鎌倉比企の谷で
たくさん鳴いているのだと聞いてまた歌1首。――
ああ、むずかしかった(・ω・;A
慣れないことで、もうへとへとです。
全部読解できてないけど、暗号解読のような
楽しいひとときでした♪
さて、お買い物に行ってこようかな♪
memo
『十六夜日記』は鎌倉中期、弘安三年(1280)ごろ成立。
阿仏尼は夫藤原為家の死後、弘安二年(1279)、
遺産相続の争点となった実子為相の所領確保を鎌倉幕府へ
訴えに下向したが、訴訟の相手の嫡男為氏ともども鎌倉で死去。