09年の日本人の平均寿命は女性86・44歳、男性79・59歳で、08年より女性は0・39歳、男性は0・30歳延びたそうで、延びの頭打ち傾向は依然現れず、まだしばらくは延び続けそうな気配です。長寿は良いことなのでしょうが、手放しで喜べることばかりではありません。
次に紹介するのは文芸春秋8月号の巻頭随筆、90歳を目前にした阿川弘之氏の「老残の身」と題する小文の一部です。
「凡ゆる事が面倒くさい。会合に出たくない。人と言葉を交わしたくない」
「脚腰の筋肉が衰へて、とぼとぼと一歩々々摺り足で歩かなくては何処へも行けない。ステッキを頼りに用心しながら歩いてゐて、路上で一度、家の中で三度倒れ、骨折こそせずに済んだものの、突き指だの擦過傷だの、あちこち怪我をした。外出が億劫になる所以で、運動不足の結果、便秘がひどい。皺だらけの腹の皮が太鼓を張ったやうに張ってゐるのに、ガスも便も出ない。担当医処方の薬を規定通り服用してみても、全く効果があらはれない。癇癪を起こし、漢方の便秘薬を定量の倍以上飲んで寝てゐたら、数時間後突然便意を催した。慌てて起き上がり、入るべき場所へたどり着こうと、心は焦ってもよぼよぼの足が思うように前へ出ず、廊下の途中、下着の中へどッと排泄してしまった。82歳の女房に手伝わせて後始末しながら、『こんな無残なこと二度とやるまいぞ』と自分に言ひ聞かせたのに、実はその後再三再四失禁を経験してゐる。
(中略) よだれが垂れる。手先が震える。眼はかすんで、目尻にいつも涙と目脂がたまってゐる」
また、志賀直哉が亡くなる3年くらい前、阿川氏にした話を紹介しています。
「もう生きてるのがいやだ」と、居間のカーテンの紐を首に巻きつける格好をして「これでこうやってしまえば簡単なんだかね」「とにかく、老年といふのは実にみじめないやなもんだ」
長々と引用しましたが、この種の話は命の尊さ、あるいは窮状を訴えるという意図をもって発表されることはあっても、下着の中へどッと排泄などという無残なことが「自然な話」として公開されることはあまりありません。誰でも最後には経験するかもしれないことが妙な意味づけなどされず、ごく自然に、若干のユーモアを交えて書かれています。
まさに陰陰滅滅でありますが、寿命のすべてを健康に過ごせるわけではありません。介護などが必要な不健康期間は男6.5年、女8.6年(WHO調査2003年)となっています。これは人生の最後に待ち受ける、本人にとってもまた周囲にとっても厄介な「通過儀礼」です。
ピンピンコロリ(元気な時に急死すること。但し周囲はいささか迷惑。PPKとも)願望は根強いものがありますが、有効な手立てはなく、運まかせです。英国の指揮者、Edward Downes卿夫妻は昨年、自殺ツアーでスイスへ行き、Dignitas(自殺幇助組織)によって目的を遂げましたが、これは一般的ではありません(09年までにDignitasで自殺した英国人は114人になるそうで、終末期の人ばかりではないようです)。
作家の吉村昭氏「もう死ぬ」と言って、点滴の管とカテーテルを自ら引抜き、元に戻そうとする看護師に強く抵抗し、亡くなったそうですが、誰もが彼のように格好よく死ねるものではありません。吉村氏は自宅であったからできたという事情もあったわけで、病院では恐らく不可能だろうと思われます。また強い意思と引き抜くだけの体力があればこそで、これらの条件がそろうのは珍しいことでしょう。一歩間違えれば自殺幇助罪に問われます。
何が言いたいかといいいますと、とりわけ不健康期間に於いては、人の在り様は実に様々であり、自らの意思で死期を決めたい人もいれば、すべて他力本願の人もいるわけです。そこでは「命の尊さは何ものにも代え難い」式の単純なきれい事では解決できないということです。
本人の意思の遂行を阻むのは自殺幇助罪や嘱託殺人罪などですが、自殺の違法性を問わずそれに協力した者だけが処罰されるという理屈は誰もが納得できるものではありません。自殺幇助を認めるいくつか国が存在するのはその反映でしょう。
これは森鴎外の「高瀬舟」の主題ともなった古典的な問題ですが、現実にはこの領域において、法は自殺幇助を装った殺人などのごく少数の悪意ある犯罪を防ぐために、非常に多数の自由を犠牲にしているように思われます。
次に紹介するのは文芸春秋8月号の巻頭随筆、90歳を目前にした阿川弘之氏の「老残の身」と題する小文の一部です。
「凡ゆる事が面倒くさい。会合に出たくない。人と言葉を交わしたくない」
「脚腰の筋肉が衰へて、とぼとぼと一歩々々摺り足で歩かなくては何処へも行けない。ステッキを頼りに用心しながら歩いてゐて、路上で一度、家の中で三度倒れ、骨折こそせずに済んだものの、突き指だの擦過傷だの、あちこち怪我をした。外出が億劫になる所以で、運動不足の結果、便秘がひどい。皺だらけの腹の皮が太鼓を張ったやうに張ってゐるのに、ガスも便も出ない。担当医処方の薬を規定通り服用してみても、全く効果があらはれない。癇癪を起こし、漢方の便秘薬を定量の倍以上飲んで寝てゐたら、数時間後突然便意を催した。慌てて起き上がり、入るべき場所へたどり着こうと、心は焦ってもよぼよぼの足が思うように前へ出ず、廊下の途中、下着の中へどッと排泄してしまった。82歳の女房に手伝わせて後始末しながら、『こんな無残なこと二度とやるまいぞ』と自分に言ひ聞かせたのに、実はその後再三再四失禁を経験してゐる。
(中略) よだれが垂れる。手先が震える。眼はかすんで、目尻にいつも涙と目脂がたまってゐる」
また、志賀直哉が亡くなる3年くらい前、阿川氏にした話を紹介しています。
「もう生きてるのがいやだ」と、居間のカーテンの紐を首に巻きつける格好をして「これでこうやってしまえば簡単なんだかね」「とにかく、老年といふのは実にみじめないやなもんだ」
長々と引用しましたが、この種の話は命の尊さ、あるいは窮状を訴えるという意図をもって発表されることはあっても、下着の中へどッと排泄などという無残なことが「自然な話」として公開されることはあまりありません。誰でも最後には経験するかもしれないことが妙な意味づけなどされず、ごく自然に、若干のユーモアを交えて書かれています。
まさに陰陰滅滅でありますが、寿命のすべてを健康に過ごせるわけではありません。介護などが必要な不健康期間は男6.5年、女8.6年(WHO調査2003年)となっています。これは人生の最後に待ち受ける、本人にとってもまた周囲にとっても厄介な「通過儀礼」です。
ピンピンコロリ(元気な時に急死すること。但し周囲はいささか迷惑。PPKとも)願望は根強いものがありますが、有効な手立てはなく、運まかせです。英国の指揮者、Edward Downes卿夫妻は昨年、自殺ツアーでスイスへ行き、Dignitas(自殺幇助組織)によって目的を遂げましたが、これは一般的ではありません(09年までにDignitasで自殺した英国人は114人になるそうで、終末期の人ばかりではないようです)。
作家の吉村昭氏「もう死ぬ」と言って、点滴の管とカテーテルを自ら引抜き、元に戻そうとする看護師に強く抵抗し、亡くなったそうですが、誰もが彼のように格好よく死ねるものではありません。吉村氏は自宅であったからできたという事情もあったわけで、病院では恐らく不可能だろうと思われます。また強い意思と引き抜くだけの体力があればこそで、これらの条件がそろうのは珍しいことでしょう。一歩間違えれば自殺幇助罪に問われます。
何が言いたいかといいいますと、とりわけ不健康期間に於いては、人の在り様は実に様々であり、自らの意思で死期を決めたい人もいれば、すべて他力本願の人もいるわけです。そこでは「命の尊さは何ものにも代え難い」式の単純なきれい事では解決できないということです。
本人の意思の遂行を阻むのは自殺幇助罪や嘱託殺人罪などですが、自殺の違法性を問わずそれに協力した者だけが処罰されるという理屈は誰もが納得できるものではありません。自殺幇助を認めるいくつか国が存在するのはその反映でしょう。
これは森鴎外の「高瀬舟」の主題ともなった古典的な問題ですが、現実にはこの領域において、法は自殺幇助を装った殺人などのごく少数の悪意ある犯罪を防ぐために、非常に多数の自由を犠牲にしているように思われます。










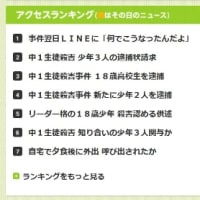

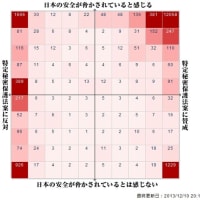
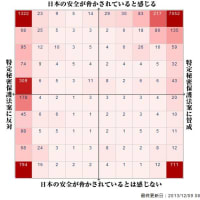
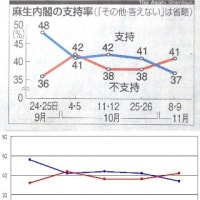
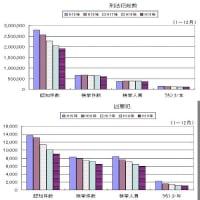
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます