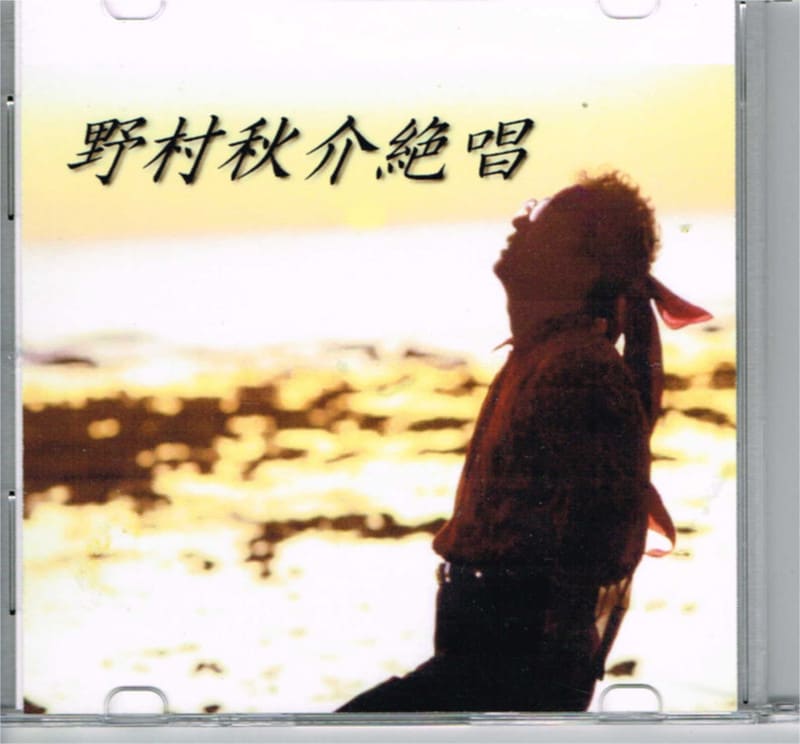六月二十四日(火)曇り後雨。
のっけから尾籠(びろう・きたなくて人前で失礼にあたること)な話で恐縮だが、先日胃カメラの検査をしてから、数日後に「ピロリ菌」の検査をするからと渡されたのが検便のキット。ううう検便など何十年ぶりである。
それを提出したら一週間ほどして「陽性なので呼吸の検査をするのでもう一度来てください」と連絡があった。それも朝から、水もダメ。飲まず食わずということなので、大好きな朝食を我慢して朝一番で病院へ行った。
まず、①検査容器に息をぷーっと入れる。②薬を一個、噛まずに水で五秒以内で飲む。③左を下にして五分間横になる。④その後に15分座っている。⑤再び息を検査容器に入れる。これでおしまい。結果はまた一週間後とのこと。まあ歳を取ると、歳なりにあちこちが傷んでくるから仕方ないか。
遅い朝食は、頂き物のマグロの味噌漬け、自家製のキュウリのおしんこと近所の肉屋さんで買った餃子。その餃子だが肉の卸問屋の前に「肉屋さんが作ったお肉たっぷりの餃子・50個、1296円」。とあるので前から気になっていたので、今日買ってみた。まあ値段なりに美味しい方でした。でももう買わないかな。
朝から天気が悪い。横浜に雷注意報が出た思ったらゴロゴロと鳴った。雷と言えば、明治の女流の平塚らいてうは、「雷鳥」とも書く。冬になると羽が純白になるのがきれいで「雷鳥」としたが、「雷」の字が嫌なので、ひらがなで「らいてう」としたそうだ。明治四十四年、雑誌「青鞜」の発刊を祝って、彼女が寄せた文章の表題、「元始、女性は太陽だった」との言葉は、その後、女性の権利獲得運動を象徴する言葉の一つとなったことは有名である。
平塚らいてうの話をもう一つ。金持ちのおばちゃんが若い男を囲うことを俗に「若いツバメ」と言うが、これも彼女らの雑誌「青鞜」に由来する。当時「青鞜」には、岡本かの子、山川菊栄、田村俊子、野上弥生子、高村光太郎の奥さんの千恵子、伊藤野枝、市川房江、与謝野晶子(さて、皆さんはこのすべての女性を知っていますかな)といった錚々たる女流が集っていた。私なんか名前を聞いただけで萎えてしまう。
余談ではありますが、野上弥生子先生は、1948年 - 日本芸術院会員、1957年 - 『迷路』で第9回読売文学賞、1964年 - 『秀吉と利休』で第3回女流文学賞、1965年 - 文化功労者、1971年 - 文化勲章、1981年 - 第51回朝日賞、1986年 - 『森』で日本文学大賞、という凄い作家で、更にご子息も皆さん立派な方ばかり。長男の野上素一先生は、京都大学教授でイタリア文学者。東京大学教授で物理学者の野上茂吉郎先生は次男、保守派論客で哲学者の長谷川三千子先生は、東京大学教授で物理学者の三男野上耀三先生の娘さんなのである。
平塚は二十八歳の時に三歳年下の画家、奥村博史と同棲していた。「青鞜」の表紙絵を書いていたのが彼である。「青鞜」は書生だけの雑誌であり、正に女の園、そこに奥村が入り込んできたために、後に「サンデー毎日」の編集長となる新妻莞が、「水鳥の群れに、若いツバメが飛んできて、ひっかきまわした」と批判したことから、「ツバメ」が、年下の若い男の愛人として使われるようになった。このエピソードは、嵐山光三郎さんの「文人悪妻」(新潮文庫)に出てくるエピソード。奥方の研究には最高の本ですぞ。
天気は悪いし、空からゴロゴロと雷様がお怒りなので、一日真面目にPCの前で仕事をしていました。夜は、酔狂亭で、雨の音をBGMに独酌。