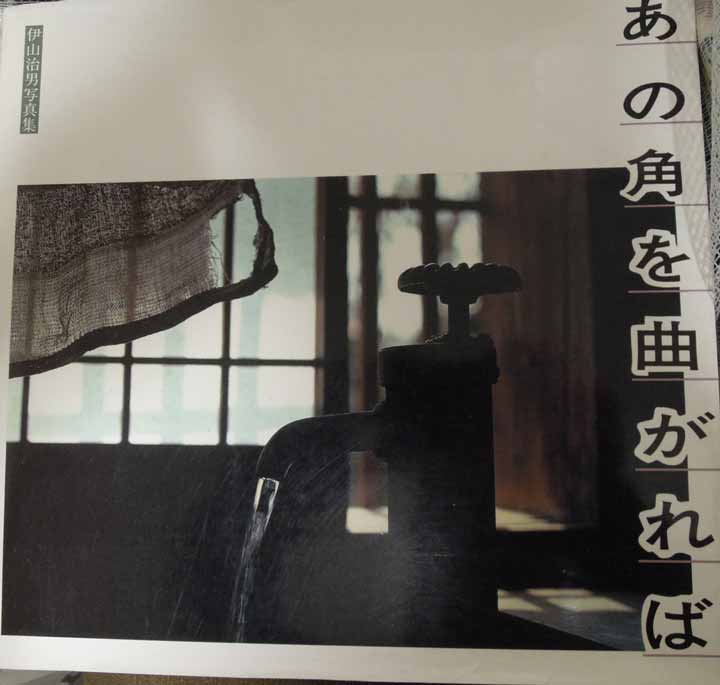一昨日ブログのアクセスが28万に到達しました。相当に偏った内容のブログですがそれでも見ていただける方々がおられる事は非常に有難く思います。
これからもよろしくお願いします。
さて、本題ですが今年最後の日は先日までの肌寒さも和らぎ思いのほかうららかな一日となりました。
毎年恒例(笑)としている大晦日の年越し運転、昨年まではメインレイアウトを舞台にその年に入線した列車を中心にひたすら走らせまくると言うのが定例でしたが今年は少し新機軸を取り入れました。
とはいえ、大掃除がずれ込んだために家事の合間を縫っての運転でしたが結構楽しませてもらっています。
大概の用事が前日までに終わる事が多く、こんな事が一日通して出来る意味で大晦日と言うのは貴重な日ではあります。

午前の部はメインレイアウトでの運転。
レールクリーニングの露払いを務めるのは昨夜(爆)電撃入線を果たしたEH200です。実は昨夜中古ショップで無闇に安い出物を見つけたものなのですが、帰宅してチェックするとパンタグラフが分解状態な上にKATOカプラーアダプターもなしという状態でした。とはいえパンタの方は欠損とは違いパーツは揃っていたのでピンセットを両手に再組み立て。
一晩格闘の末今朝やっと入線したものです。なるほど、安いのは一晩分の手間賃の分かと(汗)
クリーニングカーの牽引は短い無通電区間を楽にクリアできる性能が求められるのでEH級はうってつけと言えます。


白いかもめとNEXが行きかう本線部。
先日の線形修正は上手く言ったようで脱線トラブルは起きませんでした。
ですがこの一年殆ど手付かずだったつけが周囲のシーナリィの劣化と言う形で表面化しているのも確認できてしまいました。元々良い出来ではなかった所に経年劣化が加わると辛いものがあります。



午後の部はモジュールを使っての縁側「セミ屋外運転」。
今日の陽気があって初めて実現した企画と言えます。幸い晴れただけでなく殆ど無風だったので列車が吹き飛ばされる心配も殆どありません。
気分はすっかり庭園鉄道・・・といいつつミニカーブを使ったエンドレスだけなのですが。
傾きかけた日差しの中を鉄コレの単行電車が走行するさまには思わずゾクゾクしました(笑)
思えばコンペ出品などでレイアウトを屋外に出した事はあるのですが更に運転もやるとなるとこれまでに二三度しかありません。
天候さえよければここまでお手軽に出来る事が確認できたことは大きな収穫でした。
この後、夜の部を経て年越し走行に掛かる予定です。
最後になりましたが、
このブログにお付き合いいただいた皆様、この一年ありがとうございました。
それではよいお年を。
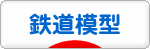 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
現在参加中です。気に入ったり参考になったらクリックをお願いします。
これからもよろしくお願いします。
さて、本題ですが今年最後の日は先日までの肌寒さも和らぎ思いのほかうららかな一日となりました。
毎年恒例(笑)としている大晦日の年越し運転、昨年まではメインレイアウトを舞台にその年に入線した列車を中心にひたすら走らせまくると言うのが定例でしたが今年は少し新機軸を取り入れました。
とはいえ、大掃除がずれ込んだために家事の合間を縫っての運転でしたが結構楽しませてもらっています。
大概の用事が前日までに終わる事が多く、こんな事が一日通して出来る意味で大晦日と言うのは貴重な日ではあります。

午前の部はメインレイアウトでの運転。
レールクリーニングの露払いを務めるのは昨夜(爆)電撃入線を果たしたEH200です。実は昨夜中古ショップで無闇に安い出物を見つけたものなのですが、帰宅してチェックするとパンタグラフが分解状態な上にKATOカプラーアダプターもなしという状態でした。とはいえパンタの方は欠損とは違いパーツは揃っていたのでピンセットを両手に再組み立て。
一晩格闘の末今朝やっと入線したものです。なるほど、安いのは一晩分の手間賃の分かと(汗)
クリーニングカーの牽引は短い無通電区間を楽にクリアできる性能が求められるのでEH級はうってつけと言えます。


白いかもめとNEXが行きかう本線部。
先日の線形修正は上手く言ったようで脱線トラブルは起きませんでした。
ですがこの一年殆ど手付かずだったつけが周囲のシーナリィの劣化と言う形で表面化しているのも確認できてしまいました。元々良い出来ではなかった所に経年劣化が加わると辛いものがあります。



午後の部はモジュールを使っての縁側「セミ屋外運転」。
今日の陽気があって初めて実現した企画と言えます。幸い晴れただけでなく殆ど無風だったので列車が吹き飛ばされる心配も殆どありません。
気分はすっかり庭園鉄道・・・といいつつミニカーブを使ったエンドレスだけなのですが。
傾きかけた日差しの中を鉄コレの単行電車が走行するさまには思わずゾクゾクしました(笑)
思えばコンペ出品などでレイアウトを屋外に出した事はあるのですが更に運転もやるとなるとこれまでに二三度しかありません。
天候さえよければここまでお手軽に出来る事が確認できたことは大きな収穫でした。
この後、夜の部を経て年越し走行に掛かる予定です。
最後になりましたが、
このブログにお付き合いいただいた皆様、この一年ありがとうございました。
それではよいお年を。
現在参加中です。気に入ったり参考になったらクリックをお願いします。