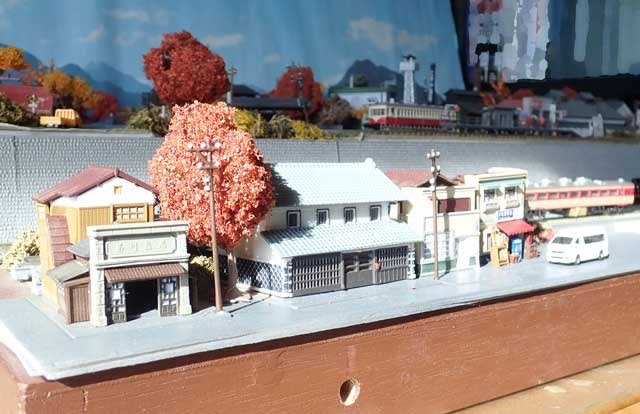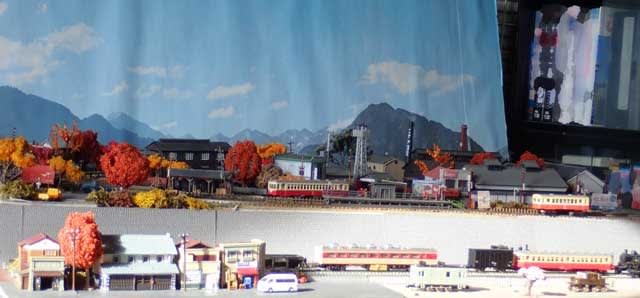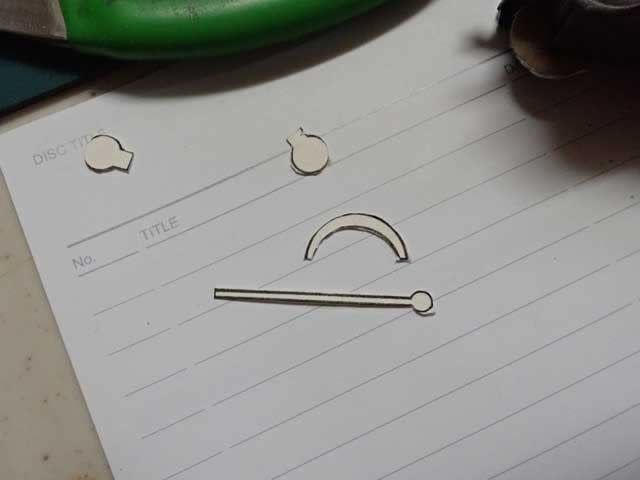今年に入って「休日に見晴らしのいいところにエスクァイアを持ち込んで車内で寝っ転がりながら本を読む」というある意味優雅、別の意味では変態的なカーライフを送っています(汗)

冬場の風景は雪のあるなしに関係なく物寂しい物ですが、寝っ転がった窓越しに眺める葉の落ちた冬の木々の枝振りはそれ自体が一服の画の様で、周囲の静けさと併せて落ち着いた気分を堪能できます。
そんなロケーションで読む本は自宅で読むのとは異なる感興が得られ、ゆったりした心持ちになれます。

この寛ぎは、まさに「書斎」の持つそれではないかと思いますが、車内で寝っ転がれるミニヴァンは車の停められるところならどこででも「景色の変わる書斎」の気分が味わえる点、他の車では味わえない楽しみが得られます。

ですがその一方で同じ休日の愉しみでもS660のもたらすそれは、エスクァイアのとは真逆。
「小さな車で走る事、運転することそのものが楽しみになる」境地はミニヴァンでは味わい難いと思います。特にスポーツカーだと「トランスミッションを通してエンジンとのコミュニケーションを楽しむ」「ステアリングを通して道と会話する」事ができますから一人で乗っていても孤独感を感じる事がありません。
実はこの「相反するクルマの魅力」を堪能できる事は充実したカーライフの一つではないかと感じています。殊に田舎暮らしの場合はそうです。

S660で山道を走って帰ってきてエスクァイアに乗り換えると1メートル近く上がった視点とアップライトに座らせるシートポジション故に「同じ風景がとても新鮮に見えます」あの見晴らしの良さはS660ではまず味わえません。
その一方でエスクァイアに乗るとS660の様に走ることはまずできない。同じ山道を走っていてもカーブを曲がる、アクセルを踏み込む事が「仕事」になってしまう感覚があります。
そのかわり上述した「持ち運べるくつろぎの空間」の楽しみが得られるのですからその魅力も捨て難いのです。

大都市圏で駐車スペースにも苦労する様な条件では「正反対の性格の車を使い分ける」のが難しいのはわかります。ですが500万円の車を1台買うのに比べれば、それと同額で2台を使い分けた方が確実にカーライフは充実すると思えます。
それも似た様な性格の2台(例えばSUVとミニヴァン)よりは正反対の性格の2台(例えばCCVと軽のボンヴァンとか)だと相互の魅力は2倍ではなく2乗に感じられると思います。
なぜならクルマの性格やメリットが正反対なので個々の車のキャラクターというのを理解しやすくなりますし、それだけ視野が広くなるのを実感できるからです。今まで「欠点」だと思ってきたことが実は欠点と言うよりも「個性のひとつ」として捉えられるようになる気がします。
それに何よりそういう選び方だと車を買うときに「欲張らなくなる」利点もあります。
1台であれもこれもと欲張ると必ずその皺寄せがどこかにくる物ですから(「皺寄せ」を具体的に挙げるなら馬力と図体と思います。カッコも良く、室内も広く、荷物もいっぱいといった具合に欲張ってゆくとサイズが巨大化し、それに伴い車重も重くなる。それをカバーするために馬力をいたずらに上げる。結果、そこいらの路地にも入れない、駐車場でドアひとつ開くのにも苦労する様な恐竜みたいなクルマになってしまうといった具合)
まあ、こんな事を考えつくのも「原住地が田舎だから」なのでしょうね。