

今月の買い物から。
発売予告を見たときから発売を心待ちにしていたカーコレのコンパクトカー編がやっとリリースされました。
どこでも見かける車たちですが、殊に都市をモチーフにしたレイアウトには不可欠な存在なだけに早速レイアウト上にはべらせて観ました(笑)
今回のラインナップは2代目のヴィッツ、初代フィット、3代目マーチ、2代目デミオという組み合わせですがよく見ると車種ごとのフォルムの違いがセダン以上に大きいので纏めて配置しても意外に単調な雰囲気にならず中々良い車種選択と感じました。
車体の色刺しも実車の雰囲気を捉えていますが、フィットなどは実車よりもやや腰高なので人間目線で見たときに少し損をしているようです(この種のコンパクトカーは一般にセダンよりも背が高い事が多いのですが)
ボディカラーもカラフルな物が多いので並べると町並みを華やかに見せる効果もありそうです。

今回は今日の買い物から。
先週末の発売のモデルでしたが、ネットなどでは早々売り切れになった所もあるとの話もあってひやひや物の購入でした。
今回のは16m級の電車が中心ですが、ここ最近のラインナップが順調に(?)車体が大型化していたので(第7弾の様にそれまでのシリーズがクリアできていた所に車体が接触しレイアウトの改修を要する物もありました)今回のダウンサイジングは個人的には歓迎しています(笑)

今回のラインナップは新潟の車輌と元地下鉄の車輌が多いのが特徴ですが、高松琴平電鉄の723+724の組み合わせ(元は名古屋の地下鉄)がビル街にもそこそこ似合う小型電車という意味では私のレイアウトでは使えそうな印象でした。
もう一つ、叡山電鉄のデオ301も色調が好みなのとKATOの「きらら」と組み合わせる事ができそうな所(時代的に一致するかどうかは解りませんが)からこれも期待株です。この車輌は鉄コレでは珍しく前照灯部にクリアパーツが入っている様で微妙に他のとは印象が違って見えます。
他にも使えそうな物は色々ありますが、残念な事にいつもなら同時発売になっている筈の専用動力ユニットが来月発売との事でこれらの車輌が活躍するのは暫くお預けとなりそうです。
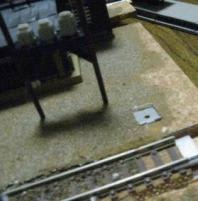
先日来当初の計画とは徐々に違う形で進行してきた機関区の製作ですが、遂に電化まで行ってしまいました(苦笑)
以前にも触れた通り今回の機関区は大量入線したジャンクの蒸気機関車を並べる目的で製作した物ですが、製作が進むに連れて蒸気とほぼ同じ数だけ在籍している電気機関車にも対応させたい欲が出てきてしまいました。
とはいえ、電気機関車用に新しいセクションを製作するスペースも予算も無い事から現在製作中の機関区の設備の一部を差し替え可能とする事で対応する事にしました。
その為、先ず付け外し可能な架線柱を設置する為に既に仕上がりつつあった地面に改めて穴を開けなおし架線柱の架台を埋め込む事にしました。線路がTOMIX である事から架線柱もTOMIXのものを使用(一部にDDF)する事とし、4線ビームと2線ビームの組み合わせで5つの側線をカバーする形としました。

さて、これが現在の蒸気機関車用のセクションの状態です。これを電気機関車にも対応する景色に差し替えるとどうなりますか。


今回は普通の工程です。
給炭台や給水塔はKATOの製品を使いました。但し、ベースが厚すぎてこのままでは様になりませんのでベースのコルク部をくりぬいてはめ込む形としたのは以前紹介したとおりです。
さて、給炭台とくれば、石炭・砂・灰が付き物なのですが、ここで何を使うかが悩み所でした。
石炭については市販の着色バラストが見つからなかったので昔の製作記事にあった冷蔵庫用の脱臭剤の活性炭を最初考えたのですが、いまどきの脱臭剤でそのまま石炭代わりになる物を見つけられず断念。次に本物の石炭と思ったのですが、昔と違って今は石炭自体なかなか見かけなくなり(そもそも使うにしても1個か2個)これもあきらめざるを得ませんでした。
結局はバーベキュー用の木炭を砕いて使う事にしました。幸い物置の隅に以前の使い残しがあってそれを使えたので助かりました。
砂はパウダーを、灰は煙草のそれを使いましたが、石炭殻の色はもう少し違っていたような気もします。

併せてプラの地色丸出しの給炭台などのウエザリングも施しました。こちらはパステル使用ですが、粉状の炭を使ってもよかったかもしれません。

こうして蒸気機関車の機関区の製作は徐々に進んでいますが・・・

先月の新製品で貨物駅と並んで注目していたのが「電車庫」と言う製品でした。
電車庫とは名乗っていますが機関庫でも通用しそうな雰囲気があり十分使えそうに感じていました。
何より他社の車庫類は殆どが複線仕様で単線で使えるサイズの物がなかったのでその意味でも今回のリリースは私にとっては朗報だった訳です。
機関庫を組み込むのは当初の予定に無かったのですが、そんな訳で急遽組み込む事にしました。


やはりこんな小型の車庫であってもあるとないとではまるで雰囲気が違います。やはり機関庫は機関区のセクションに不可欠な存在であると再認識させられました。
先日の貨物駅とあわせて機関区のセクションの雰囲気は当初の計画から更に雰囲気が変わってきました(笑)
先月の末にトミーテックのジオコレから様々な建物類(それも鉄道関連が結構多い)がリリースされました。
一時にこれだけ大量に出られるととても全部はフォローできる筈も無くごく一部の購入に留まった訳ですが、その中の一つに貨物駅というのがありました。
貨物ホームと農業倉庫の組み合わせで田舎に限らず近郊の駅でも結構見掛けるタイプです。
ところでこのキット、汲み上げて見ると建物類の寸法が街コレ第4弾の駅舎やホームとほぼ同寸である事がわかりました。
つまり先日機関区セクションに配置した小型車用の駅と差し替えが利く訳です。
というわけで早速試してみました。
やってみるとあたかも前からここには貨物駅があったかのようなはまり具合です。確かに機関区には電車の駅より貨物駅が隣接している方がより似合うとも思えるのですが・・・
少し悩んだ末にこの部分は駅と貨物駅をコンバートできるようにする事にしました。


これで済むかと思ったのですが、予想外の変更はまだ続きます(笑)
一時にこれだけ大量に出られるととても全部はフォローできる筈も無くごく一部の購入に留まった訳ですが、その中の一つに貨物駅というのがありました。
貨物ホームと農業倉庫の組み合わせで田舎に限らず近郊の駅でも結構見掛けるタイプです。
ところでこのキット、汲み上げて見ると建物類の寸法が街コレ第4弾の駅舎やホームとほぼ同寸である事がわかりました。
つまり先日機関区セクションに配置した小型車用の駅と差し替えが利く訳です。
というわけで早速試してみました。

やってみるとあたかも前からここには貨物駅があったかのようなはまり具合です。確かに機関区には電車の駅より貨物駅が隣接している方がより似合うとも思えるのですが・・・
少し悩んだ末にこの部分は駅と貨物駅をコンバートできるようにする事にしました。


これで済むかと思ったのですが、予想外の変更はまだ続きます(笑)

先日の「あおば」ことキハ181系に続いて中古ショップでジャンク扱いで売られていたのがKATOの12系3両でした。
実は12系客車のセットは来月にもJR東日本仕様が発売される事になっており既に予約しているのですが、車掌車の窓周りが少し違う雰囲気のようでしたので普通の12系も欲しかった所でした。
牽引機を択ばないこの客車の性質上多少多くても困る訳ではないのでこれも掘り出し物といえます。

さて、私の故郷ではかつて12系といえば、先ず連想されるのが「修学旅行列車」でした。
中学の修学旅行は北海道だったのですが、同じ市内の何校かで一つの列車を借り切って青森まで移動していた訳です。図鑑で見るような155系電車やあおぞら号(修学旅行用)等うちの田舎で走る訳も無く、当時は物足りなく思っていましたが、今となってはその12系でも懐かしく感じられます。
本来ならセットを購入した段階で再現する所ですが、今回の車輌を使って一足早く当時を再現してみました。

今回の機関区セクションは元々モジュールのエンドレスと接続して小型車両の入換を行なう設備として企画した物です。
その為にセクションの端の部分は小型車に対応する駅を設置しました。

一見してお分かりの様に街コレの小型駅とホームをそのまま使っています。
ただ、このままではホームと地面の段差が目立ってしまうため地面部分に紙粘土を敷いて高さを揃えようとしました。
ところがこれが失敗でした。紙粘土は乾燥時の収縮がプラスター(化学反応で固まる為か、紙粘土ほどには収縮しません)よりも大きく後になるほど継ぎ目の部分が目立つ結果になりました。
この部分はいずれ改修しなけばなりません。

形が出来た駅セクション部分は先日の帰省時にモジュールと共に実家へ持ち込みました。何しろこれがないとただのエンドレスのみになってしまうので実際の運転でも重宝しました。
このメリットは今後の運転会でも生かせるのではないかと思います。
・・・と、ここまではできたのですが、この後この駅部分を含めたセクション自体に計画とは違った部分が出てくる事になります。
その為にセクションの端の部分は小型車に対応する駅を設置しました。

一見してお分かりの様に街コレの小型駅とホームをそのまま使っています。
ただ、このままではホームと地面の段差が目立ってしまうため地面部分に紙粘土を敷いて高さを揃えようとしました。
ところがこれが失敗でした。紙粘土は乾燥時の収縮がプラスター(化学反応で固まる為か、紙粘土ほどには収縮しません)よりも大きく後になるほど継ぎ目の部分が目立つ結果になりました。
この部分はいずれ改修しなけばなりません。

形が出来た駅セクション部分は先日の帰省時にモジュールと共に実家へ持ち込みました。何しろこれがないとただのエンドレスのみになってしまうので実際の運転でも重宝しました。
このメリットは今後の運転会でも生かせるのではないかと思います。
・・・と、ここまではできたのですが、この後この駅部分を含めたセクション自体に計画とは違った部分が出てくる事になります。
今回は先日入線した中古車両の話です。
私の地元の鉄道模型を扱う中古ショップでの話ですが、このショップが鉄道模型を扱い始めて3年位になりますか、大抵のセット品はケースに何が入っているか書かれて並んでいるのですが、その中に一セットだけ表記のないパッケージの物がありました(というよりケースに付属の紙の札が取れてなくなっていた)見た目は見るからに年代物という風情です。
これらの店ではショーケースに施錠している事が多いのですが、買う気もないのにわざわざ店員さんに開錠して貰って中に何が入っているか確かめるのも億劫な気がして暫くそのままになっていました。
先日他のジャンク品を確かめた際についでにと思ってその「謎のセット」の中味も見せてもらいました。
中味はTOMIXのキハ181系6連でした。
その時はそのままで終わりましたが、最近になって妙に気になってきて先日思い切って買ってしまいました。
というのも、セットの編成をよく見ると気動車時代の特急「あおば」の編成が組めそうだと気付いたからです。

今だと「あおば」というとこの間まで走っていた東北新幹線の電車が連想されますが、70年から75年頃までの一時期、キハ181系を使った「あおば」が北上線経由で秋田まで走っていました。
当時、一度だけ見た事があるのですが子供の頃の事でてっきり82系だと勘違いして覚えていました。実際2両並べないと素人には違いが解らないくらい似ていますし。

旧「あおば」はいずれは手に入れたいと思っていた編成ですがそんな訳で当初はキハ82系で代用しようかと考えてもいたのですが、こうしてキハ181系が目の前に出てくると食指が動いてしまいました。
とはいえ、ケースのぼろさなどもあってでしょう、当時の定価からすると信じられない値段で買えましたが。
このセットは動力車がキロである事やTNカプラー非対応な所から初期の製品と思われます。走りはちゃんとしておりヘッドライトも点灯するのでレイアウトで走らせる分には十分以上といえます。
私の地元の鉄道模型を扱う中古ショップでの話ですが、このショップが鉄道模型を扱い始めて3年位になりますか、大抵のセット品はケースに何が入っているか書かれて並んでいるのですが、その中に一セットだけ表記のないパッケージの物がありました(というよりケースに付属の紙の札が取れてなくなっていた)見た目は見るからに年代物という風情です。
これらの店ではショーケースに施錠している事が多いのですが、買う気もないのにわざわざ店員さんに開錠して貰って中に何が入っているか確かめるのも億劫な気がして暫くそのままになっていました。
先日他のジャンク品を確かめた際についでにと思ってその「謎のセット」の中味も見せてもらいました。
中味はTOMIXのキハ181系6連でした。
その時はそのままで終わりましたが、最近になって妙に気になってきて先日思い切って買ってしまいました。
というのも、セットの編成をよく見ると気動車時代の特急「あおば」の編成が組めそうだと気付いたからです。

今だと「あおば」というとこの間まで走っていた東北新幹線の電車が連想されますが、70年から75年頃までの一時期、キハ181系を使った「あおば」が北上線経由で秋田まで走っていました。
当時、一度だけ見た事があるのですが子供の頃の事でてっきり82系だと勘違いして覚えていました。実際2両並べないと素人には違いが解らないくらい似ていますし。

旧「あおば」はいずれは手に入れたいと思っていた編成ですがそんな訳で当初はキハ82系で代用しようかと考えてもいたのですが、こうしてキハ181系が目の前に出てくると食指が動いてしまいました。
とはいえ、ケースのぼろさなどもあってでしょう、当時の定価からすると信じられない値段で買えましたが。
このセットは動力車がキロである事やTNカプラー非対応な所から初期の製品と思われます。走りはちゃんとしておりヘッドライトも点灯するのでレイアウトで走らせる分には十分以上といえます。

今回のセクション製作で個人的に一番の難関と思ったのは給炭台付近につけたアシュピットでした。
物はKATOから出ていたのですが、線路の真ん中部分をカットして埋め込むだけと簡単に考えていたのが運の尽きでした(笑)
実際にカットしたのはTOMIXの線路でしたがカットそのものにかなり手間を食ってしまった上にアシュピットの高さが合わずアシュピット部分の切削まで加わってしまいました。
見た目に小さな施設でしたがここまでで半日近く掛けてしまいました。
何事もなめて掛かると痛い目に遭います。

その他の部分として通路と踏み切り部分を貼り付けました。これもKATOの製品をTOMIXの線路に貼り付ける形で行なったので微妙に寸法のずれがあります。

いきなり薄汚い建物をお見せしました(笑)
今回の機関区セクションの製作では可能な限りありものを使うという方針ですが、建物類についても給水塔・給炭所など以外はこれまで取っておいた建物を使っています。
その中でも写真のGMの信号所・詰所は年代が長い物です。何しろ昭和50年に新発売されてすぐに購入して組み立てた物を33年間取っておいた物です。とはいえ、流石に33年前の状態で流用する訳に行かない(殆ど塗装もせず素組みした物)ので屋根や土台を塗り替え、多少の修正をしてあります。

手を加えたあとの写真ですが、殆ど変わり映えがしません(笑)ここは製作者の不器用さがモロに出ます。
詰所についてはこの後にKATOの給水柱のパーツに付属していた煙突を取り付け、街コレやKATO製品から取り出したドラム缶などを配置しています。

3ミリ厚のコルクを線路の隙間に敷き詰めると良い具合に線路が地面に対して埋まってきたような雰囲気が出てきました。
ここでバラストの撒布です。
作業内容は第二モジュールとほぼ同じですので割愛しますが機関区ということもあってブレンドするバラストの割合を茶色を多めにしてあります。とはいえ、どんな色になるかは実際乾燥してみるまで分からないだけに結構どきどき物でした。

乾燥直後の図です。やや色が暗めですが、
ここで地面の塗装とパウダー播きを行ないます。先ずリキテックスカラージェッソのローアンバーで下地塗りを行い乾燥前にブレンドしたパウダーを撒いていきます。今回は機関区なのでバラスト部分にもパウダーをうっすらと撒いて地面との境界をぼかす処理を試行しました。
これまでは指でパウダーを撒いたり穴開きペットボトルを使う等してみましたが今回は使い古しの茶漉しを貰ったのを幸い早速使ってみました。
この方法だとペットボトルの場合と違ってごく少量からパウダーを撒けることと均一に撒布できる事が解り次回からはもっと積極的に使ってみる積りです。

現在の地面の状態です。まだ雑草や繁みなどが追加されていません。
ジャンクや中古を取り混ぜても先月は怒涛の入線ラッシュだったのですが、今月は流石にそんなハイペースには行きません(というか、それが当たり前なのですが・・・)
今月はもう一つ、かねて予約していたTOMIXのEF15も2度ほどの延期を経て先日やっと入線を果たしました。

デッキ付きの電機はこの間ジャンクでEF57が入線したばかりですが、個人的には東京見物などの折に山手線と並走する貨物列車をEF15や18辺りが牽引していたのでこの種の電機に「都会の象徴」というイメージを重ねて見ていました(笑)


とはいえ、活躍していた年代の幅が広くほぼ満遍なくどこでもいた機関車のようなのでC63同様に違和感無く溶け込めそうです。ワキやタキ、ホキ等牽かせる貨車にも融通が利きそうですし。
今月はもう一つ、かねて予約していたTOMIXのEF15も2度ほどの延期を経て先日やっと入線を果たしました。

デッキ付きの電機はこの間ジャンクでEF57が入線したばかりですが、個人的には東京見物などの折に山手線と並走する貨物列車をEF15や18辺りが牽引していたのでこの種の電機に「都会の象徴」というイメージを重ねて見ていました(笑)


とはいえ、活躍していた年代の幅が広くほぼ満遍なくどこでもいた機関車のようなのでC63同様に違和感無く溶け込めそうです。ワキやタキ、ホキ等牽かせる貨車にも融通が利きそうですし。
今年に入って機関車の入線が新品・中古・ジャンクを問わず続いています。
特に蒸気機関車はついこの間を思い出すと信じ難いほどの増えっぷりなのですが、その極め付けのような機関車が先日入線しました。
マイクロエースの「C63」。
設計図のみで実車がこの世に存在しない、ある意味SFともいえる機関車です(綿密な設定ー設計図ーが為されているのに実物が存在しない点においてガンプラと同列の「模型」といえるかもしれません)
とはいえ、元々C58の後継機として設計がスタートした(らしい)だけにレイアウトで使う蒸気としてのポジションは使いやすい万能機ともいえます(C58との重連すら想定できますし)


早速レイアウトで試走です。牽引するのはついさっき中古ショップで特売品を見つけた12系。C63と組ませるには重宝します。
モデルとしてのC63はやや腰が高そうに見えますが、走行性能は上々。140Rのカーブもクリアできました。
実車は幻でも当レイアウト上では最前線で活躍できそうです(笑)
特に蒸気機関車はついこの間を思い出すと信じ難いほどの増えっぷりなのですが、その極め付けのような機関車が先日入線しました。
マイクロエースの「C63」。
設計図のみで実車がこの世に存在しない、ある意味SFともいえる機関車です(綿密な設定ー設計図ーが為されているのに実物が存在しない点においてガンプラと同列の「模型」といえるかもしれません)
とはいえ、元々C58の後継機として設計がスタートした(らしい)だけにレイアウトで使う蒸気としてのポジションは使いやすい万能機ともいえます(C58との重連すら想定できますし)


早速レイアウトで試走です。牽引するのはついさっき中古ショップで特売品を見つけた12系。C63と組ませるには重宝します。
モデルとしてのC63はやや腰が高そうに見えますが、走行性能は上々。140Rのカーブもクリアできました。
実車は幻でも当レイアウト上では最前線で活躍できそうです(笑)













