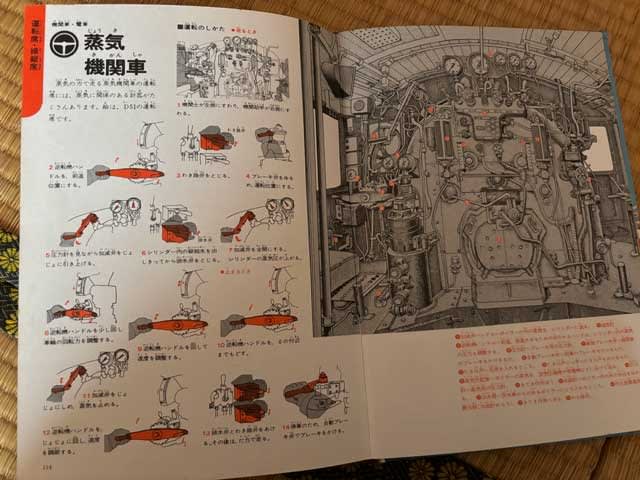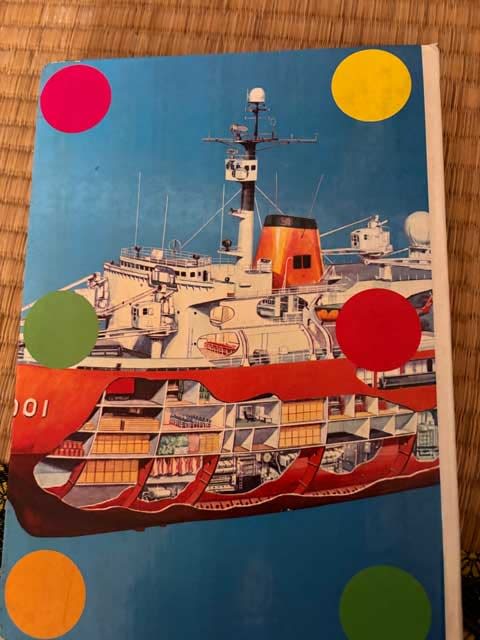今回は昨年暮れの四度目の帰省の話から。

往路の「はやぶさ」はコロナ禍以来、5年ぶりくらいの東京始発となりました。
時間はそろそろお昼時でもあったので新幹線改札前の駅弁屋へ。
思えば東京駅で駅弁を買うのも5,6年ぶり、あるいはそれ以上かもしれません。

そこで拾い上げたのが「東京肉三昧弁当」という奴。
「東京ステーションホテル総料理長 石原雅弘監修」というのが売りの様です。
黒毛和牛カルビ甘辛焼き(東京の醤油醸造所 丸大豆醤油使用)
豚ロース生姜焼き
鶏モモ江戸甘味噌焼き(江戸甘味噌使用)
と、錚々たるメンツが揃った「肉肉しい駅弁」です。
期待を胸に秘め、そのまま「はやぶさ」のE席へ。
大宮と宇都宮の間くらいでそろそろと蓋を開けます。

手前に生姜焼、奥に鳥味噌焼が配置されていますが、上から食べても下から食べても「2番目に箸を付けるのは牛カルビ」になるという計算された配置(そうか?)
つまり「豚と鳥は来たる牛カルビへの前奏曲(あるいはエピローグ)」という訳なのでしょう。
私は手前の方から頂きましたが、駅弁に豚の生姜焼きというのは(少なくとも東日本では)割合珍しい気がします。生姜焼きは自家製弁当には定番のおかずですからわざわざ駅弁で出すメリットが薄いのかもしれません。
ですが生姜風味でさっぱりした舌で次に来る和牛カルビを口にすると、これがまた芳醇な風味と赤身と脂身のハーモニーが食欲をそそりました。
その後の甘味噌焼(と付け合わせの人参、椎茸)は牛の脂身の残る舌をあっさり系の風味で締めてくれます。
まあ、駅弁なんてどこから食べても満足感がある物ですが、この弁当に関しては「3種の肉の交響曲」を楽しむ感覚で食べるのが似合う気がしました。
肉の交響楽に気を取られて一緒に買ったビールの存在をうっかり忘れるくらいに(笑)

往路の「はやぶさ」はコロナ禍以来、5年ぶりくらいの東京始発となりました。
時間はそろそろお昼時でもあったので新幹線改札前の駅弁屋へ。
思えば東京駅で駅弁を買うのも5,6年ぶり、あるいはそれ以上かもしれません。

そこで拾い上げたのが「東京肉三昧弁当」という奴。
「東京ステーションホテル総料理長 石原雅弘監修」というのが売りの様です。
黒毛和牛カルビ甘辛焼き(東京の醤油醸造所 丸大豆醤油使用)
豚ロース生姜焼き
鶏モモ江戸甘味噌焼き(江戸甘味噌使用)
と、錚々たるメンツが揃った「肉肉しい駅弁」です。
期待を胸に秘め、そのまま「はやぶさ」のE席へ。
大宮と宇都宮の間くらいでそろそろと蓋を開けます。

手前に生姜焼、奥に鳥味噌焼が配置されていますが、上から食べても下から食べても「2番目に箸を付けるのは牛カルビ」になるという計算された配置(そうか?)
つまり「豚と鳥は来たる牛カルビへの前奏曲(あるいはエピローグ)」という訳なのでしょう。
私は手前の方から頂きましたが、駅弁に豚の生姜焼きというのは(少なくとも東日本では)割合珍しい気がします。生姜焼きは自家製弁当には定番のおかずですからわざわざ駅弁で出すメリットが薄いのかもしれません。
ですが生姜風味でさっぱりした舌で次に来る和牛カルビを口にすると、これがまた芳醇な風味と赤身と脂身のハーモニーが食欲をそそりました。
その後の甘味噌焼(と付け合わせの人参、椎茸)は牛の脂身の残る舌をあっさり系の風味で締めてくれます。
まあ、駅弁なんてどこから食べても満足感がある物ですが、この弁当に関しては「3種の肉の交響曲」を楽しむ感覚で食べるのが似合う気がしました。
肉の交響楽に気を取られて一緒に買ったビールの存在をうっかり忘れるくらいに(笑)