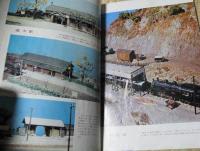1976年の11月頃のことです。
行きつけの店で最新号のTMSを見つけ、開いてみるとそれまで見た事のない写真が目に飛び込んできました。
木造の駅舎とホーム一式が組み立て式のセットとなって整然と並ぶ写真。
砂利が表現されたプラ製の道床の付いたシステマティックな線路一式。
それまでの武骨なデザインのそれとは明らかに違うしゃれた雰囲気のパワーパック。
当時の16番の金属道床のシステム線路と簡易式の建物類で成り立っていた組み立て式レイアウトシステムとは明らかに一線を画した模型システムであることが一目でわかる写真でした。
その記事の見出しには9ミリゲージの新システム「TOMIX」とあります。
最初は西ドイツのトリックスの誤植かと思いましたが、読みすすめてみると「ナインスケール」のトミーがリリースする新システムであることがわかり二度びっくりしました。
それまで日本型Nゲージのレイアウト構築システムは16番はもとよりNよりも歴史の浅いメルクリンミニクラブのそれよりはるかに立ち遅れていたものでしたがTMSの記事にあるシステムはその遅れを一気に取り返してお釣りが来るくらいの物として私の眼に映った訳です。
同時にそれは単なる新シリーズの域を超えて今まですべてを自作に頼るしかなかったがゆえに私のような不器用な年少者にとって手の届かない存在だったレイアウトの夢を一気に身近なものとして引き寄せる衝撃でした。
その時点では発売時期や価格はすべて未定の段階だったのですが記事を読むだけで当時の私を酔っぱらわせるには十分なものでした。
実際にリリースされた製品が手に入ったのはそれから約一年後のことでした(発売自体はそれより前だったのですが学生の私にはやや高価なものだったので翌年のクリスマスでないと入手できなかったのです)
10本の直線線路と駅舎・ホームのセットでしたがその線路上に初めてDD13(ナインスケール時代のTOMY製)が走った時の衝撃。
畳の上でもジョイント音を響かせながら安定した走りをしてのける様は私にも鉄道模型の新時代が来たことを実感させるに十分でした。


その後数年間の間にエンドレス・待避線と徐々に線路を拡張しながらレイアウト制作の機運を徐々に高めていきました。その当時に購入した建物類の大半は今も所持しています。とはいえ学生時代に下手なペイントやディテールアップをしたせいもあって見た目は例によって(笑)大惨事ですがこれらも今の私にとっては思い出の品としていつかレイアウトに組み込みたいと考えています。