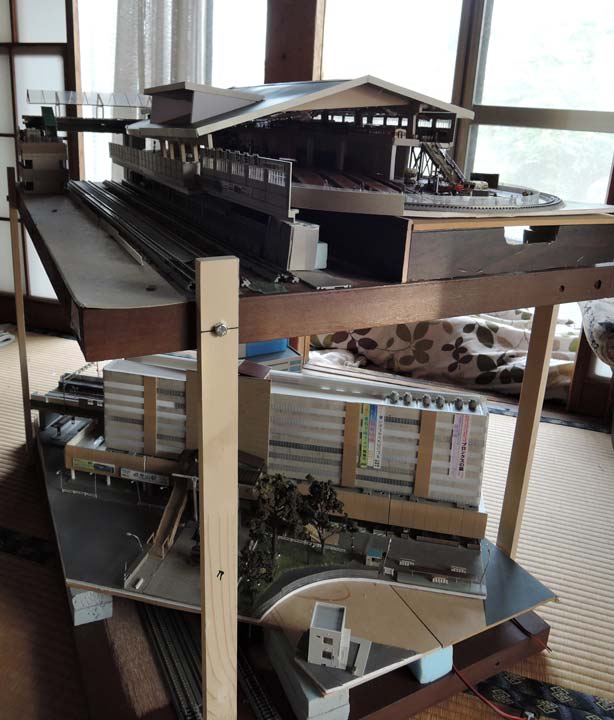今回は「急行出雲」所収の河野典生作「機関車・草原に」から
鉄道ミステリアンソロジーとはいえ、光文社時代の鮎川哲也は推理物に限定せずに幻想譚やSF、怪談まで幅を持たせたバラエティ豊かなセレクトで読者を魅了しました。
その中でも本作は特に異色なハードSFとして描かれた物です。
北極海での核爆発事故をきっかけに海浜都市部が殆ど壊滅した未来の世界。
世界の主要都市は山岳地帯へ移転し都市間は飛行機と大陸間を結ぶ原子力列車の鉄道網でカバーされ、東京をはじめとした旧都市部は半分水没した廃墟として骸をさらしている時代。
この設定、エヴァンゲリオンの背景設定に酷似した印象がありますが本作の上梓はそれより20年以上前です。
その廃墟には新時代から取り残された老人たちとまた、中央都市帯から脱走してきた少年少女たちの流浪者の群れが住み着き、その老人の一人である元機関士と少年たちが互いの企みのために旧東京駅の地下で「博物館から引っ張り出してきた蒸気機関車群をレストアする」
だが廃墟となった東京の無価値さと危険性を感じ取った中央政府はミサイルによる旧東京の爆破・破壊を決行しようとする・・・
大まかなストーリーはこんな感じですが全編に漂う乾いた筆致とハードボイルドな空気が一種の緊張感と独特な心地よさを感じさせる一篇で短編ながらも「作品世界と一体になった錯覚」を与える読後感をもたらします。
本作に登場するのは「ロクジロウ」と名付けられたC62、「ゴイチロウ」ことD51、「ゴシチロウ」ことC57、そして「ゴジロウジュニア」としてC52が登場します。
・・・ここまで読んで「あれっ?」と思ったSLファンは多かったのではないかと。

そう、この中でC52は20世紀末どころか昭和20年代に全機廃車になって保存機すら残されなかった「存在しない機関車」なのです。
作者もそれに気づいたのか作中ではC52の描写は殆ど(と言うか全く)ありません。
「ただ出ているだけ」と言う随分な扱いだったりします。本作の主人公がD52に因んだ「五二郎」と言う老人なのでそこにひっかけただけと言うのが正直なところだったのではないかと思います。
まあ物がSFだから「C52が残っていたパラレルワールド」という事でもいいかと思います。
ですが、私が読んだ感じから言うならC52こそ本作の作品世界に一番似合う外見の蒸機だったと思います。
C52のNゲージモデルはマイクロエースから16番モデルもしなのマイクロと天賞堂から出ていてその魅力については私もこのブログで何度か語った事があります。
C52は日本最後の輸入蒸気機関車としてアメリカで作られた8200という3シリンダ機をベースに後の瀬野八入線に合わせて補機に対応した改造を施された物です。
元々は国産3シリンダ機製造のためのサンプルの色彩が強く(これを基に生まれたのがC53)8200として脚光を浴びたのもわずかな期間。
C52に改造されてからの晩年は瀬野~八本松間で「峠の後押し」ばかりやらされていたのでファン以外の人には目に触れにくい機関車でした。
そのせいか大概の蒸気機関車本では非常に影の薄い扱いを受けている悲劇のロコでもあります。
「元の8200蒸機の優美なボディを瀬野八対応の改造工事で醜くされた」とか悪評も多いC52ですが、その改造による独特の凄味のある異形感は優美さとは真逆の魅力を湛えています。
例えるならば「走るサイバーパンク」「蒸気で動くモビルスーツ」という趣でしょうか。とにかく停まっていてもパワフルさを感じさせる凄みがあるのです。
私個人の感想では「日本にこんなかっこいい蒸気機関車があったのか!!」と言うカルチャーショックを与えてくれたのがこのC52です。
大体、「ミサイルが飛び交い沿線の高層ビルに次々着弾する品川の旧東海道線を破片をかいくぐりつつ子供たちを乗せた無蓋車を牽きながら爆走する蒸気機関車」なんてシチュエーション、C57とかD51よりもC52の方がぴったりくると思うのですが…
「このロクジロウは、自分で食ってたもので、自分で馬力を出し、自分で走る。しかし、こいつの食い物はわしが食わせてやる。わしはできるだけ良質の石炭を、うまいタイミングで食わしてやりこいつに最高の力が出せるように手伝ってやる。
そのわしをこいつは軽々と運んでくれる。これが人間と機械との本当の関係でないのかね。
最近じゃ都市帯じゃ、自動車道路まで手放しで走れる装置がついとるそうじゃないか。人間は中でテレビをみとるそうじゃないか。いったい、何を根拠に、そんなに機械を信用しとるのかね」
(光文社カッパノベルズ刊「急行出雲」所収「機関車、草原に」239Pより引用)
ここに書かれている蒸気機関車の魅力を私が気付いたのは本書を読んでだいぶ経ってからです。
そしていまこれを読み返して見て、現在のこの現状を引き比べる時、うすら寒い感じを受けるのは気のせいでしょうか。
本作はいわゆるミステリとは異なるジャンルに属するものですが、それでいてもっとも強烈な読後感を残す一篇です。
未読の方には是非お勧めしたいと思います。
鉄道ミステリアンソロジーとはいえ、光文社時代の鮎川哲也は推理物に限定せずに幻想譚やSF、怪談まで幅を持たせたバラエティ豊かなセレクトで読者を魅了しました。
その中でも本作は特に異色なハードSFとして描かれた物です。
北極海での核爆発事故をきっかけに海浜都市部が殆ど壊滅した未来の世界。
世界の主要都市は山岳地帯へ移転し都市間は飛行機と大陸間を結ぶ原子力列車の鉄道網でカバーされ、東京をはじめとした旧都市部は半分水没した廃墟として骸をさらしている時代。
この設定、エヴァンゲリオンの背景設定に酷似した印象がありますが本作の上梓はそれより20年以上前です。
その廃墟には新時代から取り残された老人たちとまた、中央都市帯から脱走してきた少年少女たちの流浪者の群れが住み着き、その老人の一人である元機関士と少年たちが互いの企みのために旧東京駅の地下で「博物館から引っ張り出してきた蒸気機関車群をレストアする」
だが廃墟となった東京の無価値さと危険性を感じ取った中央政府はミサイルによる旧東京の爆破・破壊を決行しようとする・・・
大まかなストーリーはこんな感じですが全編に漂う乾いた筆致とハードボイルドな空気が一種の緊張感と独特な心地よさを感じさせる一篇で短編ながらも「作品世界と一体になった錯覚」を与える読後感をもたらします。
本作に登場するのは「ロクジロウ」と名付けられたC62、「ゴイチロウ」ことD51、「ゴシチロウ」ことC57、そして「ゴジロウジュニア」としてC52が登場します。
・・・ここまで読んで「あれっ?」と思ったSLファンは多かったのではないかと。

そう、この中でC52は20世紀末どころか昭和20年代に全機廃車になって保存機すら残されなかった「存在しない機関車」なのです。
作者もそれに気づいたのか作中ではC52の描写は殆ど(と言うか全く)ありません。
「ただ出ているだけ」と言う随分な扱いだったりします。本作の主人公がD52に因んだ「五二郎」と言う老人なのでそこにひっかけただけと言うのが正直なところだったのではないかと思います。
まあ物がSFだから「C52が残っていたパラレルワールド」という事でもいいかと思います。
ですが、私が読んだ感じから言うならC52こそ本作の作品世界に一番似合う外見の蒸機だったと思います。
C52のNゲージモデルはマイクロエースから16番モデルもしなのマイクロと天賞堂から出ていてその魅力については私もこのブログで何度か語った事があります。
C52は日本最後の輸入蒸気機関車としてアメリカで作られた8200という3シリンダ機をベースに後の瀬野八入線に合わせて補機に対応した改造を施された物です。
元々は国産3シリンダ機製造のためのサンプルの色彩が強く(これを基に生まれたのがC53)8200として脚光を浴びたのもわずかな期間。
C52に改造されてからの晩年は瀬野~八本松間で「峠の後押し」ばかりやらされていたのでファン以外の人には目に触れにくい機関車でした。
そのせいか大概の蒸気機関車本では非常に影の薄い扱いを受けている悲劇のロコでもあります。
「元の8200蒸機の優美なボディを瀬野八対応の改造工事で醜くされた」とか悪評も多いC52ですが、その改造による独特の凄味のある異形感は優美さとは真逆の魅力を湛えています。
例えるならば「走るサイバーパンク」「蒸気で動くモビルスーツ」という趣でしょうか。とにかく停まっていてもパワフルさを感じさせる凄みがあるのです。
私個人の感想では「日本にこんなかっこいい蒸気機関車があったのか!!」と言うカルチャーショックを与えてくれたのがこのC52です。
大体、「ミサイルが飛び交い沿線の高層ビルに次々着弾する品川の旧東海道線を破片をかいくぐりつつ子供たちを乗せた無蓋車を牽きながら爆走する蒸気機関車」なんてシチュエーション、C57とかD51よりもC52の方がぴったりくると思うのですが…
「このロクジロウは、自分で食ってたもので、自分で馬力を出し、自分で走る。しかし、こいつの食い物はわしが食わせてやる。わしはできるだけ良質の石炭を、うまいタイミングで食わしてやりこいつに最高の力が出せるように手伝ってやる。
そのわしをこいつは軽々と運んでくれる。これが人間と機械との本当の関係でないのかね。
最近じゃ都市帯じゃ、自動車道路まで手放しで走れる装置がついとるそうじゃないか。人間は中でテレビをみとるそうじゃないか。いったい、何を根拠に、そんなに機械を信用しとるのかね」
(光文社カッパノベルズ刊「急行出雲」所収「機関車、草原に」239Pより引用)
ここに書かれている蒸気機関車の魅力を私が気付いたのは本書を読んでだいぶ経ってからです。
そしていまこれを読み返して見て、現在のこの現状を引き比べる時、うすら寒い感じを受けるのは気のせいでしょうか。
本作はいわゆるミステリとは異なるジャンルに属するものですが、それでいてもっとも強烈な読後感を残す一篇です。
未読の方には是非お勧めしたいと思います。










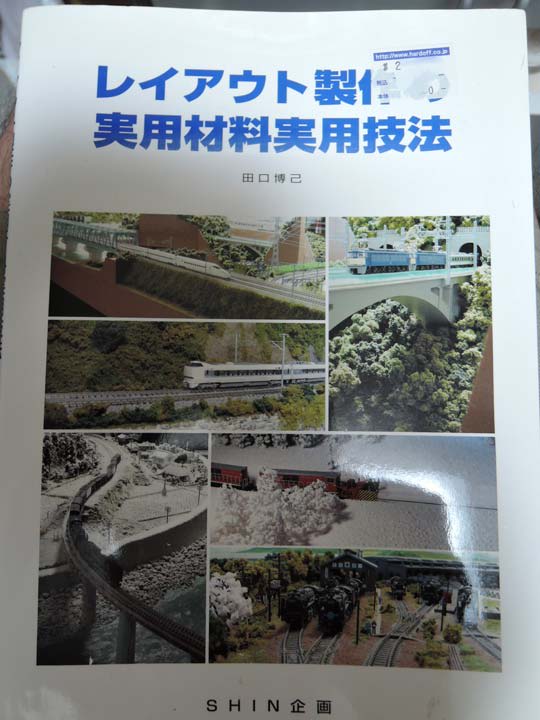










 しなのマイクロのクモユ141。例によってブラスボディの郵便電車です。
しなのマイクロのクモユ141。例によってブラスボディの郵便電車です。





























 今回は鉄道ミステリのアンソロジーのいくつかに所収のネタですが同じ題材が多い「新幹線ネタ」を纏めて紹介したいと思います。
今回は鉄道ミステリのアンソロジーのいくつかに所収のネタですが同じ題材が多い「新幹線ネタ」を纏めて紹介したいと思います。