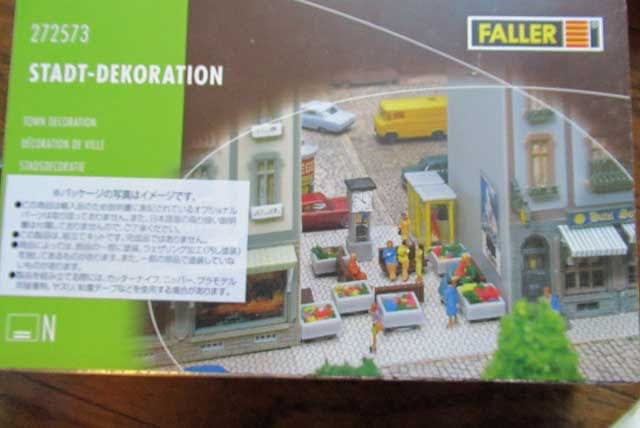先日触れたヤマナカ模型の最後の探訪の折に見つけたジャンクモデルから。

前に紹介しましたがRM MODELS出張版の「TEZMO SYNDOROME」は風奈をはじめとする面々がヤマナカ模型を訪ねてジャンク品を買い込む話があります。
その冒頭で「ショーウィンドウにカツミのEB58の出物が5両も並んでいる」のに風奈が驚く場面がありました。NゲージだけでなくHOのアイテムにも厚いあのショップならではの光景だったのですが、今回の探訪ではEB58の代わりにエンドウのEB66が1両だけ置いてありました。
EF66のショーティについては以前同じエンドウのED66の仕様を入線させていたのですが、手持ちにあるカツミの2軸客車と組み合わせるならEBの方が相応しい(ED66についてはボギーの中型客車が入線していますし)と思えました。

加えて、ヤマナカさんでの最後の買い物としてはこのモデルが最も相応しい気もして購入を決断しました。
今回のモデルは奥の相場と比べても安価な方なのですが、その理由が「前ユーザーによってリペイントされている」からだそうで、なるほど帯はやや細めで全面のアイボリーも彩度がやや強めに感じられます。
こういうところも「ヤマナカさんで買う模型らしい」という気がしました(笑)

走行性はこれまで入線させているHOのショーティの中では可もなく不可もなし。
試走時に店員さんが「こんな感じでいいですかね?」と恐る恐る尋ねて来ましたが、最新のモデルならともかく、50年以上前のHOだったら走りは大概こんなものですし、もし多少引っかかってもモーターマウント位置の微調整が容易なので多少は改善の余地はあります。

ともあれ、ヤマナカ模型最後の買い物はそれに相応しい思い出を作れるモデルが選べたと思います。

前に紹介しましたがRM MODELS出張版の「TEZMO SYNDOROME」は風奈をはじめとする面々がヤマナカ模型を訪ねてジャンク品を買い込む話があります。
その冒頭で「ショーウィンドウにカツミのEB58の出物が5両も並んでいる」のに風奈が驚く場面がありました。NゲージだけでなくHOのアイテムにも厚いあのショップならではの光景だったのですが、今回の探訪ではEB58の代わりにエンドウのEB66が1両だけ置いてありました。
EF66のショーティについては以前同じエンドウのED66の仕様を入線させていたのですが、手持ちにあるカツミの2軸客車と組み合わせるならEBの方が相応しい(ED66についてはボギーの中型客車が入線していますし)と思えました。

加えて、ヤマナカさんでの最後の買い物としてはこのモデルが最も相応しい気もして購入を決断しました。
今回のモデルは奥の相場と比べても安価な方なのですが、その理由が「前ユーザーによってリペイントされている」からだそうで、なるほど帯はやや細めで全面のアイボリーも彩度がやや強めに感じられます。
こういうところも「ヤマナカさんで買う模型らしい」という気がしました(笑)

走行性はこれまで入線させているHOのショーティの中では可もなく不可もなし。
試走時に店員さんが「こんな感じでいいですかね?」と恐る恐る尋ねて来ましたが、最新のモデルならともかく、50年以上前のHOだったら走りは大概こんなものですし、もし多少引っかかってもモーターマウント位置の微調整が容易なので多少は改善の余地はあります。

ともあれ、ヤマナカ模型最後の買い物はそれに相応しい思い出を作れるモデルが選べたと思います。