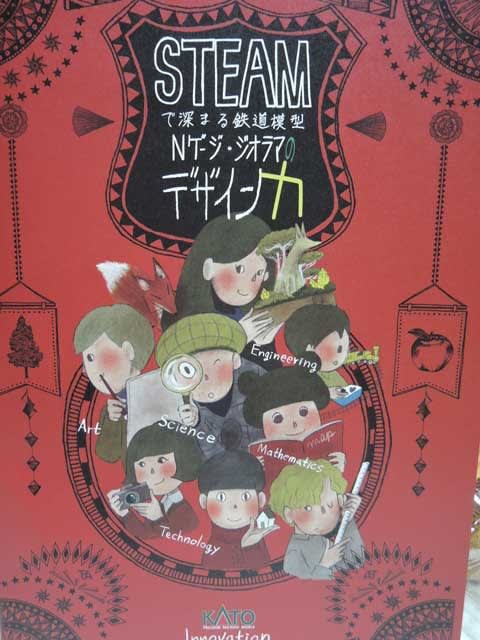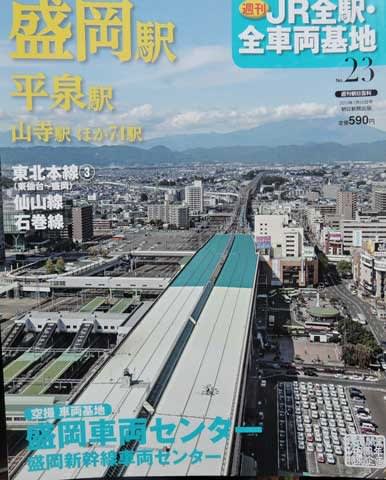帰省の折に古本屋に立ち寄る行為は、ここ20年くらい帰省時の習慣と化しているのですが(汗)最近はわたしの故郷の様な田舎でも、古本屋で鉄道模型を扱うことも増えましたから拾いものを得ることも増えました。
ですが、古本屋で買う物といえばやっぱり本な訳です。
同じ古本でも、故郷で買うのと東京とか現住地の古本屋で買って自宅で読むのとは、やっぱり気分が違う。
用事を済ませて寝床に入った時の寝酒がわり、時期によっては「帰りの新幹線の車中で読み通す」為の古本である事が多く、そこで読んだ古本類が「帰省の思い出の一部」として心に残るものです。

ですから故郷では、普段現住地で拾わない題材の一冊に手を出す事も多くなります。
今回拾ったのは「別冊太陽・蒸気機関車の旅」(平凡社)
1972年の5号ですから、かつての蒸気機関車(SL)ブーム真っ盛りの時期の出版です。
「別冊太陽」といえば我が国最初のビジュアルマガジンとして知られています。毎号テーマを変えて、1ページ大か見開きのグラビアとともに紀行文や随筆を並べた構成で「昼下がりにこれを眺めているだけで一瞬セレブみたいな優雅な気分にさせてくれる」不思議なステイタス性があります。
実はわたしの実家にも地域柄「宮沢賢治」「石川啄木」の2冊があるので帰省のたびに目を通す事もあったのですが、鉄道ネタがあることにはなかなか思い至りませんでした(大汗)
故郷の古本屋(というかカラ●ツト●インですが)にこれがあったのも何かの縁でしょう。お値段も古さを反映して一冊110円でしたし。
実家の布団の中でこれを読んでいると、他の「別冊太陽」を読んでいる時と同様に、何だか優雅な気分になります。
高井有一、加藤秀俊、古井由吉の随筆、山口瞳と高橋義孝の「鉄道対談」滝田ゆうの漫画を中心に根室から指宿までの「SL乗り継ぎ日本縦断旅行」が描かれていますが、専門誌のようなマニアックさはない代わりに、専ら読む側の情緒に訴えかける構成で肩肘張らずに読める所が専門書と違うところ。
厳冬期の北海道から始まり東北の五能線、羽越本線、飯山線を通って長野へ、京都から岡山、伯備線を米子へ向かい山陰線で下関へ、門司から都城を経由して指宿へ抜けるルートは意図的にか、当時蒸機がそういうところばかり走っていたからからなのか「絵に描いたようなローカル風景」が連続しますが、そういう風景に蒸機がまたよく似合います(というか、写真映えする)
他の題材でも言えますが、こういう雰囲気作りがこの雑誌の真骨頂なのでしょう。
いくつか通して読んでいると「いい意味で」心地よい眠気に誘われるご利益もあります。
とはいえ、古来文学者に鉄道マニアやファンが多かった歴史もあって見当外れも目立たず、その意味でも安心できる一冊と言えます。

あと、余談ながら1972年という時期から「40年前のグラビア広告」が意外な拾い物。
「ブルーバードU」と呼ばれていた頃の610、まだ健在だった頃のPAN AM、バリバリの新製品だった頃の「ヤクルトジョア」今では一般紙での 広告そのものが見られないであろう「ナショナルストロボ」などなど。
雑誌というのは書籍とは比べものにならないくらいに時代を強く反映する書物である事を実感します。