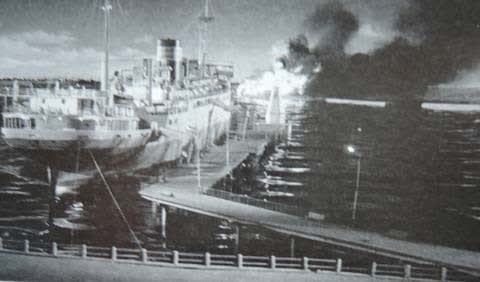今月はTOMIXのDD13、C11がリリースされていますが、先日はKATOもC11をリリース、またDD13の後期型も昨年夏頃にKATOが出していて、私も今年の元日に入線させています。
こんな風にごく接近した時期に同じ形式のモデルが複数のメーカーから相次いでリリースされるというのは昔を知るものからすればすごい時代になったものだと思います。
鉄道模型、それもプラの量産品となると企画から発売までの期間が比較的長いことが多いですから、概ね1年から半年以内に同一形式のモデル化が出れば、ほぼガチンコ勝負的な競作状態と言っても良いのではないかと思います。
私がこの趣味を始めた頃は年にふたつか三つくらい新製品が出れば御の字みたいなところがありましたが。
さて、それではNゲージの量産品で同一形式の競作が始まったのはいつ頃のことでしょうか。

上述の基準をもとに思い出してみると、私が知る限りでは1976年頃にタキ3000がナインスケールと関水金属でぶつかったのが最初ではないかと思います。
このタキ3000、片やKATOの細密化の礎を築いた記念碑的なモデル、片や香港製のトミー初のボギー車と言う物でしたが、関水の奴は細密感は見事ながら1両がブルトレ20系と同額の800円。
一方のトミー製はややラフな造形で手すりなどがないタイプだったとはいえ1両450円と価格と出来の点で結構棲み分けがしやすいラインナップだったと思います。
とはいえ、トミーと関水のタキを混結射せるのは結構つらい物がありました。当時の私の財政事情だと関水1両に付きトミーが2両くらいの比率で増備した記憶があります(笑)

ついで有名なのが昭和54~55年にかけてTOMIXとエーダイが激突したキハ58系が印象に残ります。
それまでキハ20系と82系(どちらもKATO)しかディーゼルカーのラインナップがなかった空白区に投入されただけに、どちらもメーカーのイメージシンボル的な意味合いの強い気合いの入ったモデルでした。
TOMIXとエーダイのどちらにするか悩んだユーザーは結構いたのではないかと思います。現に中古ショップを眺めているとどちらの58もそれなりの数の出物を見かけますから当時普及していたのは間違いありません。
やや搦め手ですが西武のレッドアローもTOMIXが完成品、GMがキットという形でほぼ同時期のリリースだったと記憶しています。
変わり種では阪急6300系がKATOがセミキット、エンドウとしなのマイクロがどちらもブラス車体モデルで競作というケースもありました。
後にも先にも「ブラスモデルのNゲージ完成品の競作」というのはなかったのではないでしょうか。
Nゲージの勃興期という時期もあったのでしょう。あの頃は競作と言っても片方が安かったり、片方がキットだったりとユーザーの選択肢としてわかりやすい形でリリースされていましたから自分のライフスタイルにあった(笑)選択がしやすかったと思います。
そうそう、この頃は24系ブルトレで「TOMIXがプラ、エンドウがブラス」という組み合わせもありました。
それが「同一形式仕様も価格もほぼ同じ」という形で激突するようになった嚆矢はEF65 1100番台とEF58だったのではないかと思います。
前者はブルトレブームに乗るという追い風の中で24系25型と同時期にKATO、TOMIX、エーダイの3社激突、後者はEF58ブームの中でKATO、TOMIXの激突という形で進行しました(おかげで2,3年は先行していたエンドウ製品の影が一気に薄くなってしまうというおまけつき)

モデルのリリースのペースが落ち着き、メーカーも淘汰と寡占化が進んだ90年代以降は競作もそれほど珍しくなくなりました。
それでも成田エキスプレスE253系辺りではTOMIXのHGに近い細密仕様とKATOのあっさりしているが手慣れたモデル化という形で棲み分けがあった(最近のE259系では逆にKATOの方がカプラーなどに工夫を凝らした仕様でTOMIXに対抗しましたが)りしました。
ですが21世紀に入ると価格も仕様もほとんど同じレベルでの競作という形が増え、ユーザーを迷わせる事になります。
まあ、中にはAメーカーのリリースの少し前に駆け込み的に既存モデルの小改良レベルのロコをBメーカーが出したりする事もあるにはあるのですが。
今回はC11に少し先んじる形でDD13がKATO・TOMIXのほぼ同時期リリースを実現しましたが、実際入線させてみると「殆どクローン状態」と言って良いくらいに造形の差を感じません(もちろん重箱の隅的な間違い探しをやれば違いが分かるのでしょうが)
互いが競争する事で相互にスキルを上げてゆくのは製品の進歩にとって大事な事は、車とかビデオデッキなどで私も痛感したものですが「1・5卵性双生児(親が違うのでw)」みたいな競作状態にどれくらいの意味があるのかは正直わからない物があります。
せめてどちらかが細密度を落として安いとか、片方がセミコンバージョンキットだったりとかなら、楽しみの選択肢が増える意味で有難いのですが。
前にも書きましたが正月にKATOのDD13を買った時は物を前日に見つけていながら「でも春にTOMIXが似た様なのを出すしなあ」と一晩悩んだ(それも大晦日にw)ものです。
まあ、C11やDD13辺りなら同じ様なのが何両居ても困らないのでしょうが、これが「特定ナンバーの1両しかない機関車」なんかだったりすると厄介ですね。
今回の思い出ばなし、後半はほとんど愚痴になりました。