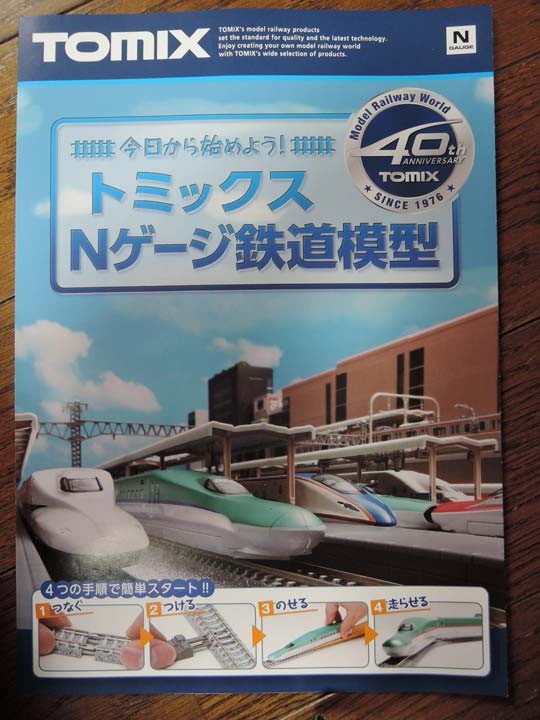「趣味とは手段が目的となる行為である」
これはあるオーディオ本で故長岡鉄夫氏が書いた言葉です。
今回はまさにそれを地で行く考察をば。
IMG_0587-photo.jpg
S660に乗り始めて三ヶ月。
先日ついに走行距離3000キロの大台に乗せました。
休日しか乗らないクルマですから当然それなりに一度に長い距離を走りまわる訳ですが、そこである事に気付きました。
これまで結構な遠出を何度もやっているにも拘らず、S660のドライブで「目的地でやった事があまりに少ない、又は目的地に長時間滞在していない」のです。
例えばある峠道の往還では「目的地の道の駅でカレーパンを一個食べただけ」
東京に行ったときなど「日劇でシン ゴジラを観ただけ」
清水まで行った時などは実質の滞在時間が20分。
もう観光もへったくれもない訳です。
これはいったいどうしたことか。
これがエスクァイアだったら多分それなりに買い物のひとつもやるとか、それなりの見物でもやるのが普通です。
S660の場合、目的地まで行っても「そこで何かしようという気にあまりならないのです」
クルマで遠出をするからには、目的地で何かする事を考えるのは当然の話なのにS660の場合はそうならない。
むしろ目的地に居ても「帰り道はどこをどう走ろうか」てな事ばかり頭に浮かぶのです。
つまり、スポーツカーというクルマの本質が「目的地で何かする事」ではなく「走るために走る」或いは本来労働な筈の「目的地までの過程を楽しむ」事にある事に気付かされるわけです。
正にこれは「目的と手段の逆転」と言えます。
ですからこれまでS660であちこち出掛けていて、このクルマの最大の弱点な筈の「荷物が載らない」事をハンデとして認識しないのです。
これは結構な発見でした。
運転そのものを楽しむために特化したクルマにはそういう側面があるという事なのでしょう。
元々ヒトと荷物を遠くまで運ぶというのが道具としてのクルマの本質ですし、事実そうした事に特化したミニバンやトールワゴンが売れるのは当然です。
ですがそれと何から何まで逆の作られ方をしているS660は道具クルマにない清々しさがあるのも確かです。
さて、ここまではクルマを例えに持ってきた訳ですが、では鉄道模型はどうなのか。
例えば車両の工作を例にとって見ましょう。
キットメイクにしろフルスクラッチにしろ車両を作る目的は基本的に「完成した車両をわがものにする事」にあります。
この時点でこれは趣味の一部と言えますが「目的」である事にも間違いはありません。
ではそこに至る「工作」という過程は楽しみではないのかというとそんな事はない訳です。
上手い下手は置いておいても自分の車両を作るというプロセスはそれ自体が結構な楽しみと言えます。
してみると目的も趣味なら過程も趣味という点で鉄道模型(或いは工作を伴う趣味の全般は)道楽の究極と言えない事もありません。
これはレイアウトの工作についても同じ事です。
そう思うと「ただ買うだけ」「ただ集めるだけ」というのは趣味の魅力の半分もない事になります(結構強引な結論ですが)
水野良太郎氏の著書の中であるドイツ人の知り合いがこんな事を言っていたとあります。
「単なるコレクターと鉄道模型のファンとは区別すべきだ。全く異質のものだというのが私の考えだ」
最初、これを読んだ時には少し違和感を感じたものですがS660に乗り始めてみると少しその意味がわかってきた様な気がします。
これはあるオーディオ本で故長岡鉄夫氏が書いた言葉です。
今回はまさにそれを地で行く考察をば。
IMG_0587-photo.jpg
S660に乗り始めて三ヶ月。
先日ついに走行距離3000キロの大台に乗せました。
休日しか乗らないクルマですから当然それなりに一度に長い距離を走りまわる訳ですが、そこである事に気付きました。
これまで結構な遠出を何度もやっているにも拘らず、S660のドライブで「目的地でやった事があまりに少ない、又は目的地に長時間滞在していない」のです。
例えばある峠道の往還では「目的地の道の駅でカレーパンを一個食べただけ」
東京に行ったときなど「日劇でシン ゴジラを観ただけ」
清水まで行った時などは実質の滞在時間が20分。
もう観光もへったくれもない訳です。
これはいったいどうしたことか。
これがエスクァイアだったら多分それなりに買い物のひとつもやるとか、それなりの見物でもやるのが普通です。
S660の場合、目的地まで行っても「そこで何かしようという気にあまりならないのです」
クルマで遠出をするからには、目的地で何かする事を考えるのは当然の話なのにS660の場合はそうならない。
むしろ目的地に居ても「帰り道はどこをどう走ろうか」てな事ばかり頭に浮かぶのです。
つまり、スポーツカーというクルマの本質が「目的地で何かする事」ではなく「走るために走る」或いは本来労働な筈の「目的地までの過程を楽しむ」事にある事に気付かされるわけです。
正にこれは「目的と手段の逆転」と言えます。
ですからこれまでS660であちこち出掛けていて、このクルマの最大の弱点な筈の「荷物が載らない」事をハンデとして認識しないのです。
これは結構な発見でした。
運転そのものを楽しむために特化したクルマにはそういう側面があるという事なのでしょう。
元々ヒトと荷物を遠くまで運ぶというのが道具としてのクルマの本質ですし、事実そうした事に特化したミニバンやトールワゴンが売れるのは当然です。
ですがそれと何から何まで逆の作られ方をしているS660は道具クルマにない清々しさがあるのも確かです。
さて、ここまではクルマを例えに持ってきた訳ですが、では鉄道模型はどうなのか。
例えば車両の工作を例にとって見ましょう。
キットメイクにしろフルスクラッチにしろ車両を作る目的は基本的に「完成した車両をわがものにする事」にあります。
この時点でこれは趣味の一部と言えますが「目的」である事にも間違いはありません。
ではそこに至る「工作」という過程は楽しみではないのかというとそんな事はない訳です。
上手い下手は置いておいても自分の車両を作るというプロセスはそれ自体が結構な楽しみと言えます。
してみると目的も趣味なら過程も趣味という点で鉄道模型(或いは工作を伴う趣味の全般は)道楽の究極と言えない事もありません。
これはレイアウトの工作についても同じ事です。
そう思うと「ただ買うだけ」「ただ集めるだけ」というのは趣味の魅力の半分もない事になります(結構強引な結論ですが)
水野良太郎氏の著書の中であるドイツ人の知り合いがこんな事を言っていたとあります。
「単なるコレクターと鉄道模型のファンとは区別すべきだ。全く異質のものだというのが私の考えだ」
最初、これを読んだ時には少し違和感を感じたものですがS660に乗り始めてみると少しその意味がわかってきた様な気がします。


















 照明効果と言いますかこの種の博物館では意識的に電球色の灯りを使っていた事も効果的に感じました。
照明効果と言いますかこの種の博物館では意識的に電球色の灯りを使っていた事も効果的に感じました。