前回お話した学研の雑居ビルを早速作って見ました。

とか偉そうに書きましたがこのキット、みにちゅあーとと違って組みたて自体はものの5分もあれば出来上がってしまいます。
なにしろ「ただの箱」ですから(笑)

組み上がって見ると確かに単純で安直にすら見える書割です。
が、事前に思ったほどには悪い印象はありません。
もしこれが40年前のストラクチャーが少ない頃だったら私も評価しなかったと思うのですが、今の様にようやく日本型の建造物が充実してきたタイミングでならバリエーションのひとつとして評価できるのではないかと思います。
とはいえ流石にそのままではぱっとしないのでビルの屋上に手すりを追加して見るとこれだけで結構見栄えがします。
自転車屋の方はそのままですがこれも一階フロア部分の折り曲げに工夫がありそこそこ立体的に見えるようになっているので同時期のGMの商店と並べても見劣りしない感じです。

早速手持ちの建物を並べた一角にこっそり混ぜ込んでみました。
他のモデルに比べて建物の造りや素材、表現のギャップが大きいのでもっと違和感があるかと思ったのですが結構よく溶け込んでいる感じです。
してみるとジオコレやジオタウン等で種類が増えている今なら再評価できるかもしれません。

とはいえ、全ての建物をこのキットだけで賄うと相当に貧相な街並みになるのは必須ですからあくまでアクセント程度に使うのが無難でしょう。
ちょっとした加工や改造でかなり見栄えがする事もわかりましたし。


「レイアウト上の建物は一つでも種類の多いのが望ましく、特殊な場合を除いて同じ建物があちらこちらに目につくのは、どうしても興ざめするものです。そのためにも色々なタイプの建物が欲しくなります」
これは大昔のKATOのカタログにある一節ですが実際の街並みで同じ建物がいくつも並ぶというのは団地などを除けば殆どありませんから正にその通りです。
その意味ではこのペーパーキットの意義もそれなりにはあるのかもしれません。

とか偉そうに書きましたがこのキット、みにちゅあーとと違って組みたて自体はものの5分もあれば出来上がってしまいます。
なにしろ「ただの箱」ですから(笑)

組み上がって見ると確かに単純で安直にすら見える書割です。
が、事前に思ったほどには悪い印象はありません。
もしこれが40年前のストラクチャーが少ない頃だったら私も評価しなかったと思うのですが、今の様にようやく日本型の建造物が充実してきたタイミングでならバリエーションのひとつとして評価できるのではないかと思います。
とはいえ流石にそのままではぱっとしないのでビルの屋上に手すりを追加して見るとこれだけで結構見栄えがします。
自転車屋の方はそのままですがこれも一階フロア部分の折り曲げに工夫がありそこそこ立体的に見えるようになっているので同時期のGMの商店と並べても見劣りしない感じです。

早速手持ちの建物を並べた一角にこっそり混ぜ込んでみました。
他のモデルに比べて建物の造りや素材、表現のギャップが大きいのでもっと違和感があるかと思ったのですが結構よく溶け込んでいる感じです。
してみるとジオコレやジオタウン等で種類が増えている今なら再評価できるかもしれません。

とはいえ、全ての建物をこのキットだけで賄うと相当に貧相な街並みになるのは必須ですからあくまでアクセント程度に使うのが無難でしょう。
ちょっとした加工や改造でかなり見栄えがする事もわかりましたし。


「レイアウト上の建物は一つでも種類の多いのが望ましく、特殊な場合を除いて同じ建物があちらこちらに目につくのは、どうしても興ざめするものです。そのためにも色々なタイプの建物が欲しくなります」
これは大昔のKATOのカタログにある一節ですが実際の街並みで同じ建物がいくつも並ぶというのは団地などを除けば殆どありませんから正にその通りです。
その意味ではこのペーパーキットの意義もそれなりにはあるのかもしれません。




































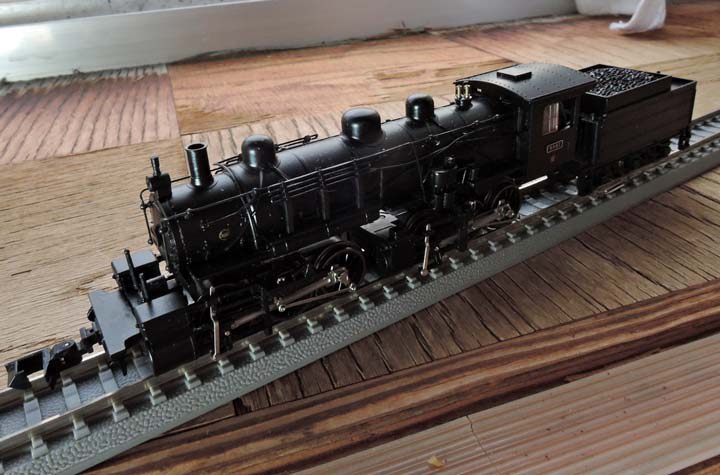
















































 当レイアウト開設この方、順調に保有量数を増やしている「偉大なる凡庸」の最右翼は何と言ってもED75とEF65といえます。
当レイアウト開設この方、順調に保有量数を増やしている「偉大なる凡庸」の最右翼は何と言ってもED75とEF65といえます。


