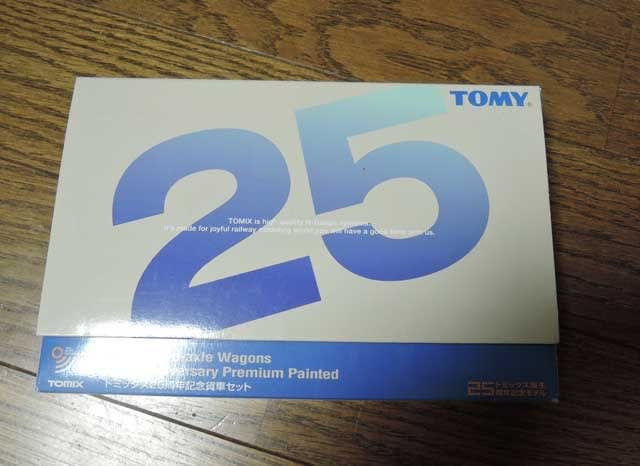先日ようやく入荷した新車です。

KATOのEF81 300番台、EF30に続くコルゲート電機の最新モデル。
EF81 300というと1970年代末、登場したてだったTOMIXのステイタスシンボルだったモデルでした。
以後、当のTOMIXでも順次バージョンアップやリニューアルが繰り返されている基幹モデルですが遅れてリリースされたKATOのEF81も造形のノリが微妙にTOMIXと異なるそうで独自にファンを持っていると聞きます。
入線したEF81ですが雰囲気は先日入線したEF30とほぼ同じボディの質感。全般に繊細な造形と感じます。
走行性についてはここ最近KATOの電機ばかり入線している事もあって、他のEF61や60とほぼ同じ印象。「スムーズで惰行もよく効く」というフレーズ、昨年来何度使って来たことやら(汗)
まあハズレにも当たっていませんし、走りに関してはそれだけ最近のKATOの品質管理がしっかりしていると解釈するのが良さそうです。
さて、当レイアウトにてレールクリーニングカーを押しているロコとしてTOMIXの初代EF81 300のモデルが存在します。
ジャンク入線だけにパンタも欠落しカプラーも片側欠損していますが重戦車系の走りは今も健在(笑)です。
この機会に比較できるところを今回のKATOの81と並べてみました。

実際やってみてまず驚いたのはTOMIXの方が若干ですが大きめだったこと。
上の写真では一見すると隣の側線にある機関車を並べている様な遠近感を感じますが、実はこれ同じ線路上で連結させた状態なのです。
これでは81同士の重連はできませんね(笑)

造形でもTOMIXのは初代81ならではの「黒いプラで表現された窓」「ステンレス製のスカート」などの個性溢れる特徴があるのを差し引かなければなりませんが、40年以上のジェネレーションギャップをモロに感じる部分はあります。
細密度及びEF30同様にステンレスの質感がよく出ている塗装は40年後に出たKATOの圧勝。それは走行性でも同様です。

こうして直接並べてみるとTOMIXの粗が目立つのですが、単体で線路に載っているとそう悪い印象は感じません(元々ジャンクですし)むしろ初めての機関車モデルゆえにKATOと異なる特徴をどう出そうかと試行錯誤した課程が透けて見える気がします。

KATOのEF81 300番台、EF30に続くコルゲート電機の最新モデル。
EF81 300というと1970年代末、登場したてだったTOMIXのステイタスシンボルだったモデルでした。
以後、当のTOMIXでも順次バージョンアップやリニューアルが繰り返されている基幹モデルですが遅れてリリースされたKATOのEF81も造形のノリが微妙にTOMIXと異なるそうで独自にファンを持っていると聞きます。
入線したEF81ですが雰囲気は先日入線したEF30とほぼ同じボディの質感。全般に繊細な造形と感じます。
走行性についてはここ最近KATOの電機ばかり入線している事もあって、他のEF61や60とほぼ同じ印象。「スムーズで惰行もよく効く」というフレーズ、昨年来何度使って来たことやら(汗)
まあハズレにも当たっていませんし、走りに関してはそれだけ最近のKATOの品質管理がしっかりしていると解釈するのが良さそうです。
さて、当レイアウトにてレールクリーニングカーを押しているロコとしてTOMIXの初代EF81 300のモデルが存在します。
ジャンク入線だけにパンタも欠落しカプラーも片側欠損していますが重戦車系の走りは今も健在(笑)です。
この機会に比較できるところを今回のKATOの81と並べてみました。

実際やってみてまず驚いたのはTOMIXの方が若干ですが大きめだったこと。
上の写真では一見すると隣の側線にある機関車を並べている様な遠近感を感じますが、実はこれ同じ線路上で連結させた状態なのです。
これでは81同士の重連はできませんね(笑)

造形でもTOMIXのは初代81ならではの「黒いプラで表現された窓」「ステンレス製のスカート」などの個性溢れる特徴があるのを差し引かなければなりませんが、40年以上のジェネレーションギャップをモロに感じる部分はあります。
細密度及びEF30同様にステンレスの質感がよく出ている塗装は40年後に出たKATOの圧勝。それは走行性でも同様です。

こうして直接並べてみるとTOMIXの粗が目立つのですが、単体で線路に載っているとそう悪い印象は感じません(元々ジャンクですし)むしろ初めての機関車モデルゆえにKATOと異なる特徴をどう出そうかと試行錯誤した課程が透けて見える気がします。