

先日の「小説伝」に続きレイアウトがらみの小説ネタです(写真は本編とまったく関係ありません)
今回は幸田露伴の「観画談」
これは青空文庫で読む事が可能ですが、姉妹編の「幻談」と併せた文庫が岩波から出ています。
物語は東北のある荒れ寺を舞台に、たまたま湯治に訪れた神経衰弱の苦学生(と言っても結構な歳なのですが)がある嵐の夜にそこに飾られていた一幅の画に心打たれる話。と言えばそれまでなのですがその絵の描写たるや、
一部を引用すると

画は美わしい大江(たいこう)に臨んだ富麗の都の一部を描いたものであった。
図の上半部を成している江の彼方には翠色(すいしょく)悦ぶべき遠山が見えている、
その手前には丘陵が起伏している、
その間に層塔(そうとう)もあれば高閤(こうこう)もあり、
黒ずんだ欝樹(うつじゅ)が蔽(おお)うた岨(そば)もあれば、明るい花に埋められた谷もあって、
それからずっと岸の方は平らに開けて、酒楼の綺麗なのも幾戸かあり、

士女老幼、騎馬の人、閑歩(かんぽ)の人、生計にいそしんでいる負販(ふはん)の人、種雑多の人が蟻ほどに小さく見えている。
筆はただ心持で動いているだけで、勿論その委曲が画けている訳ではないが、それでもおのずからに各人の姿態や心情がおもい知られる。
酒楼の下の岸には画舫(がほう)もある、舫中の人などはごま粒ほどであるが、やはり様子が分明に見える。

大江の上には帆走っているやや大きい船もあれば、ささの葉形の漁舟もあって、漁人の釣しているらしい様子もわかる。
光を移してこちらの岸を見ると、こちらの右の方には大きな宮殿様の建物があって、玉樹花(ぎょくじゅきか)とでもいいたい美しい樹や花が点綴(てんてい)してあり、
殿下の庭様のところには朱欄曲(しゅらんきょくきょく)と地を画して、欄中には奇石もあれば立派な園花もあり、人の愛観を待つさまざまの美しい鳥などもいる。
段と左へ燈光(ともしび)を移すと、大中小それぞれの民家があり、
老人や若いものや、蔬菜(そさい)を荷っているものもあれば、
蓋(かさ)を張らせて威張(いば)って馬に乗っている官人のようなものもあり、
はだしで柳条(りゅうじょう)に魚の鰓(あぎと)を穿(うが)った奴をぶらさげて川から上って来たらしい漁夫もあり、
柳がところどころに翠烟(すいえん)を罩(こ)めている美しい道路を、士農工商樵漁(しょうぎょ)、あらゆる階級の人が右徃左徃(うおうさおう)している。
綺錦(ききん)の人もあれば襤褸(らんる)の人もある、冠(かぶ)りものをしているのもあれば露頂(ろちょう)のものもある。
左の方へ行くと、江岸がなだらになって川柳が扶疎(ふそ)としており、雑樹(ぞうき)がもさもさとなっているその末には蘆荻(ろてき)が茂っている。
柳の枝や蘆荻の中には風が柔らかに吹いている。蘆のきれ目には春の水が光っていて、そこに一艘の小舟が揺れながら浮いている。船はあじろを編んで日除け兼雨除けというようなものを胴の間にしつらってある。
何やらこんろだの皿だのの家具も少し見えている。船頭のじいさんは艫(とも)の方に立上って、かしぐいに片手をかけて今や舟を出そうとしていながら、片手を挙げて、乗らないか乗らないかといって人を呼んでいる。
その顔がハッキリ分らないから、大噐氏はともしびを段と近づけた。
遠いところから段と歩み近づいて行くと段と人顔(ひとがお)が分って来るように、朦朧(もうろう)たる船頭の顔は段と分って来た。膝ッぷしもひじもムキ出しになっている絆纏(はんてん)みたようなものを着て、極小さな笠を冠(かぶ)って、やや仰いでいる様子は何ともいえない無邪気なもので、寒山(かんざん)か拾得(じっとく)の叔父さん
(以下略)
といった具合のパノラマ画なのでした。
(文章は一部簡略化しました)
主人公がこの画のどこに心打たれたか、そしてその後どうなったのかは実際に読んで頂いた方が良さそうなので割愛しますが、私が最初これを読んだ時は最初のレイアウトを作り始めて半年位のタイミングでしたので
「これは読むレイアウトではないか」というのが先ず第一印象でした。
とは言っても鉄道の「て」の字も出てこない話なのですが(汗)
そして後から読み返してみてもこの印象は変わりませんでした。
絵巻の中の風景描写はまさに活字のパノラマとも言うべきものでそれもただの風景でなくその中に生きる人々の生き生きとした様までもが読むほどに目に浮かんできます。船頭が人を呼ぶ様の所などはまさにレイアウトのミニシーンに通じる物があります。
そしてそれらの様々の小さなシーンが総合して一幅の画として読む物の心に展開してきます。
この感覚はまさに活字ならではのイマジネーションではありますが、これを立体化できないかという誘惑にも駆られます。レイアウトというのは正にそうした表現には好適ではないでしょうか。

これを読んでいるとレイアウト作りにはこうした文学的素養の様なものも必要かもしれないと思えます。
その目で見ると或いはこの種の「読むレイアウト」文学というのは案外あるかもしれません。
余談ですが幸田露伴は教科書的には「五重塔」で有名ですが、私個人は本編の姉妹編の「幻談」も私の好みです。
こちらはやや怪談仕立てになっていますが「趣味人」のひとつの行き方の手本の様なものをさらりと描いています。こちらの主題は釣りで、私自身は釣りをやらないのですが釣好きの方ならもっと味わい深く楽しめるのではないかと思います。
さて七面倒くさい話ばかりでしたのでここらで最近上げた動画をひとつ。
<object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/0UT-iKJjSh8?version=3&hl=ja_JP"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/0UT-iKJjSh8?version=3&hl=ja_JP" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="349" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>
昨年の年越し運転からの一こまです。
まさかメーカー違いでキハ35系が4編成も揃う事になるとは思いませんでした。
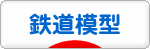 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
現在参加中です。気に入ったり参考になったらクリックをお願いします。





























































