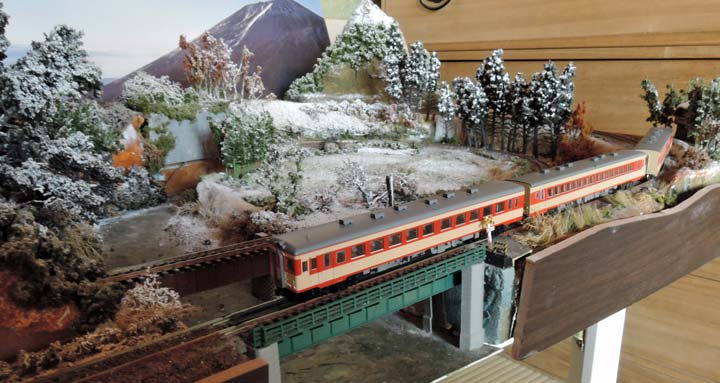そろそろグランシップに向けての準備も佳境だったころのはなしです。
平日休の午前中をモジュールの改修に費やしていたので午後は気分転換でふたつきぶりくらいに近所のハード●フを回りました。
・・・って、ハード●フが気分転換になる様な休日って一体(汗)

そこで手に入れた物というのがストラクチャー用のジャンクパーツ
これだけで54円でした(笑)
車両パーツでもそうなのですが、この種のジャンク袋というのは時としてワクワクさせてくれる事があります。
「今計画中のレイアウトでこのパーツはこう使えそう」とか買う前から想像する時がいちばんたのしいのかもしれません。
で買い込んできて自宅で開封すると実はそれらの中で本当に使えそうなのは二つか三つだったりする事実に愕然とするわけですが(汗)
でもこうしたワクワク感のある袋に当たると財布を開くのが止められないのも困ったものです。

今回のパーツの群れでお目当てだったのはGMのプラント工場用のパーツと思われるタンク類と一部配管。
これを何に使うかについてはいずれまた(但し工場ではありません)
前回、ジャンクパーツは都会の方が入手しやすいと書いたばかりでしたが、近場で手に入るならそれに越した事はないですね。
ただ、こんな機会がいつでもあるという訳にはいきませんし、改造素材になりそうなジャンク車両となると更に入手は難しいですが。
平日休の午前中をモジュールの改修に費やしていたので午後は気分転換でふたつきぶりくらいに近所のハード●フを回りました。
・・・って、ハード●フが気分転換になる様な休日って一体(汗)

そこで手に入れた物というのがストラクチャー用のジャンクパーツ
これだけで54円でした(笑)
車両パーツでもそうなのですが、この種のジャンク袋というのは時としてワクワクさせてくれる事があります。
「今計画中のレイアウトでこのパーツはこう使えそう」とか買う前から想像する時がいちばんたのしいのかもしれません。
で買い込んできて自宅で開封すると実はそれらの中で本当に使えそうなのは二つか三つだったりする事実に愕然とするわけですが(汗)
でもこうしたワクワク感のある袋に当たると財布を開くのが止められないのも困ったものです。

今回のパーツの群れでお目当てだったのはGMのプラント工場用のパーツと思われるタンク類と一部配管。
これを何に使うかについてはいずれまた(但し工場ではありません)
前回、ジャンクパーツは都会の方が入手しやすいと書いたばかりでしたが、近場で手に入るならそれに越した事はないですね。
ただ、こんな機会がいつでもあるという訳にはいきませんし、改造素材になりそうなジャンク車両となると更に入手は難しいですが。