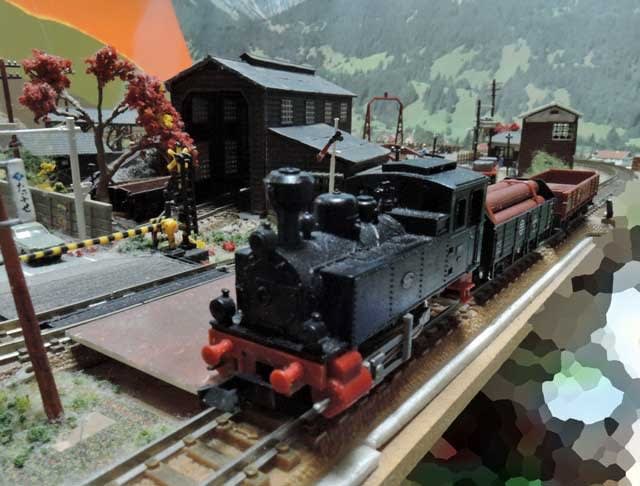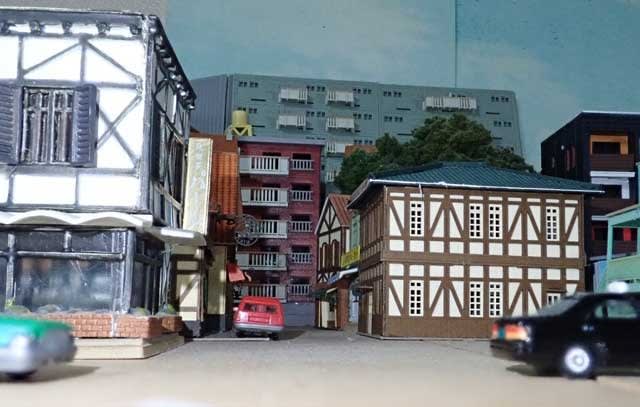自宅運転会富士急行編その3です。

これまで2回にわたってラッピング車の運行でしたが今回は昭和30年代以降の「ノーマルカラー(車種によってはリバイバルカラー)」の富士急電車で行きます。

1000系以前は富士急の主力だった5700形。
元は小田急の2200形だった通勤車です。
種車の違いで元2220の貫通扉付きと元2200の前面二枚窓の仕様が存在し、後者は事業者特注モデルでリリースされています。
(これを買ったときの騒ぎは一生忘れないだろうなあ汗)
因みに実車は引退後、甲府盆地を見下ろす某工場の敷地内に旧小田急塗装に復元されて保存されています。
甲府盆地と小田急塗装の組み合わせ、なんだか妙な感じもしますが。

元京王5000系の1000系リバイバルカラー。
これもイベントの限定品で最初にリリースされた鉄コレの「元5000系」モデルでもあります。通常品で5000系の譲渡車が出るのはこの少しあとだったのですが、このモデルを手にして「これなら京王仕様も期待できそうだ」と胸を躍らせたものです。
(でも実際はGMの京王5000系で満足してしまい、鉄コレオリジナルの京王5000系にはいまだに手を出せないでいるのですが)
こちらの編成は昨年の電車祭りの折、実車を見ています。

富士急オリジナルの3100形。
独特の湘南顔と伸びやかなフォルムが特徴の2扉車です。
この編成は2編成4両が存在していたのですがそのうちのひと編成が昭和46年に踏切衝突~暴走転落事故に巻き込まれて廃車になってしまいます。踏切でぶつかったトラックがたまたまブレーキ配管を直撃、破損したため列車がそのまま下り坂を暴走、急カーブで転覆してしまうという惨事でした。
(前回紹介の5000形は実質的な後継車の意味合いもあった様です。また5000系が当時としては異例な前突対策・ブレーキ保安装備を施されているのもその際の教訓があったのでしょう)
モデルは鉄コレ初期の20M車で当時の動力ユニットを使っていますが今でも元気に走ってくれます。
残り2両の実車はごく最近解体され残っていないとの由。

ブルーを基調とした富士急行の通常塗装(あるいは旧塗装)は夏場などに見るととても涼感があふれるカラーリングと思います。

これまで2回にわたってラッピング車の運行でしたが今回は昭和30年代以降の「ノーマルカラー(車種によってはリバイバルカラー)」の富士急電車で行きます。

1000系以前は富士急の主力だった5700形。
元は小田急の2200形だった通勤車です。
種車の違いで元2220の貫通扉付きと元2200の前面二枚窓の仕様が存在し、後者は事業者特注モデルでリリースされています。
(これを買ったときの騒ぎは一生忘れないだろうなあ汗)
因みに実車は引退後、甲府盆地を見下ろす某工場の敷地内に旧小田急塗装に復元されて保存されています。
甲府盆地と小田急塗装の組み合わせ、なんだか妙な感じもしますが。

元京王5000系の1000系リバイバルカラー。
これもイベントの限定品で最初にリリースされた鉄コレの「元5000系」モデルでもあります。通常品で5000系の譲渡車が出るのはこの少しあとだったのですが、このモデルを手にして「これなら京王仕様も期待できそうだ」と胸を躍らせたものです。
(でも実際はGMの京王5000系で満足してしまい、鉄コレオリジナルの京王5000系にはいまだに手を出せないでいるのですが)
こちらの編成は昨年の電車祭りの折、実車を見ています。

富士急オリジナルの3100形。
独特の湘南顔と伸びやかなフォルムが特徴の2扉車です。
この編成は2編成4両が存在していたのですがそのうちのひと編成が昭和46年に踏切衝突~暴走転落事故に巻き込まれて廃車になってしまいます。踏切でぶつかったトラックがたまたまブレーキ配管を直撃、破損したため列車がそのまま下り坂を暴走、急カーブで転覆してしまうという惨事でした。
(前回紹介の5000形は実質的な後継車の意味合いもあった様です。また5000系が当時としては異例な前突対策・ブレーキ保安装備を施されているのもその際の教訓があったのでしょう)
モデルは鉄コレ初期の20M車で当時の動力ユニットを使っていますが今でも元気に走ってくれます。
残り2両の実車はごく最近解体され残っていないとの由。

ブルーを基調とした富士急行の通常塗装(あるいは旧塗装)は夏場などに見るととても涼感があふれるカラーリングと思います。