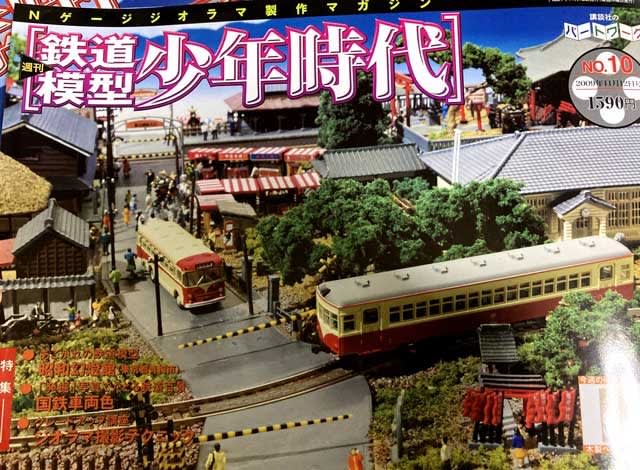今回は積みキットではなく、最近になって入手したモデルのキットメイク(要するに「素組み」)です。

物はワールド工芸のマルチマテリアルキットのひとつ「TMC400A」モーターカーです。
これの入手に際しては少なからず行きつけの店のご店主にお世話になりました。この場を借りてお礼を申し上げます(汗)
このタイプのABSとエッチングパーツの組み合わせのモデルは以前、弘南鉄道のED22 1を作った事があります。
プラの車体に手すり類をエッチングパーツで組み付ける事でオールプラのモデルよりも好ましい細密感を出せるモデルでした。
なので今回もそういうキットだろうと思った掛かったのですが、これが良くも悪くも大違いでした。
何しろエッチングパーツこそ一枚板に全パーツが収まっているのに、ここのパーツが小さくて細かい!
しかもそれらの手すり類を組み付けるには0・5ミリ径のドリル刃が必要ときます(汗)
なのでED22よりも小型の機関車でありながら以外に手こずる組み立てでした。
まあ、これは私の手が大きくて細かいパーツの取り付けに向いていないという事情も少なからず絡んでいます(大汗)

順番が前後しますが、カラーリングは特に実車のカラーに拘らず横須賀線アイボリーをベースに手すり類を白、下回りを黒で纏めました。
工程の煩雑さを防ぐために各パーツは前もって塗装してから組み立てています。今回はやっていないのですがボディにウエザリングをするなら組み立て前にやっておいた方がいい気がします。
車体が小型なので手すりなどを付けてからだとかなり手間取るのではないでしょうか?

ある程度形になって来ると、この種のモーターカー系の他社モデルに比べて相当な細密感があります。
なお、このキットは動力は既にシャシに組み込み済みなのは有難いポイントでした。
走りについては2軸の片側1軸にギアをつなげ、床下に鎮座したコアレスモーターで駆動する形式です。
これらの動力装置は床板と一体の構造で「モータも床下にぶら下げる」という昔のNゲージからすると想像もできない構造になっています。
動力の構造こそシンプルですがモータ自体がが小さいせいか、繊細なスローを効かせる走りは少し荷が重いようです。
同じコアレス仕様でもKATOのチビ電の様に大きなモーターであればもう少しスローは効くのでしょうが、今回のTMCは聊かラビットスタート気味で独楽鼠のような走りになりがちでした。
(但し動力の個体差でスムーズの走れるのもあるかもしれません)
ところで、このキットを組み立ててみてふと思った事があるのですがそれについては近いうちに。

物はワールド工芸のマルチマテリアルキットのひとつ「TMC400A」モーターカーです。
これの入手に際しては少なからず行きつけの店のご店主にお世話になりました。この場を借りてお礼を申し上げます(汗)
このタイプのABSとエッチングパーツの組み合わせのモデルは以前、弘南鉄道のED22 1を作った事があります。
プラの車体に手すり類をエッチングパーツで組み付ける事でオールプラのモデルよりも好ましい細密感を出せるモデルでした。
なので今回もそういうキットだろうと思った掛かったのですが、これが良くも悪くも大違いでした。
何しろエッチングパーツこそ一枚板に全パーツが収まっているのに、ここのパーツが小さくて細かい!
しかもそれらの手すり類を組み付けるには0・5ミリ径のドリル刃が必要ときます(汗)
なのでED22よりも小型の機関車でありながら以外に手こずる組み立てでした。
まあ、これは私の手が大きくて細かいパーツの取り付けに向いていないという事情も少なからず絡んでいます(大汗)

順番が前後しますが、カラーリングは特に実車のカラーに拘らず横須賀線アイボリーをベースに手すり類を白、下回りを黒で纏めました。
工程の煩雑さを防ぐために各パーツは前もって塗装してから組み立てています。今回はやっていないのですがボディにウエザリングをするなら組み立て前にやっておいた方がいい気がします。
車体が小型なので手すりなどを付けてからだとかなり手間取るのではないでしょうか?

ある程度形になって来ると、この種のモーターカー系の他社モデルに比べて相当な細密感があります。
なお、このキットは動力は既にシャシに組み込み済みなのは有難いポイントでした。
走りについては2軸の片側1軸にギアをつなげ、床下に鎮座したコアレスモーターで駆動する形式です。
これらの動力装置は床板と一体の構造で「モータも床下にぶら下げる」という昔のNゲージからすると想像もできない構造になっています。
動力の構造こそシンプルですがモータ自体がが小さいせいか、繊細なスローを効かせる走りは少し荷が重いようです。
同じコアレス仕様でもKATOのチビ電の様に大きなモーターであればもう少しスローは効くのでしょうが、今回のTMCは聊かラビットスタート気味で独楽鼠のような走りになりがちでした。
(但し動力の個体差でスムーズの走れるのもあるかもしれません)
ところで、このキットを組み立ててみてふと思った事があるのですがそれについては近いうちに。



















 かねて当ブログでも何度か書いていますが、鉄道模型の趣味には「モデラー」と「コレクター」という二つの方向性がありました。
かねて当ブログでも何度か書いていますが、鉄道模型の趣味には「モデラー」と「コレクター」という二つの方向性がありました。