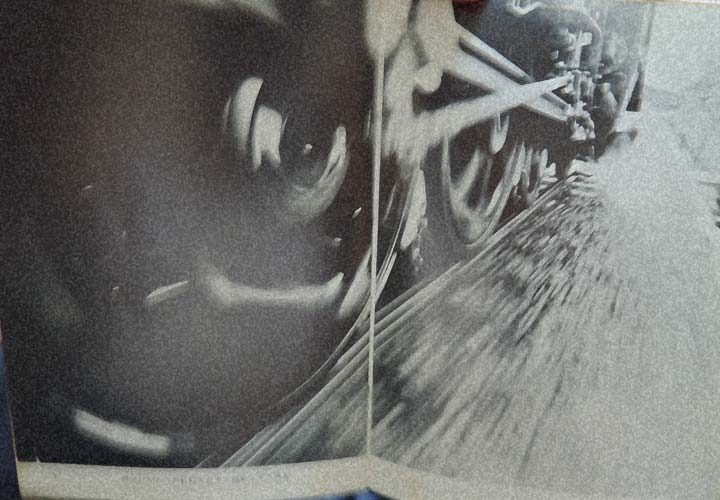ジオコレの交差点の建物から

3つ目のバリエーションは1階にコンビニを内蔵した3階建ての雑居ビル風です。
これも「どこにでもありそう」感が強い外見でどんな町並みにも似合う感じがします。
(私などはこれを見て思わず新宿西口の「ホビーランド●ち」の入ったビルを連想してしまいましたw)

さてこのビルの特徴は1回右端の部分。
2階へ上がる階段パーツがありますがここをジオコレで既出の「地下鉄入口」に差し替える事が出来るようになっています。
これが付くだけで「田舎にでもありそうな3階建ての角ビル」が「地下鉄のある大都会の一角のビル」にバージョンアップできるというご利益が(笑)

こちらも先日紹介の商社ビルと同様ガラスパーツを貼り付けても窓の「金壺眼」状態が目立つ欠点を持っています。
ですがその一方でこういう構造なのでユーザーによるリペイントが前より容易になっている点も見逃してはいけない気がします。
(初期のジオコレの建物はガラスを外すのが結構難儀でしたから汗)

最近のジオコレやジオタウンは路面電車やバスのモデルのリリースに伴い駅前と関係ない街並み創成用のアイテムが増えていますが今回でまたバリエーションが広がりました。
これまでGMやTOMIXの数種類しかバリエーションの無いビルを組み合わせただけではなかなか作りにくかった「都市風景のレイアウト」のハードルがここ10年くらいでかなり下がってきているのを実感します。

3つ目のバリエーションは1階にコンビニを内蔵した3階建ての雑居ビル風です。
これも「どこにでもありそう」感が強い外見でどんな町並みにも似合う感じがします。
(私などはこれを見て思わず新宿西口の「ホビーランド●ち」の入ったビルを連想してしまいましたw)

さてこのビルの特徴は1回右端の部分。
2階へ上がる階段パーツがありますがここをジオコレで既出の「地下鉄入口」に差し替える事が出来るようになっています。
これが付くだけで「田舎にでもありそうな3階建ての角ビル」が「地下鉄のある大都会の一角のビル」にバージョンアップできるというご利益が(笑)

こちらも先日紹介の商社ビルと同様ガラスパーツを貼り付けても窓の「金壺眼」状態が目立つ欠点を持っています。
ですがその一方でこういう構造なのでユーザーによるリペイントが前より容易になっている点も見逃してはいけない気がします。
(初期のジオコレの建物はガラスを外すのが結構難儀でしたから汗)

最近のジオコレやジオタウンは路面電車やバスのモデルのリリースに伴い駅前と関係ない街並み創成用のアイテムが増えていますが今回でまたバリエーションが広がりました。
これまでGMやTOMIXの数種類しかバリエーションの無いビルを組み合わせただけではなかなか作りにくかった「都市風景のレイアウト」のハードルがここ10年くらいでかなり下がってきているのを実感します。