JTBキャンブックスは時折古本の出物を見つける事がありますが、鉄道書籍自体の古本が少ない現住地や故郷にあってコンスタントに並んでいる事が多いシリーズです。

今回紹介するのは「私鉄機関車30年」
以前紹介している「ローカル私鉄30年」の姉妹書とでも言えます。
「ローカル私鉄?」の時もそうだったのですが、本自体の興味に加えて鉄コレの登場で「ガイドブック」としての性格も持つ様になりかなり重宝しそうな一冊と言えます。
実際、本書を開いて見るとここ数年鉄コレやワールド工芸などのキットでリリースされた機種も数多く掲載されていて、その意味でも役に立ちそうです。
が、本書の魅力は「旧国鉄の払い下げ機」「国鉄のそれとは異なるノリで作られた私鉄ならではの機種の持つ個性」「後の貨物事業の縮小や私鉄そのものの廃止、廃線に伴う機関車の流転の経歴」といった私鉄の機関車故の特徴が俯瞰できる点にもあります。
第3の特徴については鉄コレの機関車なんかが「同一機種の登場時と移籍後」を同時リリースしたりするので模型そのものが「鉄道図鑑」みたいなノリに近づいていますが、本書を併読すると各機種の経歴や特徴が鉄コレのパッケージ解説よりも詳しく書いているのでなかなか参考になったりします(笑)
ジャンルの俯瞰本としてもなかなか役立ちそうですし、少しの暇を見つけて1ページだけ斜め読みしていても楽しい一冊です。

今回紹介するのは「私鉄機関車30年」
以前紹介している「ローカル私鉄30年」の姉妹書とでも言えます。
「ローカル私鉄?」の時もそうだったのですが、本自体の興味に加えて鉄コレの登場で「ガイドブック」としての性格も持つ様になりかなり重宝しそうな一冊と言えます。
実際、本書を開いて見るとここ数年鉄コレやワールド工芸などのキットでリリースされた機種も数多く掲載されていて、その意味でも役に立ちそうです。
が、本書の魅力は「旧国鉄の払い下げ機」「国鉄のそれとは異なるノリで作られた私鉄ならではの機種の持つ個性」「後の貨物事業の縮小や私鉄そのものの廃止、廃線に伴う機関車の流転の経歴」といった私鉄の機関車故の特徴が俯瞰できる点にもあります。
第3の特徴については鉄コレの機関車なんかが「同一機種の登場時と移籍後」を同時リリースしたりするので模型そのものが「鉄道図鑑」みたいなノリに近づいていますが、本書を併読すると各機種の経歴や特徴が鉄コレのパッケージ解説よりも詳しく書いているのでなかなか参考になったりします(笑)
ジャンルの俯瞰本としてもなかなか役立ちそうですし、少しの暇を見つけて1ページだけ斜め読みしていても楽しい一冊です。
























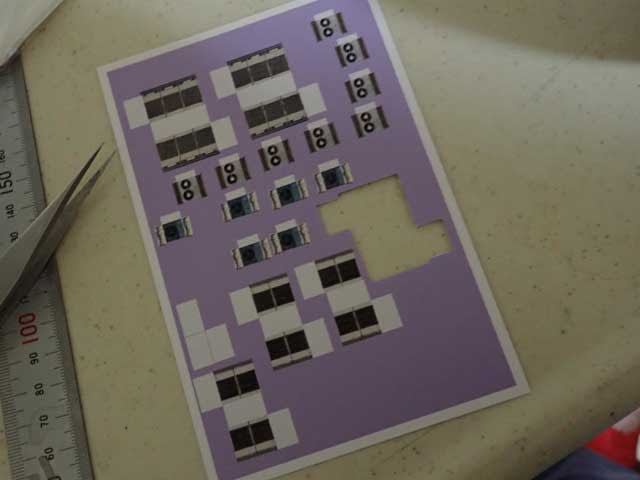




























 大概の場合、新車状態であっても線路とかパワーパックの相性などで走り味が変わる事がモデルによってはあるのですが、この四季島にはそれがほとんど感じられません。
大概の場合、新車状態であっても線路とかパワーパックの相性などで走り味が変わる事がモデルによってはあるのですが、この四季島にはそれがほとんど感じられません。



















