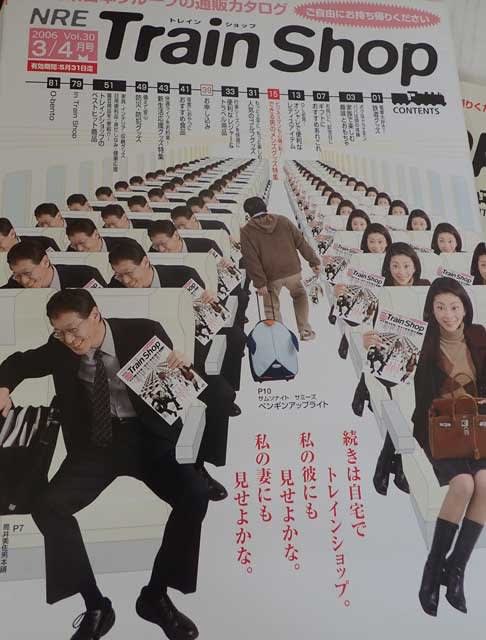昨日スタートしたTwitter上の「おうちでグランシップトレインフェスタ」、昨日来仕事の合間を見ながらチェックしているのですが予想通りと言いますか、参加者が思い思いに写真や動画をアップロードして一種仮想博覧会のノリになっています。

出展予定だった車両やレイアウトの片鱗を見られたでイベント中止の渇はそれなりに癒されましたし、各自が持ち寄った実車の写真を俯瞰で眺められたのは望外の収穫だったと思います(実際のイベントでこれだけの写真をゆっくり眺めるなんてのはできないですから)
私も協賛の意味で二本ばかり動画をアップロードさせていただきました。

それにしても
Twitter上のイベントとはいえ、各クラブ、各個人が一斉に思い思いの動画や画像、コメントなどを発信しているのはやはり壮観でした。
これらがスマホの小画面(いや、パソコンの大画面であっても)でなしにリアルなライブ参加だったらもっと楽しめた事でしょう。
これまでの出場経験から言っても書籍やビデオでは感じきれない、実物の模型を間近に眺め、その空気を共有するというライブ感覚はインドアが本質である鉄道模型の趣味であってもとても重要な事ではないかと思えます。

それに私にとってはこのイベントは「テツドウモケイを肴に多くの人と飲み明かせる」数少ない(というか唯一w)イベントでしたから、それが楽しめないのはやはり残念と言わざるを得ません。
次回こそは無事開催できますように。そして次回こそは飲み明かせますように(爆)
それまでは次回に備えてモジュールの改修と車両の工作に勤しんでいるとしましょう。

出展予定だった車両やレイアウトの片鱗を見られたでイベント中止の渇はそれなりに癒されましたし、各自が持ち寄った実車の写真を俯瞰で眺められたのは望外の収穫だったと思います(実際のイベントでこれだけの写真をゆっくり眺めるなんてのはできないですから)
私も協賛の意味で二本ばかり動画をアップロードさせていただきました。

それにしても
Twitter上のイベントとはいえ、各クラブ、各個人が一斉に思い思いの動画や画像、コメントなどを発信しているのはやはり壮観でした。
これらがスマホの小画面(いや、パソコンの大画面であっても)でなしにリアルなライブ参加だったらもっと楽しめた事でしょう。
これまでの出場経験から言っても書籍やビデオでは感じきれない、実物の模型を間近に眺め、その空気を共有するというライブ感覚はインドアが本質である鉄道模型の趣味であってもとても重要な事ではないかと思えます。

それに私にとってはこのイベントは「テツドウモケイを肴に多くの人と飲み明かせる」数少ない(というか唯一w)イベントでしたから、それが楽しめないのはやはり残念と言わざるを得ません。
次回こそは無事開催できますように。そして次回こそは飲み明かせますように(爆)
それまでは次回に備えてモジュールの改修と車両の工作に勤しんでいるとしましょう。