最近ウェブやブログのコメント、以前ならSNSのコミュニティなんかを見ていてふと思った事から。

鉄道模型、特にNゲージの場合に顕著ですがブランドの信者の軋轢という奴に当たる事があります。
特にKATO,TOMIX、マイクロエースの御三家の間で信者同士の熱いやりとりや論争などが特に多い様です。
前々から書いていますが、私自身は特定のブランドに肩入れする趣味がない、それどころか世間で誰が見ても駄作扱いするモデルでも結構喜んで入線させる事の方が多いのでこの手の論争に首を突っ込む事はあまりありません。
ですが自分の好きなブランドに肩入れする余り特定の他社を貶めたり中傷したりするのには少なからず不快感を覚えます。
書いている事のいくつかが正しいと思っていてもコメンターの物言いによっては反対したくなったりすらするので、随分と天の邪鬼な話ではあります。
この種の論争の根底にあるのは贔屓の引き倒しと先入観、自分の好きなブランドの対する冷静さを書いた過剰な思い入れがあるのでうっかり首を突っ込むと痛い目を見そうな側面もあります。
ですから、ここからは私自身の経験に基づいたはなしから。
この趣味を再開した当初は殆ど素人同然の所からの再スタートでしたので雑誌やネットからの情報からモデル選びをする事が多かったです。
その過程でとある特定ブランドのモデルの性能の悪さや造形の雑さについての悪評を随分と聞かされたものです。
私自身そうした評判を随分と参考にさせて頂きましたし、当初の段階ではそれに乗せられる形でそのブランドの製品を意識的に避けていたりもしました。

そんな折、SNSでもずいぶんと懇意にさせて頂きレイアウトビルダーとしてもなかなかの方だった方のブログでそのブランドのモデルを購入したという一文に当たりました。
その方はそのモデルの走行性については殆ど手放しに近い褒め方だったので、少なからず違和感を感じたものです。
何しろ当時そのブランドに肯定的な意見という物を殆ど見ていなかった事もあって、かなり眉唾な印象を持ちました。
が、それから暫くしてたまたま中古モデルでそのブランドの編成物を入線。
理由は「その編成のモデルがそこからしか出ていなかったから」という物もありましたが上述のブログの話も心のどこかに引っかかっていたのも事実です。
ですから試走時はどこかおっかなびっくりでまともに走らない覚悟だけは決めておりました(笑)
ですが私のレイアウト上ではその編成が結構するすると走りでしたのを見て「これなら許容範囲じゃん」と胸をなでおろした記憶があります。
確かに他社に比べると雑な構造の動力系はスムーズさや走行条件にシビアな点で噂通りだったのですが、それを持って全否定するほどの物ではなかったのです。

それ以降(主に中古モデルですが)そのブランドの車両を増備する上での心理的抵抗はかなり減りました。
確かに常識の範囲を超えてひどい物もあるにはあったのですが最初の予想よりは少ない物でした。
それどころかそうしたモデルに当たったのをきっかけに走行性改善のために動力をばらして再調整する事をためらわなくなったのが一番の収穫でした。
長い目で見るとこのブランドへの偏見を打破できた事で増備の対象が他社の旧モデルなんかにも広がりましたしかなりモデルライフが充実したのも確かです。
(一方で殆ど屑屋同然のラインナップにもなりましたが大汗)
この時の経験で私が覚えた事は「少なくとも趣味の世界では他人の褌で相撲を取る真似はしない方がいい」という事です。
もちろんモデル選びの上ではある程度、第三者の評価が大事なのは間違いありません。


ですが殊趣味にかかわる場合は、外野がどう騒ごうと選ぶのは結局自分自身ですから、最終的には借り物でない自分自身の感性をもう少し信じても良いのではないかと言う気もします。
それに買って後悔するにしてもその事で人を恨む必要がなくなりますし(汗)
個人的には車両に関する限りブランド性だけに頼る様な買い方はそれだけ自分の視野を狭めている様な気もします(これは鉄道模型に限らず他のジャンルでもいえる事ですが)
ブランド性の陰になっている「隠れた傑作製品」を見つけられるのも結構面白いですし、メーカー毎の造形や動力機構の差異もそこに興味を持って見れば単なる優劣だけでは語りきれない刺激があります。
とまあ、車両模型についていえばそういう事になるのですが、実はここで厄介なのが線路や走行システムに関するブランド性の問題です。
(写真は本題とは関係ありません)
2
主に車両の事について書きましたが今回は線路とシステムの話から。

いま、うちのレイアウトの線路上は最新モデルのKATOのC50が快走していますが、TOMIXやマイクロ、GMの車両も走っています。
或いは今は亡き学研、エンドウ、MOREなんかのモデルも走ります。
それどころかアーノルドやフライッシュマンの機関車や電車、それも50年近く前のモデルも(コンディションが整っているなら、ですが)最新式のモデルと同じ様に走れます。
考えて見たらこれは凄い事です。上述の車両モデルは「同じ線路であれば古今東西の違いなく走れてしまう」訳ですから。
これこそが規格が守られる事ゆえに可能な楽しみであり鉄道模型の満目躍如たる部分だと思います。
ことほど左様に線路とは鉄道模型にとって必須のパーツと言えます(当り前ですが)
ですがその凄さを意識する機会というのは普通にはあまりないと思います。
DSCN2548.jpg
40年前のTOMIXの登場はNゲージ全体にとっても大きなエポックと言える物でした。
それまでの道床なしのレールでは難しかったお座敷運転へのハードルを一気に引き下げましたし、これで鉄道模型趣味へ第一歩を踏み出した層も多かったのではないかと思います。

その直後からエーダイやエンドウも独自の線路システムを引っ提げて「道床付き組みたてレール」に参入。
中でもエーダイは当初から複々線に対応出来る事を売りにするなどかなりTOMIXを意識するものでした。
そしてそれから数年後、最後発とはいえTOMIXのシステムを研究し尽くしその欠点をある程度カバーする形でKATOがユニトラックシステムで参入。
その頃にはエーダイやエンドウは倒産、撤退などで消えており実質TOMIX・KATOの二大ブランドの時代を迎えました。
今では各々のシステムは互いにアップデートを繰り返しながら完成度を上げてきている事は皆様もご存知の事と思います。
さて
車両と異なり線路システムは「古今東西を組み合わせたチャンポンが最もやりにくい」ジャンルと言えます
特に道床付き線路のそれではさらに顕著だったりします。
実は線路という奴は組線路の時代からメーカー毎に枕木やレール断面の寸法、それどころか微妙にゲージの幅まで違っていたのですが、それでも少し無理をすれば接続自体はどうにか可能なレベルでした。
ですが今の道床付きシステム線路という奴は原則他社のシステムと組み合わせる事を考えていないだけに「メーカー毎のユーザー囲い込みがやりやすい」というメーカーにはメリット、ユーザーにとってはある意味不便な要素をはらんでいます。
そのせいでしょうか実質上記の2大ブランド体制な事もあって「ファイントラックとユニトラック」の優劣に関する論争もそれなりに聞かれます。
ただここで幸いと言いますか車両の時ほどには感情的な諍いはあまり聞かれないのがとりえです(笑)
βとVHS、WINDOWSとMac程の極端な差異がない事もここでは幸いしているでしょう。
まあ車両の様に情緒的な感性が入り込む余地が少ない点も大きいのでしょうし、ツールとしての有利さ、不便さの観点から語られる事が多いのかもしれません。

私なんぞはTOMIXの登場当時からのお付き合いだったので最初の数年くらいそのノリが続いていましたが、20年の中断の後にこの趣味を再開して最初に作ったレイアウトはKATOのパンフレットに出ていた作例を参考にした関係でユニトラックを使いました。
その後路線の拡張で本線を敷設する時にTOMIXを使ったのでメインレイアウトに関する限りはKATO・TOMIXの並立体制となっています。
これは別にユニトラックに不満があった訳ではなく「複数の線路を敷設するなら違うメーカーを使ってみるのも面白いか」位のノリで選んだにすぎません。
(ちなみにこのレイアウトではKATOーTOMIX間の相互接続はやっていません)
そんな訳でこれらの比較と言うといわゆるブランド性というよりも「便利・不便」という観点で比べる形になっています。
TOMIXの場合当初からDCフィーダーというパーツが存在した関係で「大抵のレールにフィーダーが付けられる」事が最大の魅力です。
このメリットが生かされているのがミニSLレイアウトの棚幡線で運転会の時と自宅での使用時に条件に合わせてフィーダー位置を自在に変えて使っています。
あと感覚的な印象ですが線路同士の接続はTOMIXの方に幾分かっちり感があります。
一方でユニトラックの長所は路盤状態にあまり左右されない(あとTOMIXよりも線路らしい外観の)道床とジョイナーがメリットでしょうか。
それと線路のカットと接合が比較的容易なのもメリットと言えば言えます(クラブの運転会なんかでは1ミリ単位でカットした端数レールが大活躍しています)
線路のラインナップに関しては片方が新機軸をやればもう一方も追随するというまるで仙台駅の駅弁みたいな拡充の仕方をするので大した差は感じません。
こうしてみると二つのシステムのどちらを選んでもそう問題は少ない感じです。
但しパワーユニットだけはTOMIXは乾電池駆動からサウンドシステム搭載機までかなりのラインナップなのにKATOはスタンダードと上級機まで2,3種類しかありません。
それと形態は似ている物のポイント切り替えやギャップの設定方法などの配線系にはあまり互換性がないのが不便と言えば言えます。
それとごくたまにですが例えばユニトラックで線路を組み合わせていて「ここでファイントラックにあるあれがあればなあ(もちろん逆もアリ)」と思う場面が多少はあったりする事があります。

因みに今現在私が列車運転に使っている通称クレイドルレイアウトは運転会用モジュールをベースにエンドレス化した物ですがクラブの規格がユニトラックなので直線部分とフィーダーはユニトラックです。
ですが曲線部分はカント付きカーブレールの緩和曲線の設定とベースの奥行きの都合上ファイントラックを使っています。
勿論そのままでは直接つながりませんからユニトラックのアダプターレールとバリアブルレールを組み合わせて長さの調整を図っています。
この種の他の規格同士を接続するアダプターレールはかつてはエーダイからも出ていましたが肝心のTOMIXだけは出していません。
しかも惜しい事にレイアウト上で一番列車がガタつくのがこの接続部分だったりします。
そういえばローカルレイアウトの葉純線ではメインはTOMIXでしたがガーダーブリッジだけはどうしてもKATOの奴を使いたかったので前述のアダプターレールを使ったこともあります。
またパワーパックと接続するコネクタがそれぞれの規格で異なる事(特にポイント操作系)なんかは明らかにユーザーの囲い込みを意識したものだと思います。
まあDC系のフィーダー線位ならはんだごてと熱収縮チューブの一本もあれば繋ぎ換えは簡単ですが、本来ワンタッチで済みそうな「たかが線路との結線」にそこまで手間を掛けさせられるのもどうかと。
どちらのシステムもいい加減長い期間を掛けて構築されただけに今更規格統一などができるとは思いません。
ですが異なるシステム間の接続性についてはもう少し柔軟に対応してほしいというのが正直なところです。
少なくとも線路に関する限り「ブランド性のために不便を我慢出来る層」がそうそういるとは思えないですし。





























































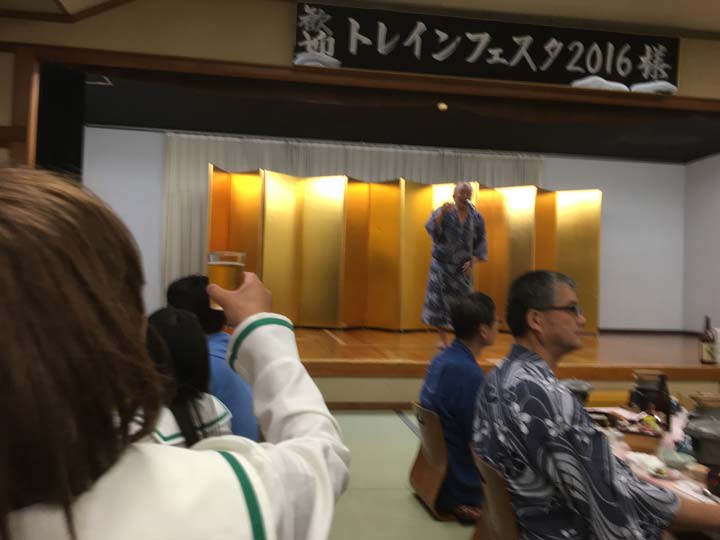

























 トレインフェスタに出展したモジュールのはなしからその2です。
トレインフェスタに出展したモジュールのはなしからその2です。
