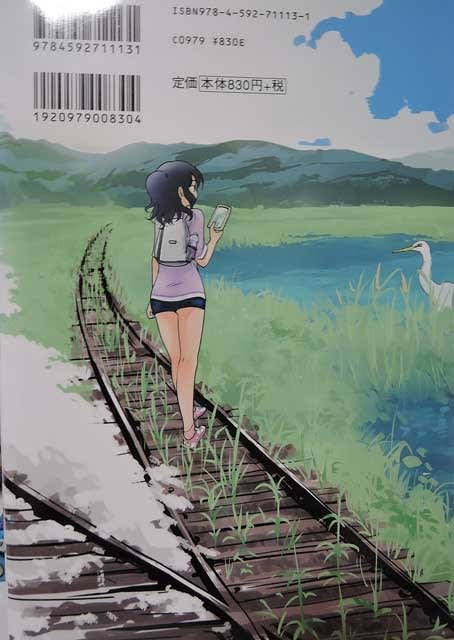先日紹介した学研ICSシステムのはなしの続きです。

このシステムは「同一線路上にふたつの動力車があって初めて威力を発揮する」訳なので、早速先日入線のKATOの701系を載せてみました。
ついでにキハ40の方も昨年暮れに中古を入手していたKATOのキハ40のトレーラーをつないで2連化させます。
701系の方はパワーパックで、キハ40の方はICSでそれぞれ個別に制御されます。
それぞれのリダクションスイッチを操作すると701系とキハ40が正面衝突コースで突進したり、先行するキハ40をKATOの701系の方で今をときめく「あおり運転」する事も可能でした。

デュアルキャブコンによる複数列車の制御運転ではギャップで区切られた閉塞区間への給電で列車の制御をおこなうため大レイアウトでないと意味が薄いと思いますが、ICSの場合は列車自体の制御なので車間距離の調節が自在にできるのがメリットと思います。

なるほど、これは面白いしレイアウトの規模によっては十分実用にもなりそうです。
現に今だったらDCCフレンドリーの車両に手を加えればこれ以上の事もできる訳ですから、私がDCCやメルクリンデジタルにはまったら大変な事になりそうな気が(おもに経済的に汗)
面白かったのはICS用の制御信号の関係なのでしょうか、KATOの701系のヘッドライトが列車自体は停止させているのに点灯し続けたこと。同じことは室内灯装備のキハ40でも起きました。
一種の常点灯状態ですが、これをうまく使えば面白いことができそうな気もします。例えばICSのユニットを停車状態の列車室内灯の常点灯ユニットとして使うなんてのも良いかもしれません(但しLEDや点灯用回路への影響は今の時点で未知数ですが)

ですが学研の悪癖はこのICSでも露呈しています。
現時点で確認できる製品としてのICS対応車はこのキハ40のみ。予定品ではキハ55とキハ58(何れも旧エーダイナイン系)が出ていますが実際発売されたのかどうか?
前述の通り、このキハ40はICSコントローラが死んでしまったらその時点でコントローラもろとも粗大ゴミ化必須。
それとこの種のコントロールシステムは機関車に組み込んだ方が威力を発揮しやすいと思うのですが、ICSでは予定すらされていません。
ICS自体も同時運転できるのは最大で2列車のみ。3編成以上に対応し室内灯のON OFFもできる現行のデジタルコマンドシステムとの差が大きすぎます。
学研も、せめて3列車以上が同時操作できるくらいの所まで頑張ってシステム展開してくれればもう少し面白いものになったろうと思うと残念です。
まあ、この辺がホビーメーカーとしての学研のカラーなのかなとは思いますが。

このシステムは「同一線路上にふたつの動力車があって初めて威力を発揮する」訳なので、早速先日入線のKATOの701系を載せてみました。
ついでにキハ40の方も昨年暮れに中古を入手していたKATOのキハ40のトレーラーをつないで2連化させます。
701系の方はパワーパックで、キハ40の方はICSでそれぞれ個別に制御されます。
それぞれのリダクションスイッチを操作すると701系とキハ40が正面衝突コースで突進したり、先行するキハ40をKATOの701系の方で今をときめく「あおり運転」する事も可能でした。

デュアルキャブコンによる複数列車の制御運転ではギャップで区切られた閉塞区間への給電で列車の制御をおこなうため大レイアウトでないと意味が薄いと思いますが、ICSの場合は列車自体の制御なので車間距離の調節が自在にできるのがメリットと思います。

なるほど、これは面白いしレイアウトの規模によっては十分実用にもなりそうです。
現に今だったらDCCフレンドリーの車両に手を加えればこれ以上の事もできる訳ですから、私がDCCやメルクリンデジタルにはまったら大変な事になりそうな気が(おもに経済的に汗)
面白かったのはICS用の制御信号の関係なのでしょうか、KATOの701系のヘッドライトが列車自体は停止させているのに点灯し続けたこと。同じことは室内灯装備のキハ40でも起きました。
一種の常点灯状態ですが、これをうまく使えば面白いことができそうな気もします。例えばICSのユニットを停車状態の列車室内灯の常点灯ユニットとして使うなんてのも良いかもしれません(但しLEDや点灯用回路への影響は今の時点で未知数ですが)

ですが学研の悪癖はこのICSでも露呈しています。
現時点で確認できる製品としてのICS対応車はこのキハ40のみ。予定品ではキハ55とキハ58(何れも旧エーダイナイン系)が出ていますが実際発売されたのかどうか?
前述の通り、このキハ40はICSコントローラが死んでしまったらその時点でコントローラもろとも粗大ゴミ化必須。
それとこの種のコントロールシステムは機関車に組み込んだ方が威力を発揮しやすいと思うのですが、ICSでは予定すらされていません。
ICS自体も同時運転できるのは最大で2列車のみ。3編成以上に対応し室内灯のON OFFもできる現行のデジタルコマンドシステムとの差が大きすぎます。
学研も、せめて3列車以上が同時操作できるくらいの所まで頑張ってシステム展開してくれればもう少し面白いものになったろうと思うと残念です。
まあ、この辺がホビーメーカーとしての学研のカラーなのかなとは思いますが。