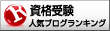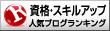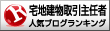いよいよ、第5講です。
ここでは、意思表示に関するトラブルを扱っています。
まず、無効となるのが3つ、取り消しできるのが2つ、あることを覚えます。
無効の方がちょっと、すぐには覚えきれないかな。みんなは。
でも、ここではどうしてそうなっているかが、だんだん気になってきます(この感覚が出てくるように)。
どうしてなんだ、という法律的な見方がでてくるはずなんです。出てきましたね。
全部5つ、無効だっていいと思うからですよ。なんで、3対2にわけたんだってこと。
そこで、人がどうして契約をするかを分析してみます。手掛かりとしてね(立法者もそうしたからです)。
まず、(契約する)動機があって、次にそこから意思を固めて、で決めたらいっきに相手方に表示するわけですね。
最後のところで、意思(の)表示というわけです。
で、この流れでどこかに紛争の種があれば、以上の5つのどれかになるわけです。それ以外にはないところが、考えた人はすごーいですね。
たった5つ。で、そんくらいなら、覚えられるでしょう。
で、意思と表示が不一致だから、無効となるグループが3つできた。
単に動機のところで問題となるのが、取消の2つ、っていう分類となった。
こちらは、一応本人の意思と表示は合致してるから、本人の意思を尊重して無効にはしなかった。感動もんですね。
そうかあ、と納得して、そうかあと一気に、覚えます。
5つはどういうものか、どう処理するのか、ですね。第三者まで登場することを予定して規定されていますので、ここでもすごいなーと思いながら学習していくわけです。
詳しい内容は、テキストを見てくださいね。
というこで、ここも制覇だ。
では、また。
☆ 最高のテキストに仕上がったと思いますので、下記テキストをよろしくお願いします。
宅建110番 パーフェクト2013
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
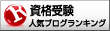
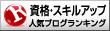
 にほんブログ村
にほんブログ村 にほんブログ村
にほんブログ村 にほんブログ村
にほんブログ村