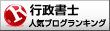初心者なら特にそうですが、テキスト、特に(項目)過去問を選ぶときの情報はほとんど持っていないと思います。
そういう場合には、使用していた人の口コミで選ぶか、アマゾンのレビュー(これも万全ではないのですが・・・)等を参考にするかでしょうか。
そうであっても、自分で使っていて、しっくりこなければ、すぐに買い換えましょう。
一発で良書を見つけられるのは、運が良いくらいに思ってください。2,3冊は、出費仕方ありません。
勿論、法律試験ですから、選ぶ基準は、単に覚えよ的なものが前面に出ているものではなく、何とかして理解させようとする著者の熱いものが、読み取れるものを選びましょう。
特に、宅建の中でも、法令の科目が一番、その判断が分かりやすいと、私は思っています。
例えば、過去問集では、H23年度の問16の問題が掲載されていたら、そこを比較してみてください。
もし、それが載っていないのは、そもそもマズイのですが・・・。ちなみに、以前出版した「宅建110番 過去問 勝利の公式 」では、この問題をきちんと扱っています(p162)。
・・・・・
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 都市計画区域は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を当該市町村の区域の区域内に限り指定するものとされている。
2 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることはできないものとされている。
3 都市計画区域については、区域内のすべての区域において、都市計画に、用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。
4 都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
・・・・・・
正解は、肢2ですが、本試験では肢3を選んだ人の方が多かったのです。
この問題ですが、準都市計画区域の実質・内容が出題された最初の年です。事前の勉強では、ほとんどの人が、講師も含めて、このような切り口の指導はしてなかったと思います。
それまでは、指定権者か区域など程度です。これは覚えろ的に教えても十分対応できました。しかし、これから法令も応用問題を出すぞということになりました。
だから、「うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ 」のようなテキストが必要と思っています。
では、先ほどの問題に戻りますが、その年でも消去法で解くこともできますから、試験委員としては、今回この区域の実質・内容がらみをこれから出すので、今後はしっかり勉強するように、とのメッセージが込められていたものでした。
ちなみに、消去法では、肢1は市町村の区域とは関係ない「趣旨が違うから」・・「H28年度25時間ではp164」
肢3は、各都市計画(11種類)の関係であり、本来は別々である。つまり、任意的である。健全な都市化は地域によって異なるからだと理解しておくべきである。・・「H28年度25時間ではp164、184」
肢4は都市計画は、肢3でも述べたように原則任意であり、区域区分も原則任意である。例外は大都会だ。・・「H28年度25時間ではp167」
なお、任意的ということは、・・「H28年度25時間ではp166の問題解説できちんと書いているので参考を」
では、消去法で肢2を出せるが、こん後のためにも、そのメッセージとは何か、この区域のイメージを押さえておいてほしいというものは何かです。
それは、この区域は「積極的なまちづくりをするのではなく、むしろ将来健全な街作りをするだんになったときておくれにならないよう、そのような障害となる行為を規制しようとするもの」ということです。・・「H28年度25時間ではp164の表、切り札、p170の切り札」でしつこく記載してます。
このように準都市計画区域は、この年から応用問題となりました。
ですから、過去問集なら、この問題を取り上げているかどうか、または準都市計画区域の問題に対するイメージを教えているか、がテキスト等を選択するときの参考になるものです。
昨年受験し、残念にも不合格となった人は、問16が照れていないと思います。でも、事前に絶対にそういう切り口・切り札が載っていれば解けたはずで、そうなってないものではダメだと分かるでしょう。
そういう本を選ぶことが合格への必要不可欠です。
では、また。
 にほんブログ村
にほんブログ村
 にほんブログ村
にほんブログ村
 資格(行政書士) ブログランキングへ
資格(行政書士) ブログランキングへ
 資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ
資格(宅地建物取引主任者) ブログランキングへ

そういう場合には、使用していた人の口コミで選ぶか、アマゾンのレビュー(これも万全ではないのですが・・・)等を参考にするかでしょうか。
そうであっても、自分で使っていて、しっくりこなければ、すぐに買い換えましょう。
一発で良書を見つけられるのは、運が良いくらいに思ってください。2,3冊は、出費仕方ありません。
勿論、法律試験ですから、選ぶ基準は、単に覚えよ的なものが前面に出ているものではなく、何とかして理解させようとする著者の熱いものが、読み取れるものを選びましょう。
特に、宅建の中でも、法令の科目が一番、その判断が分かりやすいと、私は思っています。
例えば、過去問集では、H23年度の問16の問題が掲載されていたら、そこを比較してみてください。
もし、それが載っていないのは、そもそもマズイのですが・・・。ちなみに、以前出版した「宅建110番 過去問 勝利の公式 」では、この問題をきちんと扱っています(p162)。
・・・・・
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 都市計画区域は、市又は人口、就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他の現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を当該市町村の区域の区域内に限り指定するものとされている。
2 準都市計画区域については、都市計画に、高度地区を定めることはできるが、高度利用地区を定めることはできないものとされている。
3 都市計画区域については、区域内のすべての区域において、都市計画に、用途地域を定めるとともに、その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。
4 都市計画区域については、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
・・・・・・
正解は、肢2ですが、本試験では肢3を選んだ人の方が多かったのです。
この問題ですが、準都市計画区域の実質・内容が出題された最初の年です。事前の勉強では、ほとんどの人が、講師も含めて、このような切り口の指導はしてなかったと思います。
それまでは、指定権者か区域など程度です。これは覚えろ的に教えても十分対応できました。しかし、これから法令も応用問題を出すぞということになりました。
だから、「うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ 」のようなテキストが必要と思っています。
では、先ほどの問題に戻りますが、その年でも消去法で解くこともできますから、試験委員としては、今回この区域の実質・内容がらみをこれから出すので、今後はしっかり勉強するように、とのメッセージが込められていたものでした。
ちなみに、消去法では、肢1は市町村の区域とは関係ない「趣旨が違うから」・・「H28年度25時間ではp164」
肢3は、各都市計画(11種類)の関係であり、本来は別々である。つまり、任意的である。健全な都市化は地域によって異なるからだと理解しておくべきである。・・「H28年度25時間ではp164、184」
肢4は都市計画は、肢3でも述べたように原則任意であり、区域区分も原則任意である。例外は大都会だ。・・「H28年度25時間ではp167」
なお、任意的ということは、・・「H28年度25時間ではp166の問題解説できちんと書いているので参考を」
では、消去法で肢2を出せるが、こん後のためにも、そのメッセージとは何か、この区域のイメージを押さえておいてほしいというものは何かです。
それは、この区域は「積極的なまちづくりをするのではなく、むしろ将来健全な街作りをするだんになったときておくれにならないよう、そのような障害となる行為を規制しようとするもの」ということです。・・「H28年度25時間ではp164の表、切り札、p170の切り札」でしつこく記載してます。
このように準都市計画区域は、この年から応用問題となりました。
ですから、過去問集なら、この問題を取り上げているかどうか、または準都市計画区域の問題に対するイメージを教えているか、がテキスト等を選択するときの参考になるものです。
昨年受験し、残念にも不合格となった人は、問16が照れていないと思います。でも、事前に絶対にそういう切り口・切り札が載っていれば解けたはずで、そうなってないものではダメだと分かるでしょう。
そういう本を選ぶことが合格への必要不可欠です。
では、また。
 | 平成29年版パーフェクト行政書士過去問題集 (ゼロからチャレンジするパーフェクト行政書士シリーズ) |
| 高橋克典等 | |
| 住宅新報社 |
 | うかるぞ宅建士 最短25時間~最後の切り札~ (うかるぞ宅建士シリーズ) |
| 高橋克典 | |
| 週刊住宅新聞社 |
 | 試験にうかる!!法律のカンタン思考術―宅建受験生必携 |
| 高橋克典 | |
| 住宅新報社 |