
現行教育基本法第10条には、「(教育が)国民全体に対し直接に責任を負って」おり、「教育行政は、この自覚のもとに…教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行わなければならない」と規定されている。この規定を、今回の「改正」によって、教育行政は、「国と地方公共団体との適切な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適切に行わなければならない」と規定し直している。
読み方によれば、常々行われる「国」と「地方自治体」の責任の押し付け合いを合理化し、法律に書き込んだということではないか? 国は、「地方が自立的にやることだ」といい、地方自治体は「国からの指示がないのでやれない」という、このようなことを役人言葉で「適切な役割分担及び相互の協力」というらしい。その一方で、「教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立」はないがしろにしている。
いじめ自殺、不登校、ストレスなどなど、心がとても傷ついている子どもたちがいる。そんな子どもたちための居場所となっていた学校を、大阪市の教育行政は、教育委員会での審議もなく閉じようとしている。文部科学大臣は子どもに直接死ぬなと訴えているが、その一方で、国と自治体の教育行政は子どもの生きる場を奪おうとしている。そのことを、当事者は「静かなる殺人」と呼んだ。
ともに困難をかかえた子どもたちを守ろうと、今日、「貝塚養護学校の子どもと教育を守る会」が結成された。
読み方によれば、常々行われる「国」と「地方自治体」の責任の押し付け合いを合理化し、法律に書き込んだということではないか? 国は、「地方が自立的にやることだ」といい、地方自治体は「国からの指示がないのでやれない」という、このようなことを役人言葉で「適切な役割分担及び相互の協力」というらしい。その一方で、「教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立」はないがしろにしている。
いじめ自殺、不登校、ストレスなどなど、心がとても傷ついている子どもたちがいる。そんな子どもたちための居場所となっていた学校を、大阪市の教育行政は、教育委員会での審議もなく閉じようとしている。文部科学大臣は子どもに直接死ぬなと訴えているが、その一方で、国と自治体の教育行政は子どもの生きる場を奪おうとしている。そのことを、当事者は「静かなる殺人」と呼んだ。
ともに困難をかかえた子どもたちを守ろうと、今日、「貝塚養護学校の子どもと教育を守る会」が結成された。










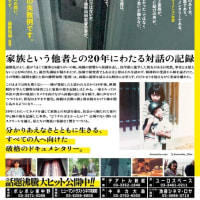




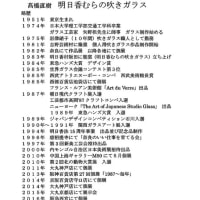

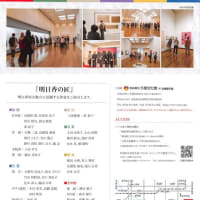


滋賀県立守山養護学校大津分校が廃校になり院内学級化されようとする時に全国の病弱教育関係者やネットを通して様々な方から応援をいただき与党の県議会議員が紹介議員になってくれるようになり、結局存続を勝ち取ることができました。
貝塚養護学校も今後ともなくてはならない学校です。存続に向けて、これまでの教育を守れるようになんとか応援していきたいと思います。