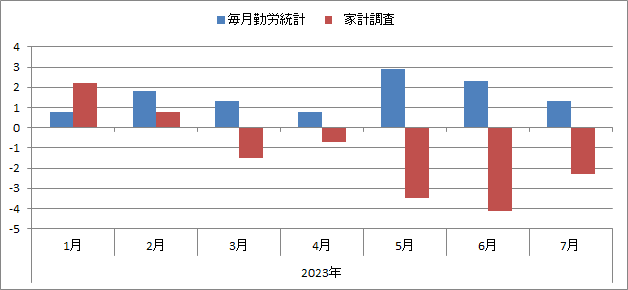岸田総理は党人事を了えて、今日は内閣改造ですね。もうほぼ決まっているようですが、新しい布陣で、平和を愛好し、豊かで潤いのある日本を作って頂きたいと思います。
今朝起きて窓を開けると真っ青な空がありました。「秋晴れ」とか「日本晴れ」という言葉がありますが、やっぱり秋だなという気がしました。
外気温も24℃で、空気も綺麗、狭い庭は雑草が伸びて先日から気になっていましたが、それはそれとして喜んでいるのは、地球柑(しまだいだい)が、色づき始めた事です。
今年は2度ほど中間報告をしましたが、鉢植えで毎年2~3個実がなる盆栽を、お隣の爺様から頂き、地球儀のような地球柑の実を見ているうちに、これを地植えにして大きくなって、枝々に、この小さな地球儀の様な実が生ったらさぞ面白いだろうと思ったのが事の始まりでした。

南側の窓のすく下に植えたのですが、丈は伸びましたが、翌年から全く花が咲かなくなりました。花が咲かなければ当然実は生りません。
木が大きくなれば実を付けるのではないかと思いながら、今年もダメかという年を重ね、こちらの寿命の方が先かなとも思い始めていました。
そして6年目、卆寿になる年を迎えた春、蕾が出、花が咲き、想像した通りに枝々に実が付いたのです。
秋になれば黄色くなり、緑の縦縞がその名の通りおもちゃの地球儀の様になるのではと思っていた日が、未だ些か暑い秋と共に来たようです。
朝食の後、数枚の写真を撮り、選んで載せたのが下の写真です。

秋晴れの朝の日光が強すぎましたが、小さな地球儀の様な実がご覧いただけると思います。
平和な日本の将来が危ぶまれるような時期ですが、こんな自然の営みを、長い時間を掛けても楽しめるのは、やっぱり人間は自然の子、自然の一部だからでしょうか。
最後にもう1枚。

今朝起きて窓を開けると真っ青な空がありました。「秋晴れ」とか「日本晴れ」という言葉がありますが、やっぱり秋だなという気がしました。
外気温も24℃で、空気も綺麗、狭い庭は雑草が伸びて先日から気になっていましたが、それはそれとして喜んでいるのは、地球柑(しまだいだい)が、色づき始めた事です。
今年は2度ほど中間報告をしましたが、鉢植えで毎年2~3個実がなる盆栽を、お隣の爺様から頂き、地球儀のような地球柑の実を見ているうちに、これを地植えにして大きくなって、枝々に、この小さな地球儀の様な実が生ったらさぞ面白いだろうと思ったのが事の始まりでした。

南側の窓のすく下に植えたのですが、丈は伸びましたが、翌年から全く花が咲かなくなりました。花が咲かなければ当然実は生りません。
木が大きくなれば実を付けるのではないかと思いながら、今年もダメかという年を重ね、こちらの寿命の方が先かなとも思い始めていました。
そして6年目、卆寿になる年を迎えた春、蕾が出、花が咲き、想像した通りに枝々に実が付いたのです。
秋になれば黄色くなり、緑の縦縞がその名の通りおもちゃの地球儀の様になるのではと思っていた日が、未だ些か暑い秋と共に来たようです。
朝食の後、数枚の写真を撮り、選んで載せたのが下の写真です。

秋晴れの朝の日光が強すぎましたが、小さな地球儀の様な実がご覧いただけると思います。
平和な日本の将来が危ぶまれるような時期ですが、こんな自然の営みを、長い時間を掛けても楽しめるのは、やっぱり人間は自然の子、自然の一部だからでしょうか。
最後にもう1枚。