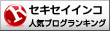日本(社会の)組織論として一世を風靡した1冊。今でも大型書店の店頭に平積みされていることが多く、楽天の三木谷氏とか、勝間和代氏など、多くの人が愛読書として掲げている。
巻頭では、単なる戦史研究ではなく、社会科学的な観点からの日本軍の組織的特性や戦略の分析を行うことにより、失敗の本質を解き明かそうと試みたとある。
・・より明確にいえば、大東亜戦争における諸作戦の失敗を、組織としての日本軍の失敗ととらえ直し、これを現代の組織にとっての教訓、あるいは反面教師として活用することが、本書の最も大きなねらいである。それは、組織としての日本軍の遺産を批判的に継承もしくは拒絶すること、といってもよい。いうまでもないが、大東亜戦争の遺産を現代に生かすとは、次の戦争を準備することではない。それは今日の日本における公的および私的組織一般にとって、日本軍が大東亜戦争で露呈した誤りや欠陥、失敗を役立てることにほかならない。(序章)
日本の「戦後」というのは、それまでの「戦前」の全否定の上に成り立っている、といわれるが、実際には日本人自らが過去をきちんと振り返って、敗因を検討していないのではないか、という議論はよく聞かれる。こういう話はともすれば観念的な議論になりがちで、実際近年巷間を賑わしている議論はそういうものが多い。他方、時流に乗ってとりあえず過去のことを否定しまくる、みたいなことをいう人は昔からいたようで、こういう人たちから新しい展望が開けることはないし、将来も同じ失敗を繰り返すであろう事は容易に推測できる。
そうした視点から見て、このような事例研究は非常に重要なのだと思う。
ただ、それを現代の組織一般にどう役立てるか、と考えてみると、複雑な気分になる。
今目の前にある、自分の属している組織や社会を見ていると、そこにいる人たちは旧日本軍のとっていた行動とよく似た事をしているような気がするが、あいにくと自分がその組織を是正できる力は、ごくわずかしかない。現状に対しこれでは良くないと思いながら、それらしい顔をしてその場をやり過ごさざるを得ないのが実情だ。おそらく、戦時中の日本軍将校の少なからぬ人たちも、似たような思いをしながら現実に流されていったというのが実情だったのではないか。
今も昔も声の大きい人が勝つことに変わりはない。大声を出せる人だけが悪いのではなく、それを押さえられない人も同罪だ。だから僕も罪を背負っている。声の大きい人との違いは、彼(女)らは罪の自覚がより薄いことだけだ(ちなみに、この組織は純粋な日本人組織ではない。欧米人と東洋人という視点で見れば、アジア各国の違いもそれほど大きくないのかもしれない。江戸っ子と関西人の気質は違うだろうが、どちらも日本人であるように)。
そう考えると、世の中の進歩って何だろうと暗澹とした気持ちになってしまう。とはいえ本書の刊行から30年が過ぎても、多くの読者の支持を受けているという事実は、将来への希望へと結びつくものだと思う。