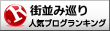先日紹介した「失敗の本質」はアカデミックな観点から見た日本軍の作戦評論、「日本海軍400時間の証言」は戦争指導者達の発言を追ったルポルタージュだったが、これは大学(高専?)を卒業して徴兵され、陸軍少尉となった著者の戦争経験談である。
歴史書や、戦記のような形の読み物は過去何度も読んだが、こういう視点からの体験談は読んだことがなかった。学生時代の思い出から始まり、徴兵検査、入隊、士官学校経験、戦闘への参加と降伏、捕虜生活と順を追って綴られている。
山本氏の著作は、大昔に「日本人とユダヤ人」(著書かどうかは議論があるそうだが)、を読んだくらいだが、この方の文章はそれほどわかりやすいとは言いがたい。自伝的な文章というよりはインタビューなどで知っていることを洗いざらいしゃべりまくったのを、そのまま文章にしているような感じである。
つらつらと時空を自由にさまよいながら、話が続くので、さて、前に作者はどうやってそこにいったんだっけ?とか、ここに出てくるX大尉って誰だっけ?とか、注意して読まないとわからなくなってしまう。まあ、僕の頭が悪いのかもしれないが・・。
しかし文章表現力が良くないのかというと、多分そうではなくて、部分的な描写はとても的確で目に浮かぶようだし、所々にあらわれる警句や独自の見解は非常に心に残る。また、読みにくい文章は、自己の内面に深く入り、それを正確に文章にしようとした結果とも取れ、それほど欠点とも思えなくなる。
戦場で生きるか死ぬかという思いをしたときに、何を感じたか、あるいは非常に厳しい状況をくぐり抜けて来た後、落ち着いてしまってからそのときの気持ちを振り返ろうとするとどうなるか(思い出せない、のだという)、というあたりの表現は、自身を振り返り本当に自分の感じたことを書き連ねようとしているのだな、という気持ちが伝わってくる。
美麗字句でそれらしい表現を重ねるという表現の仕方ではないという意味だ。。
前回「400時間の証言」の時にも書いたが、あとから振り返るとなぜあのときに、と思うようなことでも、その場にいたときの気持ちを考えると、どうにもできない、という瞬間は常に存在する。たとえ数人の仲間内ですら、まわりに流されずに適正な行動をとるのは難しいのだ。そのくせ、その場を離れると、なぜあのときに・、と悔やんでしまう。
戦争ともなると、そういう思いが極端に集積していく。その場に居合わせる経験のなかったものは、言葉でわかろうとしても正確には理解できない。
山本氏が所々に書いているが、軍隊時代の経験を若い人に語って、そうそう、と頷かれても、こいつら、本当にわかってないな、と断絶感に襲われるのも「わかるような気がする」。
ほかにもいくつか、興味深い見解が披露されている。
- 敵に包囲され、このままではダメだとわかっていても、その恐怖の対象が見えず(暗闇のなかなので)、今その場にいることが安全であるときは、その先動くことができなくなる。山本氏の知人は、船が沈みかけているとき、甲板から飛び降りなければならないとわかっているのに、甲板から夜の海に飛び込むことは難しい、といわれたという。人は理性では理解できても、自分が「いま」死ぬことは最後の瞬間まで実感できず、何とかなるのでは、と思ってしまうらしい・。
- 日本の軍隊の特徴は「言葉を奪ったこと」だという。それは私ではありません、などといえば、言い訳をするな、と何倍も殴られる。それが嫌なら何も言わずに1度殴られた方が良い。人から言葉を奪うと、あとは暴力で秩序を作っていくしかない。 もう一つの指摘は、日本が欧米人を捕虜にすると、彼らは自ら自治組織を作りそれぞれの専門性を生かして担当者を決め、一つの社会を作り上げた。ところが日本軍捕虜が収容されると、やがて暴力団組織のようなものができて、力で秩序づけられるようになったのだという。
- 他方、将官のなかでは上官が参謀、下士官に依存するような構造ができていたという。以前僕も似たことを書いたが、組織では声の大きいものが勝つ。勿論声量のことではなく、相手に威圧感を与えて自分の意見を押し通せるものが強い。かつては度量の大きな上官が、部下に自由に具申させて決断し、自らの責任の下に実行する形が取れていたが、いつの間にか上司が部下に使われるような形になってしまったらしい。それに近い形は僕の身近にも見られる。
- 明治以降の法制度における軍隊のありかたについて。いわゆる統帥権の問題だが、軍を日本国行政府の軍ではなく、天皇の直轄としたのは、それまでの藩閥勢力の一掃を図り、国内の政争から軍を引き離す意図があったのだと。そもそも、日本軍には海外と戦うなどという意図も規模も持っていなかったが、日本の経済発展の中で軍も急成長して変貌、日清、日露の戦争を勝利する。そうした中で、日本軍は日本国政府とは別の形で、日本を支配、占領して行った。
いわば一つの国が二つの勢力に支配されていたというのが当時の日本であった。軍は戦況が悪化していくと、交戦国より先に日本国政府そのものを掃討し、日本を「占領」してしまう。戦後、アメリカの占領統治がきわめてスムーズに行われたのは、それまで支配されていた日本軍よりもアメリカ軍の方がまだましだ、と思われたからではないか、という見解だ。
すべての考え方に賛成、というわけではないが、なにより組織の中で、いろいろあったときに人はどのような行動をとるか、という視点で見ると、興味深い見解は多い。
今日、身の回りで暴力による統治というのは、さすがに見ることはないが、言葉を奪うことはほかの方法でもできる。相手に何も話しかけない、というのも一つの方法だし、大声を出さなくても、一方的にまくし立てるという方法もあり、いずれも身近で見られることだ。話し合いに参加させないというのもそうだろう。そうなると、ディスカッションという習慣のない日本人は、言葉による交流というのはそもそも難しいものなのか、と考えたりもするが・・。少し考えすぎかもしれない。
もう一つ、時々いわれることに、かつては男性社会だったので戦争や暴力が肯定された、という意見。もしかしたらそうなのかもしれないが、他人を傷つけ屈服させるという「罪」は、女性でも別の方法で達成する可能性はある。出方は違っても同じ人類同士、一方だけを断罪し他方を神聖視することはできないと思う。