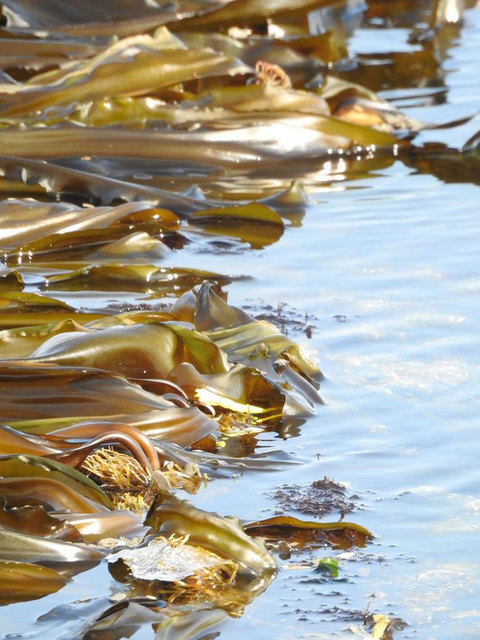男だと ちょっとグッと来るお話・・・目から汗が・・・
____________________
■「行きつけのバー」のススメ
「行きつけのバー」
男なら誰しもが憧れるだろうが、そう簡単には手に入らないソレ。
僕が手に入れたきっかけは、なかなかに面白いものだった。
大学卒業後、某メーカーの営業職に就職した僕だが、
とある日の外回りで危機的な状況に陥っていた。
「ヤバイ……。う○こしたい……下痢っぽい……」
夕方を過ぎ、最後の訪問先に向かう寂れた商店街で、
僕は冷や汗をかきながらトイレを探していた。
しかし周囲はシャッターの閉じた店ばかり。
トイレを貸してくれそうな店はない。
(こうなったら路地裏でぶっ放すしかないか……)
そう思った時に目の前で店のシャッターを開ける、
年の頃60位だろうか、自分の父親と同じくらいの男性がいた。
僕はなりふり構わず、その男性に
「すみません。お腹を下してしまって、トイレを貸してはいただけないでしょうか」と、持ちうる限り最大限の丁寧さでお願いした。すると男性は、
「いいけど、なんか飲んでって。ここ、バーだから」と、真顔で答えた。
(この人、腹を下してる人間に何を言ってるんだ……)
内心、おかしな人に当たってしまった、と思いつつも、
「しかし、この後まだ営業先に行かなくてはいけないので、
お飲み物の代金をお支払する形ではダメでしょうか」と提案すると、
「じゃあ帰りに飲みに来て。ここはバーで、トイレじゃないんだ」
男性はそういうと僕を店内に手招きした。
(そうなると、僕は帰りにここに寄らずに、そのまま帰ることもできるのに、
なんだかとても変わった人だなぁ)そう思いつつ、トイレを済ませると、
「では、帰りに寄らせてもらいます」そう言って僕は店を出た。
訪問先の滞在時間が延びたこともあり、約束は覚えていたけれど
面倒だから帰ろうかなとも思った。けれど、ちょっと様子を見てみよう、
そんな気になって、僕は帰りにその店の前を通った。
ガラスがはめられたドアをそっと覗くと、
夕方の男性が一人でカウンター内でタバコを吸っていた。
やはりというか、当然だが、この店のマスターだろう。
正直に言うと、その姿があまりにもカッコよく、様になっていて、
僕は無意識の内にドアを開けていた。
マスターは僕を一瞥すると、
「あんた、変わってるね」と無表情に言った。
(それはあなたの方では……)と思っていると、マスターはグラスを出しながら続けた。
「寄らずに帰ろうと思えば帰れた。けれどあんたはここに来た。
あんたいい人だ。今日は店を休もうと思ったけど、開けてよかったよ」
そういって丸氷を入れたグラスにお酒を注いだ。
「あんたがこの店で最初に飲む酒は、これが良い」
目の前に琥珀色より少しばかり深く落ち着いた、何とも美しい色のお酒が出された。
当時、酒を全く知らなかった僕は、とりあえず値段が怖くなり、
「お幾らですか?」と財布を出しながら聞いた。マスターは
「俺は一杯飲んでけ、と言っただけで、金をとるとは言ってない
この一杯はプレゼントだ」と優しく笑った。
その後、僕はこのバーに足しげく通い、色々な人と知り合った。
マスターから見ればまだまだヒヨっ子だが、大人になり、
結婚もし、いつか子供とこのバーに行きたいと思っていた。
そんな矢先、マスターが亡くなった。
いつだっただろうか、常連達でしっぽり飲んでいた夜、
マスターが「なんだかインターネットに店が載ったみたいで、
『落ち着いたバーですね。僕好きです』みたいな若造が増えた
俺はそういう客は好かないんだ。機械による巡り合わせは好かないんだ」
と、愚痴っぽく言っていたことがあった。
僕も含め、何かしらおかしな巡り合わせでこの店とマスターと縁が出来た常連達は、必死にネットを探し、掲載元に記事を取り下げるように頼んだりした。けれど、大半のところは「言論(表現)の自由だ」と取り合ってくれなかった。
そんな中、マスターが暫く店を休むと言った。
今思えば、あの頃から体調が悪かったのかも知れない。
そのまま復帰の知らせのないまま、常連仲間からマスターの訃報を聞いた。
告別式はマスターらしい、参列者の少ないものだった。
会場には見覚えのない女性が2人いて、話を聞くと離婚した元奥様と娘さんだった。
マスターは自分の話を全くしない人で、「俺は既に天涯孤独だ」と言っていたので、我々はそれが本当だとてっきり信じていた。
火葬の待ち時間、マスターの元奥さんと娘さんが
「これを渡すように、と言われました」と僕に1本の酒を渡してきた。
何でも亡くなる少し前に、マスターが2人に、僕に渡すように言付けたそうだ。
具体的な商品名は控えるが、某日本メーカーのウイスキー(50年)と言えば、
分かる人にはその価値がわかると思う。何故こんなものを僕に、と混乱していると、娘さんがバーで使われていた伝票を渡してきた。裏には走り書きの文字で、
「あの日のウイスキー。あんたにあげる」
そう書いてあった。
ボトルはあの日僕が飲んだ一杯から、減っていなかった。
僕は涙が止まらず、大人げなくその場に膝をついて嗚咽した。
「行きつけのバー」
僕に人生とは何か、人付き合いとは何か、
大人になるとはどういうことかを教えてくれた、大切な空間だ。
男なら誰しもが憧れるだろうが、そう簡単には手に入らないソレ。
僕は今後の人生において、もう行きつけのバーをつくることはないと思う。
マスターの三回忌にあてて。最大限の感謝と愛を込めて。