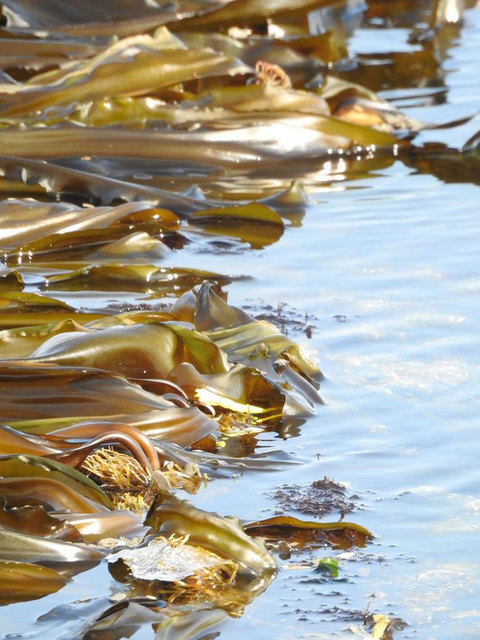1 デ・ ベジョータ DE BELLOTA
森林地帯で放牧中、どんぐり、草、その他の自然の産物のみを食べ、その後他の補完飼料を与えられなかった豚。
放牧が 10 月 1 日から 12 月 15 日までの期間に開始され、
出荷は 12 月 15 日から3 月 31 日までの間。
重量と月齢に関する条件:
放牧開始時のロットの平均体重は 92 キロから 115 キロ。
60 日以上の放牧で体重が最低 46 キロ以上増加していること。
最低月齢は 14 ヶ月。
枝肉個体の最低重量は 115 キロ、
2 デ・ セボ・デ・カンポ DE CEBO DE CAMPO
森林地帯で放牧され、どんぐり、草、その他の自然の産物を食べ、穀類・豆類を主原料とした他の補完飼料も与えられ、屋外、もしくは部分的に屋根のついた農場で飼育された豚。
一頭あたり最低 100平米 以上の広さ(110 キロ以上の豚の場合)の面積がなければならない。
放牧屋外農場での飼育期間は、最低 60 日。
最低月齢は 12 ヶ月。
枝肉個体の最低重量は、115 キロ
3 デ・ セボ DE CEBO
穀類・豆類を主原料とした飼料を与えられ、一頭あたり最低 2平米(体重 110 キロ以上の豚の場合)の面積のある農場で飼育された豚。
最低月例は 10 ヶ月。
枝肉個体の最低重量は 115 キロ、
廃止された呼称
旧規定にあった、デ・レセボ(DE RECEBO-補完飼料仕上げ)のカテゴリーは廃止された。
これは、放牧の後に、穀類・豆類を主原料とした飼料を補完的に与えられた豚の呼称だった。