『百人一首の謎』について解明した、織田正吉さんの偉業を周りの人にわかりやすく、感動をもって伝えるようにするためにはどのような手順を踏めばよいか。また資料などについても考えてみたい。
まず、話を聞いてくれる周りの人を定義しよう。百人一首がなんぞやということについてはおぼろげに知っていると仮定しよう。絵札と字札があって、絵札に書いてある歌を読んでばらまかれた字札をとるという、カルタ取りをしたり、坊主めくり等をするカルタである。百首全部暗唱している猛者から、あやふやな形で一、二首覚えている人とか、色々であろう。わたしは勿論後者でまともに言える歌は、第一首目の天智天皇の歌くらいであった。多分小学校や中学校でなんとなしに習ったことがあるのが実情なのか。ずいぶんあとになって上の子供に買い与えた『百人一首』と参考書を捨てないで取って置いたのだが、それをずいぶん後になってひもとくことになったのである。
この段階では、わたしの百人一首にたいする認識は、万葉集や古今集などと同じ歌集にすぎなかったのであるが、百人一首よりも前に西行の山家集とか、源実朝の金槐和歌集があった。
ある時期から日本の古典を読んでいくなかで織田正吉さんの『百人一首の謎』に出会い感銘を受けてしまった。読むたびに新しい発見があり、興奮するのだが、世の中にはこの喜びを知らない人が多いように思う。興味のある人は本を歌って読めばいいのだが、年を取ってくるとそこまではなかなかしい。そこで自分の頭の中の整理もかねてまとめてみようとなった。しかし、織田説は盛りだくさんでどの順番で何を伝えればよいか迷ってしまう。結論は、後鳥羽院と式子内親王への魂鎮めと身を焦がしたと言うことを伝えている。二人とも身分が違い、特に後鳥羽院は流人であるので、あからさまには気持ちを表明できない。しかし、この気持ちを百人一首に隠し、なおかつ百人秀歌や新古今集などを参考に綿密な論理で表明しているのである。










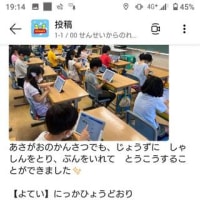
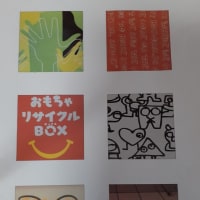














※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます