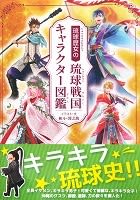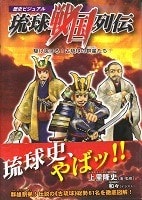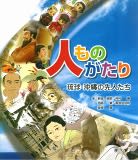ネコスケ、元気になりました。
まだちょっと食欲はないようですが、
毛繕いもしてるし、紐にじゃれもするのでもう大丈夫っぽい
肝高の阿麻和利よかったー
話には聞いてたけど、なんかいろいろとバージョンアップ
っていうか、まだまだ進化が可能なことにビックリ です。
です。
ホントは夜公演も観たかった
でもまた明日のお楽しみ。
で、公演終了後、実家に帰る道すがら、
金丸の弟の墓参りと、
百十踏揚が生まれ育った城跡と、
鬼大城がオモロで嵐を引き起こした場所(かもしれない)も巡ってきた
沖縄市にもゆかりの地がたくさんです
今日は本のご紹介。
『海の王国・琉球 「海域アジア」屈指の交易国家の実像』
(上里隆史著/洋泉社)
です。
今週発売されたばかりの新書です。
著者の上里さんはテンペスト(ドラマ・映画)の時代考証も担当した
琉球史の専門家さんです
このブログの記事とか創作小説とか、ワタシの数々の妄想(笑)や小ネタは
上里さんの本や講演から聞いたものが元になってるのも多いくらい
お世話になってる歴史家さんです(笑)
(このブログでも何度も登場してますしネ)
だって専門が古琉球!
謎に包まれた古琉球の世界を様々な視点から解き明かしていき
よりリアルな古琉球の世界を紹介してくれています
今回の本は去年沖縄タイムス連載していた
「古琉球と海域アジア」がベースになっています。
謎多き古琉球の世界を
「海域アジア」(海で繋がる国家ネットワーク)という視点で捉えたものです。
「国」と聞くと、普通は国土(陸地)のみをイメージしますが、
そうではなく、海を渡ってアジア諸国と交流をしていた
海も含めた琉球の「エリア」という大きな視点を通して
リアルな古琉球が垣間見れます。
古琉球の様々な出来事や偉人たちについても
海をキーワードにして解釈されていて「ははぁ!
 」って目からウロコです。
」って目からウロコです。
護佐丸、阿麻和利についてもありますよ
いつも面白いと思うのは(前も書いたと思いますが)、
専門家さんの視点、モノの見方。
同じ事象を見ても、専門家さんは捉え方、考え方、視点が全然違う。
(あれども見えず、は歴史に限らず全ての専門職でもいえることでしょうけど☆)
この「視点」「モノの見方」を、本や講演を通して触れられる、
新しい視点を示してくれる、得られるというのが
専門家さんから学ぶ醍醐味ですよね
というわけで、
海域アジアの視点から見る古琉球の世界、
是非、この本からその世界に触れてみてください

きっとコレまでとは一味違った古琉球や偉人たちの姿が
見えてくるかもしれません。
目次が見たい人はこちらからどうぞ。

今日から肝高の阿麻和利卒業公演始まります!
ぽちっとクリックお願いします↑
上里さんのブログの、今日の記事も面白かったですよ!
(再論「万国津梁の鐘」の真実(1))
是非こちらもご一読を☆