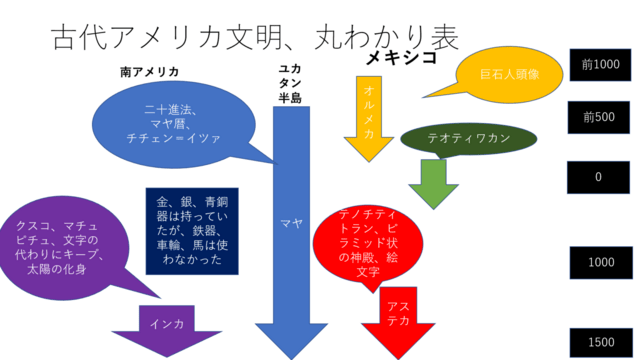『「イースター島 21の謎」を見て、ますます謎が深まった 1』
『謎解きは、世界中に分散・散失したロンゴロンゴ木片の解読から』
『絶海の孤島の歴史「黎明期・隆盛期・衰退期」の変遷から現世界は学ぶべき!』
ロンゴロンゴの記された24の木片(文字板)が19世紀後半に収集されたが、風雨による損傷や、破損、焼失部分のあるものも多かった。 これらは現在、世界各地の博物館に分散しており、イースター島に残っているものはない。
先日、NHK BS『絶海!謎と神秘の巨石文明モアイとイースター島▽21のミステリー徹底究明』再放送(2021/08/26)を見ました。 もし『ロンゴロンゴ』の破損・焼失した過去の、残念な歴史がなければ、こんなに多くの謎が残らず、多くは解読・解明されたことだと思い、残念です。
イースター島には『ロンゴロンゴ』と言う不思議な絵文字がありました。 謎の『ロンゴ・ロンゴ』の解読と解明の歴史は?
1770年、
スペインからフェリーペ・ゴンザレスが、イースター島にやって来ました。 そのとき島民は、奇妙な文字でサインしたと言う。 それが「ロンゴ・ロンゴ」です。
しかし、1862年
ペルーの奴隷狩りによって、最後の読み手である、『タンガタ・ロンゴ・ロンゴ』たちも、さらわれ死んでしまった。
1864年
宣教師ユージン・エイラウドは、島の民家から、いくつかの文字が彫られた木片を発見したと言うが、その後、島民のキリスト教改宗とともにほとんどの、『コハウ・ロンゴ・ロンゴ』のもの言う木は、『悪魔の文字』として焼き捨てられてしまった。 謎の文字となった『ロンゴ・ロンゴ』ですが、根気強い研究によって、文字の読み方は、解明されました。 まず、右上から左へ読み、180度回転させて板の上下を逆にして、下から2行目を右から左へと読む、これを、繰り返すという奇妙な読み方でした。
この文字のルーツは、インダス流域の『古代インド文字』、『アンデス文字』、
『エジプト文字』と、諸説入り乱れています。 内容にしても、
神への祈り
神官への支持
鳥に伝わる伝説
死者の名簿、など様々です。
ロンゴ・ロンゴの文字が刻まれている木片で、現存しているのは、世界でたった28点。 世界各国の博物館などにあるが、イースター島の博物館には、本物は、1枚しかありません。 チリ本土の「サンチアゴ国立自然史博物館」にあるものの複製が、2枚展示されています。 この文字が解明されれば、島に残された多くの謎が解明されるかも知れません。
ロンゴロンゴの『文字板B』
 ウキペデイア情報から引用
ウキペデイア情報から引用
数字は何行目かを表す数字。Fin de 13 は「13行目の終わり」という意味
バルテルが発表した絵文字の一例 [Jacques B.M. Guy / Public Domain / 出典]
 ウエブ情報から引用
ウエブ情報から引用
イースター島
モアイ1,000体以上、周囲60㎞、休火山3個の火山島、木がなく、川がない、動物もいない。 そのイースター島の21の謎。
1. 楕円形の遺跡、と
2. 石垣箱型がセットになっている
3. 石がゴロゴロなのに栄養満点のタロイモ、水分蒸発防いだ
4. 川がないが、5か所の地底湖
5. 黎明期、隆盛期、衰退期 島民のルーツはタヒチ
6. 島民のルーツは台湾?
7. どやって渡ってきた ダブルカヌー
8. 綾取り創世神話、溶岩の中に巨木の化石
9. 未解読文字 ロンゴロンゴ
10. モアイ 面長、ほりが深い、長い爪
11. 頭蓋骨に羽根飾りの跡
12. 超能力
13. 1000体も量産
14. 運び方
15. なぜ巨大化、全長12ⅿ、巨人21ⅿ、人口2万人で、12世紀3ⅿ座している、14世紀5ⅿ、16世紀10ⅿ、権威誇示
16. 星とモアイの神秘的な関係、モアイの向きとスバル?
17. 衰退原因はネズミ、海鳥の卵
18. 食料危機
19. 人骨に刃物の跡(女性・子供)森林崩壊から100年
20. 希望を託された鳥人伝説
21. ラパヌイ文明滅亡
先ずは、『1、楕円形の遺跡』
8-10世紀にモアイと、ほぼ同時期につけられた、この楕円形の遺跡
(ヤシの巨木をモアイづくりで全滅させた海洋民族の祈り)
 ウエブ情報から引用
ウエブ情報から引用
『2、石垣箱型がセットになっている楕円形の遺跡』
重要な食糧(鶏卵・鶏肉)を、盗人、野生動物から守った鶏舎
 ウエブ情報から引用
ウエブ情報から引用
『「イースター島 21の謎」を見て、ますます謎が深まった!』の残り(3~21)は、楽しみな今後の課題です。
(記事投稿日:2022/05/05、#531)