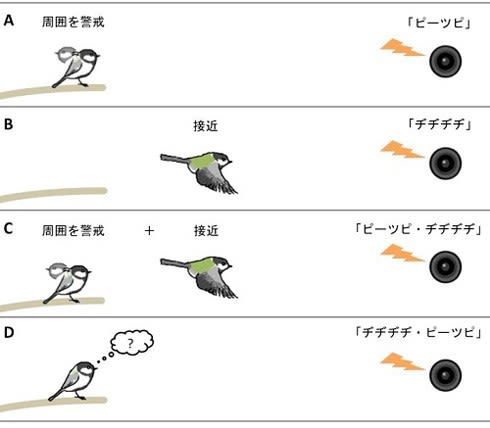1701年 江戸城で浅野内匠頭が吉良上野介に向かって刀を振り回し斬りつけた事件。 『忠臣蔵』では吉良のいじめが動機として描かれている。
幕府(5代将軍綱吉)から勅使饗応役(ちょくしきょうおうやく)を命ぜられました。 江戸城に来た朝廷の使者をもてなす役割で、費用は藩が負担します。
その上司は高家・吉良上野介義央
高家:朝廷との交渉や儀式・典礼を司る役職で、吉良はその筆頭。浅野は18年前にも接待役を務め、接待費用を450~460両支払いました。 近年の費用を確認すると、1200両(約1億4400万円)に増額していた。
浅野は700両に出来ないかと提案、しかし吉良は受け入れようとはしなかった。
松の廊下事件
吉良は、浅野が世間しらずの田舎者だと愚弄したようです。 古文書には浅野が短慮(気みじか)な人物とも書かれており、吉良の横柄な態度に浅野が恨みを抱いたとする説があります。
浅野は即日切腹、吉良はおとがめなしと、喧嘩両成敗ではなかった。
赤穂藩はお家取りつぶし。 藩の城や屋敷はすべて幕府に没収されました。
松の廊下事件の後、吉良は両国に引っ越し。 吉良の屋敷が広すぎる、吉良は留守が多いなど問題点がありました。
屋敷は東西に約130m、南北に約60m 約780㎡(敷地 約2550坪)と広大。
作戦1 赤穂浪士の前原・神崎が雑穀店に変装して屋敷近くに潜伏
吉良家の人間と親しくなって、警護の様子を探っていました。
雑穀店の屋根から吉良邸を観察していました。
前に住んでいた大名家の図面に集めた情報を加え屋敷図を作りました。
作戦2 吉良の顔を探れ
大石を始め、誰も吉良の顔を見たことが無かった。顔がわからないまま、
当時約8300万円あった軍資金が江戸での滞在費等で消費され、討ち入りを
作戦3
吉良は、親戚の上杉家に泊まることが多いことが分かりましたが、お茶会が
<吉良邸内部をどう探ったのか>
名前や職業を変え、吉良邸の人間と接触、屋敷の構造や在宅日時を掴んだ
赤穂浪士の怪我人は数名で、吉良を打ち取るに成功、圧勝出来たのは、討ち入り道具。
呼子鳥笛:討ち取った時の合図・47士全員が持っていた。 室内用の黒い筒(照明道具):松明だと火災の可能性があるため。 放火や失火は罪が重く、死罪となることもあったため。 さらに吉良邸の隣の大名家が高提灯で屋敷内を照らしてくれていた。
大石は吉良側の人間の士気が低いことを察知。 渡者:派遣社員のように主人を変えて仕える者。 渡者の比率が高かった。
表門部隊は約5mの長屋塀を竹梯子で乗り越え、裏から表門のかんぬきを外した。
裏門部隊はかけ矢(木槌)で侵入。 さらに、庭の見張り、屋敷内の斬り込みなど、分担。 備えてあった弓や槍も破壊しました。 敵一人に付き3人態勢で戦闘し、有利に戦いを進めた。 約1時間で屋敷を制圧しましたが、なかなか吉良氏が見つかりませんでした。 炭小屋に隠れていた老人を見つけ、
肩の傷跡をで、吉良だと判別。 彼らの装束でわかるように、浅野家は祖父の代から火消し役でした。
<150人相手になぜ圧勝>
用意周到な装備と戦術の工夫と、火消しとしての統率力があったから
大石内蔵助を介錯した刀。 介錯人の子孫に伝わる介錯の刀・二尺一寸
刀を研ぐことは非礼に当たりとされ、300年以上手入れは油の塗り替えのみ。
切腹の解釈に「備前長船」という名刀が使われました・それだけ敬意を表していました。
赤穂浪士・寺坂吉右衛門は切腹せずに83歳まで生き延びました。
大石は、正確に世間に伝わることを願い、真意が後世に残るよう、寺坂に密命していました。 切腹までの間の聞き込みにも、誰も口を割らなかった。 寺坂の主人の吉田忠左衛門「この男は不届きものだ」と幕府の捜索が入らないことの芝居だった。寺坂の記録が『寺坂信行筆記』に残っています。
堀部安兵衛も自分たちの手紙などを学者に渡したと言われています。
<大石内蔵助が仕掛けた狙い>
寺坂によって、討ち入りの真意を後世に残すこと。
討ち入り直前まで潜伏していた大石は、家紋を内側に隠してあります
近松家に伝わる記録『義士墓前報告一件』「主君の想いを遂げよう」
「懐から刀を出し、石塔に置き、吉良上野介の首に三度当てた」
討ち入りの後、泉岳寺で敵討ちの報告をしました。
浅野内匠頭の短刀で斬る仕草を、義士たちが代わる代わる行う儀式。
主君に吉良の首を取ってもらうというのが、彼らの本当の狙いだった
主君の浅野が成仏できず、怨霊になることを恐れたとも言えます
<赤穂浪士たちの本当の目的>
亡き主君の願いを叶えること
切腹の日に検視から、吉良家がお家取りつぶしになったことを聞いて、大石が泣いたそうです。
高家:戦国大名の子孫など、格式の高い家が務める役職
時には将軍の使者として朝廷の儀式に参加することもあります
吉良の死後、吉良家自体が高家の役職から解任されました。 幕府の中には、吉良を排除して、朝廷と新たな関係を築きたいとの思惑がありました。
幕府としては合理化していきたい、そのために吉良が邪魔な存在になり、公家の次男の新高家にどんどん変えていくことを考えていきました。
いくつか、討ち入りに際して違和感があることに気づきます。
・吉良邸の引っ越し
警備の厳重な江戸城の近く(現在の丸の内)から警備の薄い両国へ。 周りに住んでいた大名たちから「赤穂藩が攻めてくるから嫌だ」と言われていました。
・大石内蔵助の手紙
幕府が密偵を付けてきましたが、吉良邸を打ち破ることを特段とがめることもありませんでした
幕府内の怪しい人物は、柳沢吉保(5代将軍綱吉の側近として信頼の厚かった人物)ではないかと言われています。 平和な世の中において、不要になってしまった武士の本来のスゴさを庶民に再認識させたかった、という説もあります。
<成功した理由>
幕府の陰謀か、大衆の熱狂などの空気があったと言われています。
かつて赤穂浪士は120人以上いました。
大石は裏切らない確信として、血判状を書かせ、浪士たちの覚悟を見際めました。 「親族にも一切口外しません」大石はわざと使いの者から「討ち入りは断念しました」と血判状を返却しました。 その反応を見て、やる気のある者を討ち入りのメンバーを選びました。 覚悟のない人の前で討ち入りの話をすると、周辺の藩に噂が広がってしまいます。 処分されそうな赤穂藩の実情に対して、報告・密告をするのが御奉公の一つでした。
大石は討ち入りを諦めたふりをして血判状を返却し、スパイの目を欺く狙いもあったようです。
この用意周到さには驚くばかりです。 情報が拡散されない時代に、幕府の動向・様子をよく分析・読めたものです.