







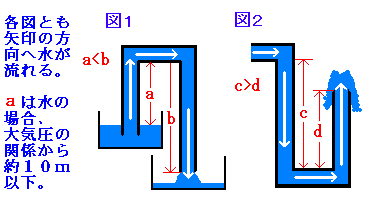
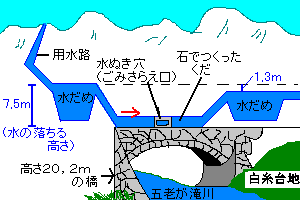
『錆びない剣 2(隕石から低温鍛造で鉄剣を製造、凄い古代技術)』
『ツタンカーメン王墓から発見された鉄剣、当時製鉄技術普及なし』
数年前に、ツタンカーメンの特番で、3,400年間も『錆びなかった剣』が放送されました。 今回は、その製造方法と起源を千葉工大の研究チームが特定しました。

ウエブ情報から引用
上段2枚、ツタンカーメンの鉄剣の両面。下段は1925年に撮影された同じ鉄剣
日経新聞(2022/03/06)サイエンス蘭の抜粋・引用です。
千葉工業大学の研究チームは、古代エジプトのツタンカーメンン王墓から発見された鉄製の短剣が製造された方法や場所を解明した。 短剣が隕石から低温の鍛造と呼ばれる手法でつくられたことや、メソポタミア北部にあったミタンニからエジプトに送られたとみられることを明らかにした。 これまで短剣は鉄でできた隕石が原料とみられているが、製造方法などはわかっていなかった。
ツタンカーメンの時代にはまだ製鉄技術は普及していなかったと考えられており、鉄の歴史に一石を投じそうだ。 短剣を削ったりせずに分析できる蛍光エックス線分析装置を使い、使っている鉄や短剣の柄を分析した。 鍛造という金属をたたいてのばして、加工する鍛造という手法で、セ氏950℃以下の低温で製造されたことを明らかにした。 鉄は通常セ氏1300℃程度の高温にしてから加工される。
メソポタミアのミランニからツタンカーメンの王の祖父に贈られたと記録が残る鉄の短剣の可能性があると結論づけた。 短剣が隕石からつくられたとみられること、は、イタリアのチームが、2016年に、発表したがエジプトの隕石でつくられたと推定していた。
ツタンカーメン王は紀元全14世紀の古代エジプトの王。 当時、開発されて間もない製鉄技術は、現在のトルコにあったヒッタイト帝国が独占していたと考えられている。
とにかく、当時のエジプトを中心とし、ヒッタイト帝国を含めた『サプライチェーン』には驚くばかりで、ますます、エジプトとヒッタイトに興味津々です。
(記事投稿日:2022/03/06、#487)
『日本は凄い・日本人は凄い 1(折り紙のこと)』
『「ミウラ折り」宇宙で衛星用太陽電池パネルの輸送時のコンパクト化が実現』
折り紙の起源はハッキリしてないようです。 中国やスペイン説もあります
正式にわかっていないのが現状のようです。 最近では、韓国が名乗り上げていますが韓国の折り紙は、ハサミや接着剤も使っているので、日本の伝統の折り紙とは全く違うと言われています。
日本の折り紙の凄さは三浦公亮東大名誉教授が考案した『ミウラ折り』です。 『ミウラ折り』では、縦の折り目にジグザグに傾斜をつけることによって、折り目が重ならずコンパクトになる。また、折り畳んだ一端を引くだけで、全体を一気に開けるという特徴があり、衛星用の太陽電池パネルの輸送時の驚異的なコンパクト化が実現しました。
ある方から入手した、折り紙のゴジラです。 その精緻さには驚くばかりです。


カラフルな折り紙
無骨者・不器用な傘寿爺にはとても折れない折り紙五態

折り紙の歴史のウェブ情報からの抜粋です。
7世紀初めに大陸から紙の製法が日本に伝えられたのち、日本人の工夫によって薄くて丈夫な紙、「和紙」が生まれました。 はじめ写経や記録が紙の重要な用途でしたが、神事にも用いられるようになり、神への供物など様々なものを紙で包むようになりました。やがて供物や贈り物を包んだとき紙に折り目がつくことに着目して、包みを美しく折って飾る儀礼折が生まれてきます。
室町時代(14,15世紀)に入ると小笠原家や伊勢家によって様々な礼法が整えられ、紙包みの礼法(儀礼折)もそのころ考えられたものです。今も使われている熨斗包みや雌蝶・雄蝶などの折り方はその名残です。
やがて礼法や決まりから離れて、折り方そのものを楽しむようになったのが「折り紙」です。江戸時代に入ると紙の生産量も増え「折り紙」はいっそう庶民に親しまれるようになりました。寛政9(1797)年には世界で最も古い折り紙の本「秘傅千羽鶴折形」が出版されています。
明治時代に入ると、「折り紙」は幼稚園教育にもとりいれられ、小学校では手工や図画でも教えるようになり、ますます盛んになりました。現在では、「折り紙」は世界各地に広まり、折紙愛好家の団体がいくつもできて盛んに活動を続けています。
折り紙の歴史からも、折り紙の設計図描きを想像する時、日本は・日本人は、やはり凄いです。
(20181218纏め、20210220追補、#040)
『AI・人工頭脳は人間を超えるか 1(人類の位置はどうなるか)』
ー『ノーベル賞が消える日』20XX年のノーベル賞は、AIが独占かという記事がー
11月4-6日の日経朝刊にシリーズで『AIと世界』が特集され、その中に『ノーベル賞が消える日』というショッキングな見出しで、20XX年のノーベル賞は、AIが独占かという記事がありました。
(影の声、日経新聞までも、この表現!)
既に、2014年6月7日、英レイティング大学が実施した『コンピューターに知性があるかどうか』のテストに、ウクライナ製のコンピューターソフト『ユージーン』が、史上初の合格となった。
その前後に、AIが人を超えたのは、具体的にいろいろありました。
❶1997年5月にIBMの『ディープブルー』という、チェスのコンピューターソフトが、チェスの世界チャンピオンに勝利。
❷2012年の日本の将棋電王戦ではコンピューターソフトが3勝1敗1待ち将棋(引分け)で勝利。 その前に米長プロが率先して挑戦を受け負けています。
❸2016年3月にグーグルのコンピューターソフト『アルファ碁』が韓国の天才棋士・李世乭に勝利。 韓国人の間に『AI恐怖症』蔓延。
この李世乭棋士、同じ現役の李昌鎬の実績、世界戦での21勝に次ぐ18勝。
『囲碁においては、あと10年は、AIは人間に勝てない』と言われていました。
今回の勝利、『囲碁の謎』を解いたグーグルの超知能は、AIの進化を10年
早めた。
『囲碁においては、あと10年は、AIは人間に勝てない』を裏付ける一言。
最近、日本囲碁で7冠達成の井山裕太プロも この李世乭棋士との対戦、2連敗の後、こう言っていました『囲碁の長い歴史のなかで、李世乭さんは、もしかしたら人類最強かもかもしれない。 李世乭さんがコンピューターに勝てないなら人類は永遠に勝てないかもしれない』と。 李世乭棋士は、コンピューターに負けたことで引退も考慮と。
掲記のテスト『コンピューターに知性があるかどうか』が想起させたのが、AIが人間を超える、転換点・特異点(シンギュラリティ)が2045年で『2045年問題』となります。 米国の発明家・未来学者レイ・カーツワイル氏の提唱。

下記は、現時点での専門の方々の見方です。 人類の叡知で『2000年問題』と同様に解決できると・・・。 余談ですが、『2000年問題』の比ではないと思うと同時に、なぜ、2045年とピンポイントで指摘できるのか。
❶AIで東大合格を目指す、新井紀子氏
日本の人口が減ることを前提に、人とAIが一緒に働くモデルを。
❷光明寺僧侶、松本紹圭氏
AIは先人の死生観を学び、人とAIの死生観を変え、死の意味合いが変わる。
❸パラリンピックランナー、高桑早生氏
積極的に、AIを体に組み入れは、したくないが、共に生きる相棒に。
❹日立製作所、東原敏明氏
AI思考は人間より深く広いが、最終的経営判断は人の直感だ。
❺米スタンフォード大教授、ポール・サフォー氏
技術の進化は加速する一方で、人の倫理や文化がついていない。 予想外の、
ことに対応できる、より強い仕組みと規律が必要だ。
❻中国のSF第一人者、王普康氏
AIは人間より信頼できる。 文化大革命のような過ちはせず、新しい共生
関係が生まれる。
❼仏哲学者、シャンガブリエル・ガナシア氏
機械がある日突然、人間抜きで、自主性を持つというのは幻想だ。
❽シンガポール投資家、ジム・ロジャーズ氏
私はまだ、AIには負けない。 この『2045年問題』を解決するAIは発明されていない。
以上、お国柄がよく出ています。
AIにノーベル賞を与えざるを得ない、受賞させようとする、人々の意見は「『大量に発表される論文を読み込み、超高速で膨大な仮説を作成し、繰り返し、検証を続けることができるのがAI』、ひらめきや偶然が生み出す、人の大発見に対し、AIは、圧倒的なスピードと量で臨む」から。
ここで、凡人の一言を言わせてください。 『AIを作るのも人、AIを使うのも人だ』と、いう人も居るが、『AIがAIを作り、AIを使う。 さあ、どうする人である皆様』が『2045年問題』という大問題なのです。
この問題解決への『人の頑張り』を自分は、全部見られないことを残念に思うこの頃です。
(20161106纏め 20181230改 #047)