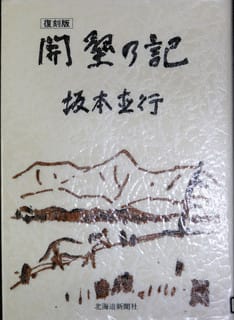
北海道の誇る菓子メーカー「六花亭」の包装紙に描かれた草花の絵や、児童詩誌「サイロ」の表紙絵を長く手がけたことで知られる坂本直行(1906~82)。
名は「なおゆき」と読むのが正しいらしいが、ほとんどの場合「ちょっこう」と呼ばれている。知名度が高い人で、北海道文化賞も受けているが、北海道の美術史の主流をつくる画家とは正直いって言いがたい。
団体公募展や、現代美術のグループ展で活躍したというよりは、50代に入ってから、個展や、北大関係者の登山好きによる「歩々の会」などを舞台に作品を発表しながら、挿絵を描いたという、独特のポジションにあった人だといえそうだ。
その坂本直行の代表的な著作といえるのが、1942年(昭和17年)に出版された『開墾の記』である。
筆者が読んだのは1992年に北海道新聞社から復刻された版である。
北大農学部実科を卒業、在学中は北大山岳部創立メンバーとしてあちこちの山に登った坂本直行は、36年に十勝管内広尾町(当時は広尾村)に入植した。それから約5年間の体験をつづったのがこの書物だ。
北海道で最初に本格的な開拓が始まったのは明治時代であり、それから70年以上がたった昭和時代であるが、その原始生活ぶりはとにかくすさまじいのひとことに尽きる。掘っ立て小屋のような家には容赦なく雪が吹き込んでふとんの上に積もり、冬の初めに室内で凍った水は春までとけない。馬は流産する。牛は転んで倒れ、死ぬ。鶏を飼えばイタチにやられ、育てた麦はカラスに食われる。風呂は数カ月沸かせない。霧や冷害が作物を枯れさせる。
こんな厳しい自然環境の中でよく挫折せずに生きているものだと感服するほかない。現金収入がないので、冬は炭を焼き、馬小屋も自宅も自ら建て、雪の中をついて牛乳を売りに行く。薪を割り、畑を起こす。休む暇もない。
そのわりには、坂本直行の筆致は意外と淡々としており、湿っぽいグチをこぼすでもなく、咲き乱れる野の花や陽光にかがやく日高山脈の山々に心をなごませ、ばりばりと野良仕事をこなしていくのである。そればかりか、農村における文化を論じ、役所仕事の形式性を批判するくだりもある。
同じく十勝地方の農民兼画家が題材になっている神田ミサ子『私の神田日勝』も、その生活の過酷さ、ギリギリさ加減に胸をつかれるのだが、とりあえず四半世紀後の日勝の時代は電気が来ているだけでもまだマシといえる。
しかし、個人的な感覚を述べれば、『私の神田日勝』のほうが好きなんだな。
『開墾の記』は、確かにすごい経験でびっしりと埋まっているのだが、なんだか肌に合わないところがある。敬遠したくなるというか。
なぜだろうと、考えてみた。
統計などがあるわけでなく個人的な印象で言うのだが、文学でもジャーナリズムの文章でも、昭和一桁に書かれたものの多くが暗いのに比べ、昭和10年代、とりわけ14~17年(西暦だと1939~42年)あたりに書かれた文章は、妙に明るく、健康さがあるように思う(言うまでもないが、昭和18、19年は、出版自体が激減してしまう)。
祖国が破滅に向かって突き進んでいるその数年前になんて奇妙な、とわたしたちが感じるのは、歴史を知っているからであって、その当時に生きていた人々は1945年(昭和20年)に破局が来るなどとはつゆ知らずに日々を送っていた。むしろ、五族協和と大東亜建設の明るい夢を見ていた時代だったといえるのである。経済が昭和恐慌のどん底を脱したことも一因かもしれないし、「ヤバイぞ」と言い続けていた人たち(おもに左翼陣営)の口がふさがれてしまったこともあるだろう。
これは同時代のナチスドイツのプロパガンダの明るさや健康性にも通じるところがあろう。
復刻版で読む限り『開墾の記』には軍国主義を鼓吹するような部分はない(後から削除した可能性は否定できないが)。国から作物の割り当てがあったり、近所の人が出征したりといったくだりはあるが、軍人は登場しないし、日本の主要都市が空襲で焼け野原になることは予想だにしていなかったころの本なのである。
筆者のように非力な文弱の徒にははなはだ生きづらい時代だっただろうなと思う。
それでも、金子光晴のように敗戦を見据えていた者はごく少数で、横光利一も高村光太郎も三好達治も、時代の中に明るさを見ていた。
筆者は、通底する明るい健康的なにおいを『開墾の記』にかぎ取ってしまい、なんとなく敬遠したくなったのだろう。
名は「なおゆき」と読むのが正しいらしいが、ほとんどの場合「ちょっこう」と呼ばれている。知名度が高い人で、北海道文化賞も受けているが、北海道の美術史の主流をつくる画家とは正直いって言いがたい。
団体公募展や、現代美術のグループ展で活躍したというよりは、50代に入ってから、個展や、北大関係者の登山好きによる「歩々の会」などを舞台に作品を発表しながら、挿絵を描いたという、独特のポジションにあった人だといえそうだ。
その坂本直行の代表的な著作といえるのが、1942年(昭和17年)に出版された『開墾の記』である。
筆者が読んだのは1992年に北海道新聞社から復刻された版である。
北大農学部実科を卒業、在学中は北大山岳部創立メンバーとしてあちこちの山に登った坂本直行は、36年に十勝管内広尾町(当時は広尾村)に入植した。それから約5年間の体験をつづったのがこの書物だ。
北海道で最初に本格的な開拓が始まったのは明治時代であり、それから70年以上がたった昭和時代であるが、その原始生活ぶりはとにかくすさまじいのひとことに尽きる。掘っ立て小屋のような家には容赦なく雪が吹き込んでふとんの上に積もり、冬の初めに室内で凍った水は春までとけない。馬は流産する。牛は転んで倒れ、死ぬ。鶏を飼えばイタチにやられ、育てた麦はカラスに食われる。風呂は数カ月沸かせない。霧や冷害が作物を枯れさせる。
こんな厳しい自然環境の中でよく挫折せずに生きているものだと感服するほかない。現金収入がないので、冬は炭を焼き、馬小屋も自宅も自ら建て、雪の中をついて牛乳を売りに行く。薪を割り、畑を起こす。休む暇もない。
そのわりには、坂本直行の筆致は意外と淡々としており、湿っぽいグチをこぼすでもなく、咲き乱れる野の花や陽光にかがやく日高山脈の山々に心をなごませ、ばりばりと野良仕事をこなしていくのである。そればかりか、農村における文化を論じ、役所仕事の形式性を批判するくだりもある。
同じく十勝地方の農民兼画家が題材になっている神田ミサ子『私の神田日勝』も、その生活の過酷さ、ギリギリさ加減に胸をつかれるのだが、とりあえず四半世紀後の日勝の時代は電気が来ているだけでもまだマシといえる。
しかし、個人的な感覚を述べれば、『私の神田日勝』のほうが好きなんだな。
『開墾の記』は、確かにすごい経験でびっしりと埋まっているのだが、なんだか肌に合わないところがある。敬遠したくなるというか。
なぜだろうと、考えてみた。
統計などがあるわけでなく個人的な印象で言うのだが、文学でもジャーナリズムの文章でも、昭和一桁に書かれたものの多くが暗いのに比べ、昭和10年代、とりわけ14~17年(西暦だと1939~42年)あたりに書かれた文章は、妙に明るく、健康さがあるように思う(言うまでもないが、昭和18、19年は、出版自体が激減してしまう)。
祖国が破滅に向かって突き進んでいるその数年前になんて奇妙な、とわたしたちが感じるのは、歴史を知っているからであって、その当時に生きていた人々は1945年(昭和20年)に破局が来るなどとはつゆ知らずに日々を送っていた。むしろ、五族協和と大東亜建設の明るい夢を見ていた時代だったといえるのである。経済が昭和恐慌のどん底を脱したことも一因かもしれないし、「ヤバイぞ」と言い続けていた人たち(おもに左翼陣営)の口がふさがれてしまったこともあるだろう。
これは同時代のナチスドイツのプロパガンダの明るさや健康性にも通じるところがあろう。
復刻版で読む限り『開墾の記』には軍国主義を鼓吹するような部分はない(後から削除した可能性は否定できないが)。国から作物の割り当てがあったり、近所の人が出征したりといったくだりはあるが、軍人は登場しないし、日本の主要都市が空襲で焼け野原になることは予想だにしていなかったころの本なのである。
筆者のように非力な文弱の徒にははなはだ生きづらい時代だっただろうなと思う。
それでも、金子光晴のように敗戦を見据えていた者はごく少数で、横光利一も高村光太郎も三好達治も、時代の中に明るさを見ていた。
筆者は、通底する明るい健康的なにおいを『開墾の記』にかぎ取ってしまい、なんとなく敬遠したくなったのだろう。



















