2024年2月13日(火)
1月25日付の当ブログで、ケストナーの小品から下記の会話を転記した。
「息子のホールバインご存じ?」
「正直言うと、知らんですな!おやじのほうも知らんです」
「ホールバインは有名なドイツの画家なんですよ。長い間ヘンリー八世の宮廷にいたんですの」
「そりゃあ知っとるです」
キュルツは嬉しそうに言った。
「そりゃああれでしょう、裸足で一日雪の中に立ってたやつでしょう」
「ちがうわ、それはヘンリー四世よ」
「しかし、だいたい当たったでしょう?」
「そうね、まあだいたいね。ヘンリー四世はドイツの皇帝で、ヘンリー八世はイギリスの王様なの…」
「正直言うと、知らんですな!おやじのほうも知らんです」
「ホールバインは有名なドイツの画家なんですよ。長い間ヘンリー八世の宮廷にいたんですの」
「そりゃあ知っとるです」
キュルツは嬉しそうに言った。
「そりゃああれでしょう、裸足で一日雪の中に立ってたやつでしょう」
「ちがうわ、それはヘンリー四世よ」
「しかし、だいたい当たったでしょう?」
「そうね、まあだいたいね。ヘンリー四世はドイツの皇帝で、ヘンリー八世はイギリスの王様なの…」
キュルツ親方は英国王ヘンリーとドイツ皇帝ハインリヒを混同しているのだが、そもそもトリュープナー嬢は英国王を指して「ヘンリー」と言ったか「ハインリヒ」と言ったかが気になっていたのである。
本日、真相判明。原文は下記の通り:
"Kennen Sie Holbein den Jüngeren?"
"Wenn ich ehrlich sein soll: nein! Den Älteren auch nicht."
"Holbein der Jüngere war einer der berühmtesten deutschen Maler. Er lebte eine Zeitlang am Hofe Heinrichs VIII."
"Den kenn ich", meinte Külz erfreut. "Das ist der, der einen Tag lang barfuß im Schnee stand."
"Nein, das war Heinrich IV."
"Aber ungefähr hat's gestimmt, was?"
"Ziemlich. Heinrich IV. war deutsher Kaiser, und Heinrich VIII. war König von England..."
"Die verschwundene Miniatur"
つまり、どちらも Heinrich だったのだ。そりゃそうか、というところだが、このあたりが「近場はかえって不便」だというのである。どれもこれも Heinrich では、ヘンリー8世とハインリヒ4世ばかりかアンリ2世もエンリケ1世も区別がつかず大混乱であろう。こちらは少なくとも、どこの国の王様だか皇帝だかは、名前を聞けばすぐ分かる。
ただし同種のことはこちら側にもあって、漢字を共有する便利さの反面、それぞれがそれぞれの読み方で読むのでかえって混乱しがちである。たとえば中国人は、「松山」をソンシャンと中国読みする。ソンシャンとマツヤマでは似ても似つかないが、なまじ漢字を共有しているからこういうことが起きるのだ。地名ぐらい日本語に倣えば良いのにと思うが、こちらも習近平(シー・ジンピン?)を「シュウキンペイ」と呼ぶのだから文句は言えない。
お互い様、そしてこのあたりが言葉の面白さである。
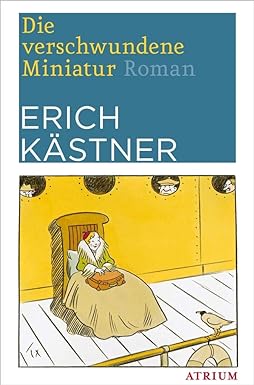
Ω









