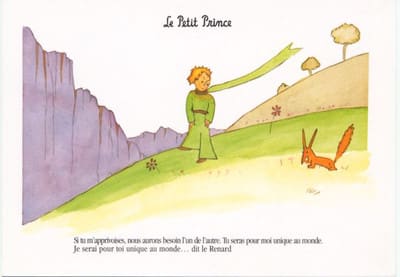2024年5月26日(日)
M師の説教から:
καὶ παράγων εἶδεν Λευὶν τὸν τοῦ Ἁλφαίου καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ λέγει αὐτῷ, Ἀκολούθει μοι. καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ.
そして通りがかりに、アルファイの子レビが収税所に座っているのを見かけて、「わたしに従いなさい」と言われた。彼は立ち上がってイエスに従った。
マルコによる福音書 2:14
「座っている」と訳されている καθήμενον < καθήμai はしばしば「住んでいる」という意味で用いられる動詞であり、そのことからもレビが収税吏として生活を立てていたことが窺われる。
これに先だってペトロとアンデレ、ヤコブとヨハネの二組の兄弟が、イエスに招かれ従っていた。彼らは漁師であって、イエスに従う道行きが挫折した場合に生業に戻ることは比較的容易だった。事実、十字架後にガリラヤ湖で漁にあたっていたことがヨハネ福音書から知られる。
レビの場合は事情が異なり、ローマの権力によって承認された収税吏の職をいったん放擲した以上、そこへ戻ることはほぼ不可能だった。さりげなく記されたレビの決断は、人生を賭けた不退転のものだったのである。
このレビという人物が福音書記者マタイであることが、他ならぬマタイによる福音書の記述からわかる。しかしマタイはこの召命のできごとを除き、自身については一切語らない。自分が何をしたかではなく、イエスが何をなさったか、何をしてくださったか、それのみを語る。
これを「証し」という…
ついでのことに16~17節:
καὶ οἱ γραμματεῖς τῶν Φαρισαίων ἰδόντες ὅτι ἐσθίει μετὰ τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ τελωνῶν ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, Ὅτι μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει;
καὶ ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς [ὅτι] Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες· οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους ἀλλ᾽ ἁμαρτωλούς.
ファリサイ派の律法学者は、イエスが罪人や徴税人と一緒に食事をされるのを見て、弟子たちに、「どうして彼は徴税人や罪人と一緒に食事をするのか」と言った。
イエスはこれを聞いて言われた。「医者を必要とするのは、丈夫な人ではなく病人である。わたしが来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。」
イエスはこれを聞いて言われた。「医者を必要とするのは、丈夫な人ではなく病人である。わたしが来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである。」
律法学者たちが「言った」ところは ἔλεγον すなわち未完了過去で、継続ないし反復を表す。イエスが「聞いて言われた」のは ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς λέγει で、こちらは ἀκούσας がアオリストだから一回限りの動作である。
ぶつぶつ言い交わされるこもった批判と、それに対する明快な答えの対照が、時制からも読みとれる。このあたりが原語にこだわる利得というものだ。
ところで、この流れではファリサイ派の律法学者は「自分たちは招かれていないのか」と憤りを募らせたことだろうが、実は彼らこそ招かれているというのが真理のさらに深い相であり、憤激をさらに高め得る危険なトリックということになる。それを直観すればこその、イエスに対する執拗な害意であったのかもしれない。
Ω