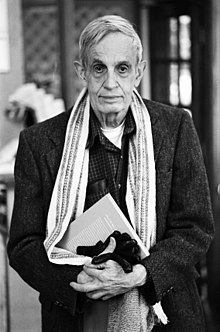2015年5月25日(月)
高校時代にMという友人があり、僕はこいつと驚くほど多くの時間を一緒に過ごした。
言葉の使い方にうるさい男で、相当鍛えられたものである。議論の中でうっかり頭に血が上って、「それは絶対に・・・」などと言おうものなら、即座の失笑と共に辛辣な反問が返ってきたものだ。
「絶対、って、何で言えるの?」
言葉の意味知ってる?国語辞典で引いてごらん、とまでは言わないが、失笑のうちに明らかにそのことがあったのだ。
言葉は正しく使いましょう、アタマも正しく使いましょう、とね。
自衛隊が米国の戦争に巻き込まれて戦闘行為に及ぶなどということは、「絶対にありえない」のだそうである。
一般に「絶対にありえない」という言明は ~ 「人が永遠に死なないことは絶体にありえない」といった一連の限られた命題や、語義矛盾である場合を除いて ~ まずもって成立しない。「絶対にありえない」という主張こそ、ありえない主張である。
さらに進んで、複雑怪奇を本来の性質とする国際政治に関わる現実において、「絶対にありえない」ことなど「絶対にありえない」
M君、これなら文句ありますまい?
そもそも、そういうリスクがないのなら、大騒ぎして法制度を整える必要もない理屈なのだ。
とはいえ、論者の不可思議な自信のありかはうすうす分かっているのである。もしもそういう事態が起きたときには、「あれは米国に巻き込まれたのではない、われわれ自身の平和を守るために必要な行為だったのだ」と言い抜ける、おおかたそういう魂胆であらせられよう。
ウソと坊主のアタマは「絶対に」ゆわない、という次第だ。
M自身の御託宣を聞いてみたいが、彼は僕のブログなんか読みはしない。この点は「絶対に」断言できることである。