2021年3月31日(水)
「罪の文化」vs「恥の文化」というR. ベネディクトの有名な定式について、古くは作田啓一氏が「再考」を上梓したことがあり、21世紀に入ってよりラディカルな批判をぶつけた論者もあるらしい。
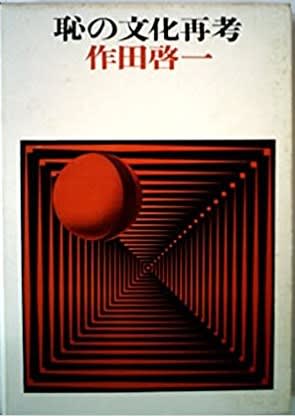
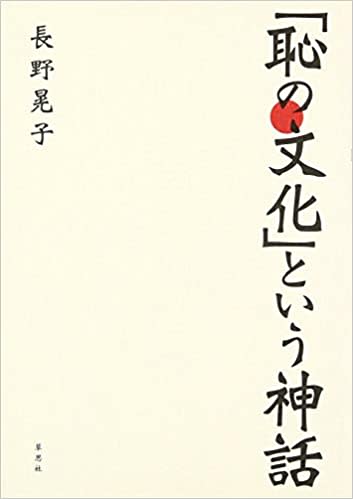
本格的に論じようとすると厄介なことになりそうだが、自分として気に入っている落としどころは比較的単純なものだ。「罪」と「恥」の違いは相対的なものであり、相互移行的なものでもある。「罪」を語るか「恥」を語るかが問題なのではない。「罪」なり「恥」なりがどれほど内面化されているかが問題であり、内面化の程度こそが人のあり方に決定的な違いを生むのである。
「恥」の規範は、「世間の目」に対する恥ずかしさとして語られることが多い。「罪」に対して「恥」の価値を低く見る説もここに注目し、「人が見ていなければ何をしても良い」という低劣なモラルと「恥の文化」を関連づけるのであろう。
しかし「恥」の対象は、何も「世間の目」ばかりとは限らない。その場にいない特定の個人や自身の社会的役割、さらには内面的な信条に照らして「恥ずかしい」ということはいくらでもある。そんなことをしたら「親兄弟の顔に泥を塗ることになる」「教師として恥ずかしい」等といったこと、とりわけかつて多くの日本人がもちあわせていたのは「御先祖様に顔向けできない」という感覚ではなかったかと思う。
このように「恥」の対象が抽象化されるにつれ、恥のモラルはその分だけ「世間体」から離れて内面化されていく。仮に信徒が「十字架で死んでくださった主イエスに申し訳が立たない」と感じるなら、「恥」の言葉で語られていても内実は既に「罪」であろう。「罪とは内面化された恥のことである」という言明は、意味を持たないだろうか。
逆の方向から考えさせられたことが留学時代にあった。セントルイス郊外の長老主義教会、1996年頃のある晩のこと。小さな集まりの中で巨漢牧師のドン・ハウランドが言ってのけた。
「人が見ていてもいなくても同じ行動がとれるかどうか、キリスト教(のモラル)はつまるところその一点にかかってるのさ。」
"That's what Christianity is all about."という彼の言い回しが今も記憶に鮮やかである。
「罪」によって育ってきた彼らであるから、自動的に人目を気にしないなどということはありえない。内面的な規範と「世間体」を意識した行動との乖離は、彼らにとっても日々常在の危険なのである。牧師はそれを踏まえ、他人の視線(=世間体)の在否にかかわらず、内面的な規範に従って行動せよと励ましたのだ。日本人が想像するよりはるかに強く、多くのアメリカ人が他人の視線を痛々しいほど気に病むことは、行ってみればすぐ分かる。
いわゆる「罪 vs 恥」のステレオタイプは、「罪=内面」「恥=外面」という固定観念を前提とし、さらに「欧米=罪」「日本=恥」と決めつけることで完成する。どちらの定式も間違っている。
すると何が問題か?国権の最高機関の公開の場で、ぬけぬけと嘘を語って動じない面々を見て、「罪/恥」論者なら「罪の欠如」と断じるだろう。それでもかまわないようなものだが、せっかくここまで説き分けてきた理屈を使うなら、むしろこの人々は「抽象化された恥の対象」を失ってしまったのだろうと考えてみたい。別に難しい話ではない、公の場で嘘などついて「御先祖様に顔向けできない」などと、この人々が考えていないのは明らかである。あるいは責めを負わされて自ら命を絶った人々の中に、内面化された対象への申し訳なさは今も存在していたかもしれない。
われわれは「恥」という言葉によって「罪」を語り、教えてきた。昭和一桁生まれの父は、明治生まれのその母から「おまえが人の道に外れるようなことがあったら、お墓の前に連れて行っておまえを殺し、私も死んで御先祖様におわびする」と言われて育ったそうである。時代遅れの悪い冗談で済みことか?そうは思わない。問題はわれわれが「恥」を頼みとすることではない。「恥」の対象であり尺度でもある大事な「御先祖様」を失ったことである。
たどたどしく以上に述べたことを、より深く豊かに表現した論説を最近読んだ。執筆者もやはりR. ベネディクトに言及したうえで、「せいぜい半面の真理にすぎない」と片づけている。これをもう少し生かして使ってみたいという、そこだけが当ブログのささやかな主張である。
「死者への畏れと惜別と無念さを見失ったとき、自己を省みるという道徳の内面的契機も喪失する。死者を切り捨てた生者だけの共同体は、利益や快楽にのみ生の充足をみる個人の集合体にしかならないであろう。」
「「魂」を媒介にした死者と生者の交感という観念を排除した戦後社会が、「世間に対する恥」だけをもっぱら道徳の規準にすれば、世間が目前の利益と快楽に耽溺するにつれ、それに合わせればよいということになってしまう。われわれは、戦後70年ほど、そんな道行きをたどってきたのである。」
「そこに東日本大震災が起きたのだった。大拙は、平安末期から鎌倉時代へかけての争乱、疫病、大災害の襲いくる末法の時代に、はじめて日本人は「霊性」に目覚めた、という。私には、10年前の大災害の教訓は、改めてわれわれの「霊性」を思い起こす契機にすることだと思われる。死者への配慮を失い、死生観をまったく失った社会など本当はどこにも存在しないだろうからである。」
佐伯啓思「「魂」はそこにある」 朝日新聞 2021年3月27日(土)
Ω













 隣家の屋根から
隣家の屋根から 地面に降り立つ
地面に降り立つ


 水仙と黄水仙
水仙と黄水仙


 クリスマスローズ
クリスマスローズ

