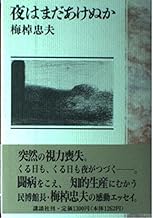…完成まで12年かかるというが、軟弱地盤対策の難工事によって工期はさらに遅れるかもしれない。総工費は3500億円ほどから1兆円近くになったが、もっと膨らむのではないか。完成のころには、今工事を進めている政治家や官僚は引退し、だれも責任をとることはない。そもそも完成するかも疑わしい、と私は見ています。
普天間飛行場を東京に持ってきてごらん。滑走路の長さ約2700㍍は、JR中野駅から阿佐ヶ谷駅までの距離。中野区や杉並区で、住宅街や学校の上空をヘリが飛んだらどうか。
私はそんな風にして、ことあるごとに本土を挑発してきました。飛行機と隣り合う普天間第二小学校では現に、着陸する米軍機のパイロットの横顔が子どもたちから見えるからです。しかし、本土は応えなかった。
2001年の米国同時多発テロの時には「米軍基地が攻撃されるのでは」と、沖縄への修学旅行のキャンセルが相次いだ。でも、沖縄にも子どもたちがいることは話題にものぼらず、気づいていないに等しかった。
どんな迷惑施設を押しつけてもかまわない。基地になれているから。沖縄だから ーー。沖縄に対しては普通の人たちがムチャクチャな考え方をする。日本本土の人たちには「沖縄=2級の国土」という意識があると言わざるをえません。
かつては自民党の政治家にも、歴史への負い目があり、沖縄ととことん向き合いました。今は全く知らない、知ろうともしない世代が台頭しています。
私は1994年から約10年間沖縄に住みました。「帰りそびれた観光客」であり、「勝手に特派員」となって、本土の人たちが知らない沖縄を伝えてきた。沖縄がかわいそうだからでも、沖縄のためでもない。弱者に負担を押しつけて、強者が利を得て、平然としている。そんな日本という国がみっともないからです…
池澤夏樹氏『辺野古工事 誰に利が』2024年4月10日(水)朝刊25面
Ω