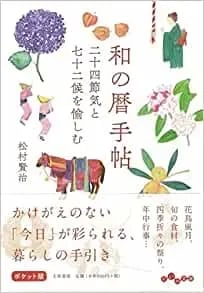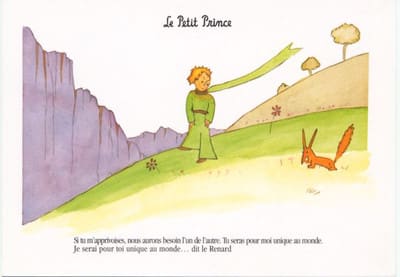2023年12月14日(木)
自分が一人っ子の育ちなので、配偶者は兄弟姉妹の多いに限ると幼い頃から念じており、これはめでたく満願成就した。4人の義兄弟妹とそのまたパートナーたちに恵まれ、今どき珍しいほど姻戚づきあいを楽しんでいる。
いちばん近くに住む義弟夫妻から久々の誘いあり、11月末に中国料理店で会食した。前にも同じ店の似たような卓を囲んだはずだが、前回は気づかなかった壁の書に目が行った。幅2メートルもあろうか、立派なものである。開店祝いに贈られた揮毫であることが読みとれる。

『将進酒』とは李白らしく、また酒家の壁を飾るにふさわしい。詳しい解説が下記にある。
「天生我材必有用」のくだりが力強い。「天我が材を生ずる必ず用有り」すなわち「天が私に才能を与えた以上、必ずやこれを用いる時が来るはずだ」と読むのだが、さらに半歩を進めて「命と人生を与えられた以上、必ずそれを用いる時が備えられる」と解してみたい。死生学的な楽観主義とでも言っておこうか、そのように言い放って李白先生また酒を飲むのである。
今朝になって写真を見直し、この書体は隷書というのだったか、隷書を含む六体(りくたい)とは何だったかと気になって、検索して出てきた画面の一隅に目が吸いついた。「六体千字文」や怪しげな画像に交じって現れたのが…

石丸神社である! この神社に六体地蔵があるので、「六体」の検索語から釣れてきたのだ。
書かれている仔細は、徳川レジームへの移行に伴って1600年代に起きた地域の小紛争、集団憤死ともいうべき事件であるが、わからないのはなぜそこが「石丸塚」と呼ばれ「石丸神社」の名に引き継がれたかということである。トリビアルな事情か、それ以上の何かがあるのか、ネット上ではわからない。
家の伝承が正しければ、伊豫の風早あたりに石丸姓を名乗る我が家の先祖が住み着いたのは1600年代と推定される。謎に包まれたその事情を推理するのに、これまで伊豫河野氏との関係ばかりを考えていたが、隣国の土佐に「石丸」という地名なり人名なりがあり、しかも同じ1600年代に、河野氏と同じく新レジームの勃興に伴って滅亡の道をたどった集団に関連しているとすれば、関心をもたずにはいられない。
名の由来は、すぐにはどうもわからない。行ってみるほかないだろうか。その昔、この名を担って同じ道を往来した人々のあることを思い描きつつ…
Ω