2017年5月23日(火)
5月15日に書き切れなかったこと。沖縄の「返還」という言葉に今では文句も出ないようだが、それが進歩とも思えない。「返還」というからには米国政府が日本政府に「返した」ということで、沖縄の土地と人はやったりとったりされる対象に過ぎず、主体的な存在として扱われていない。あくまで「施政権」の「返還」、県民から見れば「祖国復帰」がスジのはずだ。同僚のO先生が、かつて運動のスローガンとして「沖縄を返せ」と巷で叫ばれた時の違和感を語ってらしたが、同じことである。
もっともここに微妙なアヤがあって、元々の一体性が明白堅固なものであるなら「返せ」でも一向構わないのかもしれない。そもそも沖縄が日本の領土になったのは1872(明治5)年から1879(明治12)年に至る「琉球処分」の結果であり、500年続いた琉球王朝がここで滅亡したのは歴史の中では最近に属する。この時も琉球は一方的な客体として大日本帝国に編入された(「処分」!)。そのように力づくで取り込んだものを戦争でまた別の悪党に奪われたが、後日めでたく返ってきたという言い条からは、「処分」以来の胡散臭さがぷんぷん臭ってくる、それが問題だというのだ。
もちろんこれは他人事ではない。日本という国の有り様、この国とそこに住む人々との関係についての鮮やかな例証であって・・・というようなことを、数年前にかなり詳しくブログに書いた・・・ように思う。ブログの良いところは、書き散らしておけば後で検索できることだから、そのうち見直してみることにしよう。実は何も書いてなかったらショックだな。
***
このGWは松山市北辺の田舎を満喫して過ごしたが、この間ちょっとしたできごとあり。ある朝、表に出ていた父が土間から前の間に上がりながら、「おもしろい人が訪ねてきた」と皆に告げた。遠方からここを目指して来た人があるという。門前で父が誰かと話すような声が聞こえてはいたが、てっきり同じの誰彼かと思っていた。郵便配達や宅急便でもなければ他処の人が訪れることもない、ひたすら静かな田舎である。
ただ、バイパスのさらに向こうの山裾にある寺は臨済宗でそこそこ知られた名刹、加えて史跡らしきものが一つだけある。「河野塚」というもので、わが家の門前がちょうど登り道に当たっており、数年前に松山市が数ヶ所の曲がり角にわざわざ石の標識を立てた。門前から薪炭林や蜜柑畑の間の急坂をひとしきり登るのである。

僕も連れられて登ったことがあるが、たぶん半世紀も前のことで心許ない。地図上は「河野神社」などとなっているらしいがいいとこ祠ぐらいのもので、洞穴めいたものが山腹に口を開けていたような記憶がある。これがどうも、往時の河野水軍ゆかりの何からしいのである。海に向かって西向きの眺望が開ける高所にあり、昔は海岸線が近かったことを考えれば、物見台でもあったのかもしれない。
ともかくこの辺りは往古に水軍を擁して栄えた河野氏の紛れもない根拠地で、松山市に合併される前の北条市からさらに遡る戦前には、一帯を温泉郡河野村といった。わが家の前を流れるのが河野川、500m西には両親も通った河野小学校など、河野の名が土地のそこここに記されている。
歴史の流行らない昨今ゆえ解説が必要だが、河野氏といえば日本中世史上にキラリと輝く存在、いわゆる元寇とりわけ弘安の役に臨み、河野水軍は得意の海上ゲリラ戦で大いに元軍を苦しめた。神風の僥倖で無手勝流の勝利が転がり込んだと思われがちだが、事実は違う。壮絶な玉砕を遂げた対馬の宗氏はじめ西国の武士らは大いに奮戦敢闘した。殊に小回りの利く小船を操って遠来の大鑑を悩ませた河野氏ら水軍の働きは特筆される。彼ら海の雄は、博多湾に築いた防塁の前面の水域で元軍と直接対峙し、その不退転の意気が「河野の後築地(うしろついじ)」と呼ばれ九州の猛将らにも賞賛されたという。
中でも一族を率いた河野通有(みちあり、1250?-1311)は剛勇の誉れ高く、暴れ牛を素手で殴り倒したという大山倍達みたいな逸話の持ち主。執権・北条時宗(ときむね)の信頼厚く、時宗が弘安の役3年後に33歳の若さで他界したときは、墓石にすがって男泣きしたとも伝えられる。河野氏から出た逸材としては、踊り念仏で知られる時宗(じしゅう)の開祖・一遍(1239-89)も特異である。通有の祖父と一遍の父が兄弟という関係かな。時宗の信心は絶対他力の究極形とも言えるユニークなものだが、明治の廃仏毀釈で衰退したらしいのが惜しい。総本山・清浄光寺(通称遊行寺)は、正月の箱根駅伝でランナーを苦しめる坂道の背景として毎年紹介される。
 ← 河野通有(蒙古襲来絵詞より) / 一遍上人像(清浄光寺蔵) →
← 河野通有(蒙古襲来絵詞より) / 一遍上人像(清浄光寺蔵) → 
(両画像、Wiki より拝借)
以上、長い前振り。以下、あらためてその朝の出来事。
***
父が畑回りを終えて朝食に上がろうとしていると、僕ぐらいの年配の男性が門前を通りかかって声をかけた。前述の通り他郷の人がわざわざ訪ねてくる理由のない土地だが、門前の坂を突き当たって左へ上るとの墓地があり、墓参の人々がときどき往来する。突き当たりを右へ上がると河野塚である。

この男性は河野姓の人であった。現在は島根県松江市にお住まいとのこと、先祖が伊予の河野氏であると聞き、GWを利用してはるばる訪ねていらしたのである。善応寺に寄ってみたがあいにく住職が留守で、せめて河野神社を訪ねてみようと思った、河野塚の標識に間違いないかと確かめられた由。面白いのは松江市在住とおっしゃることで、同地は1965(昭和40)年から1968(昭和43)年まで父が(ということは母と僕も)住んだ場所であった。さらに仕事先が農協を介して互いに関連ある組織と分かり(父はN中金、河野氏はKS連)、幾重にも世間の狭さを思わされる。高縄山頂に車で行けるか訊かれたので、目の前のバイパスをひたすら上がるよう教えたと父が言う。そんな人なら名刺なりとも交換したいと考え、すぐ表に出てみたが既に姿がなかった。
GWが明けて東京に帰った後も、どうも気になる。島根KS連の電話番号をインターネットで調べかけてみた。電話に出た男性が親切で、河野姓の人が出向中である旨教えてくれたので、事情を話してこちらの連絡先を託したところ、ものの10分で折り返しかかってきた。間違いなく先日の来訪者とのこと。声が弾む。
聞けば僕とわずかに一歳違い、お生まれは島根県内でも松江ではなくずっと西のH市である。生家の近くにある某寺に「弘安の役に戦功あって河野通有がこの地に所領を与えられた」との縁起が記されており、御一家がその子孫であることを80歳代に入った御尊父が語られるので、「いずれ連れていってやりたいと思い、今回はその下見に日帰りしました」とおっしゃる。GWの混雑を承知で松江から松山への自動車往還、朝食の時間にこちらに着いていたということは前夜の内に発って来られたものか。孝心の篤さに頭が下がる。
何かと情報交換するのも楽しいかと考え、教わった御住所宛に手紙を出したら、数日後には返事をいただいた。いずれお目にかかる機会が楽しみである。
 「竜ヶ城の由来」 T 河野氏撮影
「竜ヶ城の由来」 T 河野氏撮影
***
さて、本項のタイトルに「ミステリアス・トライアングル」と謳った意味が通じるだろうか?西日本の地図を広げ、松江・松山・博多を結ぶ三角形を描いてみる。松山(A)を鈍角の頂とする二等辺三角形で、松山・松江間(AB)と松山・博多間(AC)はそれぞれ200km、松江・博多間(BC)は300km余りの直線距離である。ここに不思議な因縁があるのだ。13世紀末、A地出身の河野氏がC地で祖国防衛のために奮戦し、B地近傍に領地を与えられて一部がそこに移り住んだ。20世紀に至って、先祖代々A地に住み着いてきた石丸の夫婦がC地に滞在し、そこで息子(=僕)をもうけた。親子はその後B地にも住み、今はA地に戻っている。そこへ13世紀末以降B地にあった河野氏の当代が、父祖の地を求めてやってきた。双方の親子はそれぞれほぼ同世代に属する・・・
何を面白がっているかって?そうだね、大したことではないかもしれない。しかし河野氏の松山訪問から2週間後に、かねて予定の講演のため、60年前に自分の生まれた博多の地を踏んだ僕としては、けっこう不思議な感じがしたのだ。古の河野氏が松山・博多・松江(島根)の間に結んだ三角形の縁に沿って、末裔らが往来邂逅している。誰のどういういたずら心が仕組んだものか。
どうも不思議である。

Ω














 ← 雄 / 雌 →
← 雄 / 雌 → 

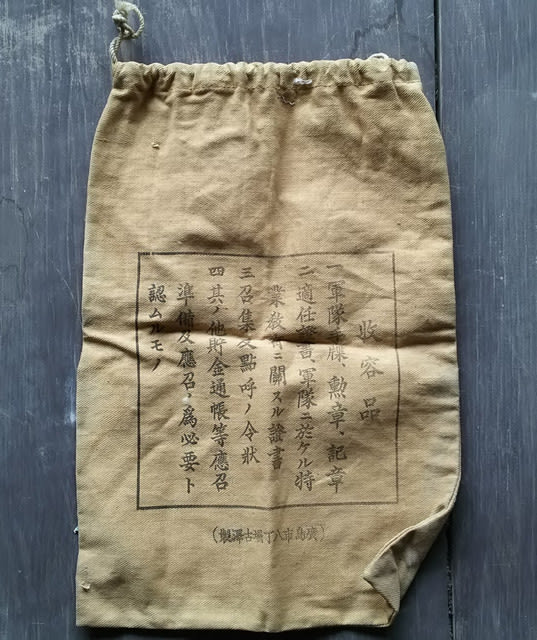




 「竜ヶ城の由来」 T 河野氏撮影
「竜ヶ城の由来」 T 河野氏撮影
 http://snakehabu.web.fc2.com/maketrap.htm
http://snakehabu.web.fc2.com/maketrap.htm