昨日、S君が送ってくれていた朝のメール:
おはようございます。今日6月28日はサラエボ事件がおこった日、そしてベルサイユ講和条約が結ばれた日だそうです。
第一次世界大戦の始まりと終わりが、同じ日だったのか。
*****
そういえば、誕生日に亡くなる人がときどきある。
有名なところでは、シェイクスピアかな。
・・・いまWikiを見ると、「正確な誕生日は不詳」とある。
1564年4月26日に洗礼を受けた記録があるから、この日までには生まれていたわけだ。命日は1616年4月23日。謀殺説というのがあったな。
誕生日に亡くなった人を、もうひとり知ってると思っていたが、記憶違いだった。
サミュエル・クレメンスこと、マーク・トウェイン。
1835年11月30日 - 1910年4月21日だから、同じ日どころか、かけ離れている。
何でかなと考えて、わかった、思い出した。
マーク・トウェインは、ハレー彗星がやって来た年に生まれ、次にやって来た年に死んでいるのだ。しかもその日というのが、
ハレー彗星の最大接近日 ・・・ 1835年11月16日
マーク・トウェインの誕生日 ・・・ 同11月30日
ハレー彗星の最大接近日 ・・・ 1910年4月20日
マーク・トウェインの命日 ・・・ 同4月21日
どちらも非常に近い。このことと混同したのだ。
没年については、トウェイン自身、強く意識していた。
「ハレー彗星が再びやってくるその時に、自分も人生を終えたい。それを過ぎて生き延びるなら、自分にとって大きな落胆となるであろう。」
というようなことを、どこかに書きのこしている。
米国ミズーリ州ハンニバル、セントルイスからドライブで2時間余のこの小邑は、僕の大好きな場所だった。マーク・トウェインが生まれ育ったここには、彼の小さな記念館がある。3年間の滞在中に6~7回も出かけただろうか。
途中の道沿いが、ハックルベリー・フィンを生んだアメリカ中西部の原野である。
この記念館に、確かハレー彗星のことも書いてあった。
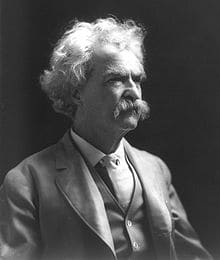

*****
今日はCMCCの総会だが、残念ながら出席できない。
この活動は現在、東京・横浜・三重に限られている。
大きく拡げることはできないか。
そういう幻が先日からちらついている。
おはようございます。今日6月28日はサラエボ事件がおこった日、そしてベルサイユ講和条約が結ばれた日だそうです。
第一次世界大戦の始まりと終わりが、同じ日だったのか。
*****
そういえば、誕生日に亡くなる人がときどきある。
有名なところでは、シェイクスピアかな。
・・・いまWikiを見ると、「正確な誕生日は不詳」とある。
1564年4月26日に洗礼を受けた記録があるから、この日までには生まれていたわけだ。命日は1616年4月23日。謀殺説というのがあったな。
誕生日に亡くなった人を、もうひとり知ってると思っていたが、記憶違いだった。
サミュエル・クレメンスこと、マーク・トウェイン。
1835年11月30日 - 1910年4月21日だから、同じ日どころか、かけ離れている。
何でかなと考えて、わかった、思い出した。
マーク・トウェインは、ハレー彗星がやって来た年に生まれ、次にやって来た年に死んでいるのだ。しかもその日というのが、
ハレー彗星の最大接近日 ・・・ 1835年11月16日
マーク・トウェインの誕生日 ・・・ 同11月30日
ハレー彗星の最大接近日 ・・・ 1910年4月20日
マーク・トウェインの命日 ・・・ 同4月21日
どちらも非常に近い。このことと混同したのだ。
没年については、トウェイン自身、強く意識していた。
「ハレー彗星が再びやってくるその時に、自分も人生を終えたい。それを過ぎて生き延びるなら、自分にとって大きな落胆となるであろう。」
というようなことを、どこかに書きのこしている。
米国ミズーリ州ハンニバル、セントルイスからドライブで2時間余のこの小邑は、僕の大好きな場所だった。マーク・トウェインが生まれ育ったここには、彼の小さな記念館がある。3年間の滞在中に6~7回も出かけただろうか。
途中の道沿いが、ハックルベリー・フィンを生んだアメリカ中西部の原野である。
この記念館に、確かハレー彗星のことも書いてあった。
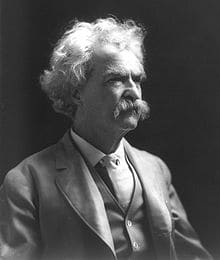

*****
今日はCMCCの総会だが、残念ながら出席できない。
この活動は現在、東京・横浜・三重に限られている。
大きく拡げることはできないか。
そういう幻が先日からちらついている。











